第39回受領者紹介
特別テーマ
助39-01
人工光合成を加速する固-固界面制御分子素子の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年深刻化する地球温暖化・エネルギー問題を背景に、再生可能エネルギーの利用は持続発展可能な社会構築に欠かせない必須課題となっている。半永久的に利用可能な太陽光エネルギーと地球上に多量に存在する水から、クリーンエネルギー源である水素を作り出す「太陽光水分解」は人工光合成とも呼ばれ、本多-藤島効果の発見から盛んに研究されてきた。これまでの膨大な研究により、酸素生成および水素生成光触媒を組み合わせたZスキーム型光触媒が、太陽光-水素エネルギー変換効率(STH)において1%を超え、実用化への期待を大いに高めている。しかし実用化には10%を超えるSTHが必要であり、これまでの光触媒開発とは異なる視点に基づいた新しいアプローチが求められている。
②目的
本研究では光触媒材料の潜在能力を現在まで引き出すべく、光触媒-固体電子伝達剤が接触する固-固界面に、自己集積性に優れた機能性分子からなる分子素子を形成させ、分子の多機能性(光吸収・酸化還元・自己集積能)を駆使することで、電荷分離を担う固-固界面構造の精密制御を目指す。本戦略の狙いは、1)正孔/電子を選択的に受容可能な色素分子からなる多層膜を光触媒の結晶面選択的に形成させ、色素増感機構と連動させた協奏的界面電荷分離によって光触媒材料の潜在能力を限界まで引き出し、2)色素多層膜表層の分子間相互作用により固体電子伝達剤を面選択的に捕捉することで、逆電子移動を誘発しない円滑なキャリヤー輸送界面を創出する、の2点に集約される。
助39-02
CO2電気化学還元に選択的に駆動する電極触媒開発と作動機構解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
CO2電気化学還元はCO2を原料として我々が必要とする基礎化学品を合成できるため、2050年代にカーボンニュートラルを達成するために必須の要素技術として近年注目を浴びている。1990年代に堀善夫教授(千葉大学)らが一連の金属電極についてCO2電気化学還元を検討しており、金属の種類によって生成物が4つのパターン(H2,CO,HCOOH,CH4などの炭化水素)に分類できることが報告されている。すなわち、CO2電気化学還元はうまく電極触媒設計をすれば、CO2を減らしながら必要なものを選択的に得られる可能性が高い。最近になって欧米の研究者によってその価値が再認識されているが、結果がまちまちであり過去の結果とは異なった結果も報告されている。これは電極触媒設計において我々がまだ知り得ていないファクターがあることを意味する。実際、堀先生に直接問い合わせたところ、過去には他の研究室では再現性が取れない例もあったようである。これは電極の表面処理方法によって反応活性や選択性が大きく変わることを意味している。申請者は触媒化学者の観点から電気化学を俯瞰しており、電極表面における活性点の存在の有無を議論し、電極表面のCO2の活性サイトが活性・選択性に大きな影響を与えることを掴んでいる。
②目的:課題設定とねらい
本研究における最終目標は、太陽光や風力など再生可能エネルギーを利用して発電した電気によって、二酸化炭素(以下、CO2と表記)を有用な物質へと変換可能な金属電極触媒を見出し、2030年代での本格的な検討及び2050年代の社会実装を目指したCO2電気化学還元系を可視化することである。可視化とは、地球上に豊富に存在する太陽光と海水を利用して、温室効果ガスの排出量の大部分を占めるCO2を原料とした革新的反応プロセスを触媒回転数・量子効率・ファラデー効率で評価するにとどまらず、COやCH4などのCO2の還元生成物の実際の生成速度・濃度を評価基準とし、将来的な社会実装へとつなげられる研究基盤を作ることを意味する。このような研究基盤を作る一環として、本研究では金属ナノ粒子電極触媒の開発に注力し、高い選択率でバラエティに富んだ生成物を製造可能な金属活性種のデザインを試みる。
基本テーマ2
助39-03
局所配位構造・結合状態に立脚したHfO2基薄膜の強誘電相の安定化メカニズムの解明と強誘電性の向上
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
非接触型ICカードシステムに代表される強誘電体メモリ、振動発電に代表されるエネルギーハーベスティング、低消費電力圧電トランジスタなど、強誘電体・圧電体は社会に大きな役割が期待されている。しかし、現在実用化されている材料はPb系ペロブスカイト型結晶が主流である。しかし、超薄膜化やナノ結晶化したときにサイズ効果によって自発分極が消失するサイズ効果が生じる。一方、環境問題に関連して非Pb鉛系強誘電体材料の開発が注目されているが、Pb系に匹敵する特性を持つ材料は未だ見つかっていない。ところが、蛍石型構造をとるHfO2基固溶体においてこれまでの常識を覆す極性直方晶相が発見され、実用に耐える強誘電性を示すことが明らかになった[T.S. Böscke et al., Appl. Phys. Lett., 99, 102903 (2011)]。従来不可能と考えられていた膜厚3 nm以下でも強誘電性や圧電性が発現し、分極が消失しない特異な強誘電特性を示す。このペロブスカイト型強誘電体の最大の弱点を本質的に解決できるHfO2基強誘電体の可能性が注目されている。申請者らは、世界に先駆けて(Hf,Zr)O2などエピタキシャル成長を実現するともに、その特異なドメイン構造を明らかにした[T. Shimizu, T. Kiguchi, Appl. Phys. Lett. 107, 032910 (2015), T. Kiguchi et al., J. Ceram. Soc. Jpn., 124 (2016), T. Kiguchi, et al. Jpn. J. Appl. Phys., 57(2018).]。しかし、極性直方晶相は準安定相であるので常誘電性の安定相である単斜晶相へ構造相転移を起こしやすく正味の強誘電性発現の妨げとなる。よって、デバイス化に向けた強誘電・圧電特性の発現とその向上をのために、極性直方晶相の相安定正の理解は喫緊の課題である。
②目的:課題設定とねらい
これまでの研究から、極性直方晶相の安定化には3つの因子、すなわち、(1)ドーパントによるミクロな配位構造の乱れ(化学的歪み効果)と基板による(2)ミクロおよび(3)マクロな弾性的拘束(物理的的歪み効果)が挙げられ、いずれが欠けても極性直方晶相を保持できない。HfO2は高対称性側から立方晶相→正方晶相→単斜晶相と相転移することが知られ、極性直方晶相は、単位胞の外形は正方晶相に類似している。しかし、重要な点は原子配列が高温相である正方晶相ではなく低温相の単斜晶相に極めて類似しており、酸素イオンがカチオンに7配位するという特異な配位構造を取る。したがって、極性直方晶相の相安定性には、7配位構造をとり、かつ単斜晶相への相転移に伴う巨大剪断変形を抑制するドーパントが必須となる。しかし、極性直方晶相は同じ7配位構造のより安定な単斜晶相へ容易に相転移するため、この相転移のエネルギー障壁を増加することができれば速度論的に単斜晶相への相転移を抑制できるはずである。このドーパント効果に関する研究は多くなされているが、相安定性の議論は第一原理計算によるところが大きく、実験的な検証は脆弱な状況にある。特に、第一原理計算の研究では、無歪み状態や等方的な静水圧効果の検証はなされているものの、基板による2次元応力状態での相安定性の議論はなされていない。また、実験的な検証では格子定数変化や原子間隔のマクロな変化を現象論的に議論しているに過ぎない。本研究では、局所構造がHfO2やZrO2の極性直方晶相の相安定性に及ぼす効果をダイレクトに検出する手法として走査透過型電子顕微鏡による収束電子ビームを利用した電子エネルギー損失分光(STEM-EELS)法に着目し、原子-単位胞スケールでZr/Hf-O間の化学結合状態、Hf-O8, Zr-O8立方体配位構造、ドメイン構造など局所欠陥構造、および歪み状態に基づいて相安定性を明らかにすることによって、これまで経験的に探索されてきた極性直方晶相の相安定性の根源的な解明を目指す。
助39-04
1~2トランス次元系の設計・創出と電子物性
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ムーアの法則に象徴される電子デバイスの微細化が、連綿と続くデバイスの高機能化を支えている一方で、現在のシリコンをベースとしたデバイスの微細化が限界を迎えつつある。この限界は、これまでのシリコンデバイスを単に小さくしていくというアプローチでは避けることができず、「これをいかに打破するのか?」が大きな問題となっている。この解決には、新構造・新原理トランジスタの開発に加え、シリコンに代わる新材料の導入が有望視されている。
一方、厚さが1 nm以下の極薄の二次元半導体である原子層が注目を集めている。これらは、層状構造をもつ半導体の1層分に相当する物質であり、1 nm以下の極限的な薄さにも関わらず、ゆらぎのない均一な厚さとバンドギャップをもつ。これは極微細デバイスの実現のため極めて望ましい特徴であり、実際サブ5 nmの微細ゲート長デバイスでシリコンを凌駕する性能を示すことが理論的に示されている(Nano Lett. 11, 2368 (2011))。
②目的:課題設定とねらい
先端薄膜成長技術による原子層超構造の開発を軸に、原子層の次世代デバイス材料としての可能性を実験的に示すことを目的とする。具体的には、独自開発の結晶成長装置(MOCVD法)を適用することで、サブ10 nmの正確さで構造制御した新規原子層接合超構造の合成法を確立する。これらは、二次元と一次元の間にある次元性をもつ新規ナノ構造体であり、「1~2トランス次元構造(1-2TDS)」とも呼べるものである。続いて、1-2TDSをチャネルとするトランジスタの評価を通して、実効的にゲート長が1~10 nmの原子層デバイスの動作を実証する。
助39-05
糖尿病予防に向けた無線式糖度計測レンズの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
コンタクトレンズは、屈折異常を矯正して視力を補強するウェアラブルな高度医療機器としての利用が一般的であったが、近年、これらレンズと電子デバイスを組み合わせることで「視る」から「診る」を実現可能なスマートコンタクトレンズの開発が盛んである。とりわけ、世界で失明原因第一位である糖尿病(網膜症)を検出する医療機器開発は、疾患予防や遠隔在宅診療を実現する点で「健康寿命の延伸」や「医療費削減」への期待が高い。さらに、国内における糖尿病の患者数は、1000万人以上に達しており、その開発は必至である。年々増え続ける患者数と共に、市場規模も大きくなっており(2019年時点で3700億円)、さらに、デバイスのウェアラブル化に伴い新たな市場を視野に入れると、その市場はとても大きいと言える。
しかしながら、糖尿病に関わる涙中糖度(グルコース)計測の実現は、以下の3つの課題を克服する必要があった。
涙に含む生化学物質は超微量(涙の分泌量:3 ml min-1 cm-2)かつ低濃度(糖度:0.01~0.30 mMほど)であるため、高感度な糖度センサを必要とする。
上記の生体情報を眼という限られた微小空腔内で取得する必要がある。特に、眼への装着を想定する場合、安全性と装用感を考慮してコンタクトレンズへ搭載するセンサ回路を設計する必要がある。また、コストを抑えた使い捨てタイプが望ましい。
生体センサとリーダー(検出器)が実用的な距離(主に0.1~100 cm)、かつ、正確に検出生体情報を伝える無線通信システムの開発が必要である。
②目的:課題設定とねらい
本提案課題は、上述した3つの課題を克服する新しい原理の高感度・高利得な無線式糖度計測レンズの開発に加え、動物実験と組み合わせたリアルタイム計測・分析システムを開発することを主たる研究目的とする。
助39-06
超音波と液晶を用いたフィルム型多機能レンズ
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高速で画面奥行き方向(光軸方向)に移動する物体をカメラで撮影する場合、常に撮影対象にピントを合わせる必要があり、そのためにはアクチュエータとギア機構を通じてレンズを連続的かつ高速に光軸方向へ移動させなければならない。一方で、スマートホンなどの小型電子デバイスに搭載されるカメラモジュールは、4,5枚のプラスチックレンズとこれらのうちのいずれかのレンズを動かすためのアクチュエータで構成され、2021年現在モジュール厚みはおよそ5 mm、応答速度は数10 msである。今後のデバイスの高機能化を考えると、カメラモジュールの応答速度の高速化と小型・薄型化の両立は今後のブレイクスルーとなる可能性を秘めている。一方、現在ディスプレイ用途で幅広く使用される液晶は、厚さ数〜数十μmの薄い領域で急激に屈折率を変化することが可能であり、薄型の可変焦点レンズとしての応用が期待できる。しかしながら液晶デバイスでは一般的に、外部からの電界によって液晶配向を変化させ光学屈折率を制御するが、電界を加えるための透明電極が必要であり、これにはレアメタルであるインジウムを要する。
②目的
本研究では、透明電極を用いることなく、超音波によって厚み数10 μmの非常に薄い範囲の液晶配向を空間的・時間的に高速制御する技術について検討する。液晶中を音速で伝搬する超音波により液晶配向を強制的に制御するため、従来技術である電界型と比較して1桁程度速い時間応答が期待できる。屈折率分布を高速に制御可能な本技術を光学レンズに応用すれば、レンズの位置を動かすことなくその焦点位置を変化可能なレンズ、すなわちアクチュエータを必要としないフィルム型可変焦点レンズを実現できる。
助39-07
細胞内微小金属粒子形成による放射線治療の効率化
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
放射線は治療に関するパラメータ(線種、線量、線量率、LETなど)の時空間的な設定を任意に行える唯一無二の特質を持つ。その効果を最大限に引き出すためには殺細胞効果のがんへの局所化が必要不可欠であるが、本学では動体追跡、スポット照射および陽子線を組み合わせた「陽子線治療センター」を設立し、物理化学的アプローチによる局所制御を追求してきた。さらなる「局所化」のためには、生物学的アプローチによるがん特異的な増感やがん細胞の高感度な検出などが求められる。
②目的
本研究では、磁性細菌が内部に形成する鉄微粒子をがん細胞内部に形成させCTやMRIでの検出感度を高めると同時に、放射線治療の効果を増大させるための方法論を確立する。磁性細菌において鉄微粒子の形成に寄与する種々の遺伝子群をがん細胞に発現させ、最も効率よく粒子を形成する遺伝子の組み合わせを決定する。最適化した遺伝子群をがん細胞のみで自己増幅するウイルスに組み込み、生体内におけるがん特異的な鉄微粒子の形成誘導を試みる。
助39-08
人工知能による人間支援デバイスを用いた次世代型口腔がん検診システム構築のための基盤研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
口腔がんは舌や歯肉など「口のなか」に発生するがんの総称であり、日本においては罹患数だけでなく、死亡数も増加傾向にある。口腔がん死亡数を減少させるためには、早期発見・早期治療が最も重要であるが、口腔がんの多くが、進行した状態で高次医療機関に紹介されているという現実がある。つまり口腔がんを早期に発見し、遅滞なく高次医療機関に送るために、地域の歯科医師会等による集団検診が行われてきたが、一人一人を視診・触診により診察するため、検診人数も限定的であり、決して効率的な検診とは言えないのが現実である。また視診・触診は、口腔がんのスクリーニング方法として確立している唯一の方法ではあるものの、その精度は検診者の経験によるところが大きく、粘膜を診察する経験が少ない検診者の場合は、決して高精度とは言えない検診が行われているのも現実である。
口腔がんを早期に発見し、遅滞なく高次医療機関に送るためのシステムは未だ確立していない。そこでわれわれは、簡便かつ効率的、そして経験によらない高精度な口腔がん検診を確立すべく、またスクリーニングの際に必ず問題となる偽陽性問題も全て解消すべく、以下のシステムの発案に至った。すなわち唾液と人工知能(AI)を組みわせた効率的な一次スクリーニングの後に、かかりつけ歯科医院でのAI搭載型口腔粘膜診断装置による高精度な二次スクリーニングを行うという、AIによる人間支援デバイスを用いた口腔がん検診システムである。
②目的:課題設定とねらい
本研究は、質量分析装置をベースとした網羅的高感度測定技術とAI技術を用いて、既に同定してある口腔がんを高精度にスクリーニングする唾液中バイオマーカーを中心とした検証・探索研究を行う。また並行して、少数データから高性能を実現するAI技術を用いて口腔がんを高精度に判別する判別ソフトウエアを完成させる。この2つを行うことで、口腔がん疑い患者の一次スクリーニングから、かかりつけ歯科による、高精度な診断に限りなく近い二次スクリーニングまでを行う、AIによる人間支援デバイスを用いた新たな口腔がん検診システムの確立を目的とした研究である。
助39-09
高速画像センシングによりヒトの運動能力を引き出すマン・マシンシステムの研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
自分自身が現存する場所とは異なった場所に自分の存在を感じ、その場所で自在に行動する遠隔ロボット(アバターロボット)に関する研究が盛んに行われている。我々の研究グループでも人がロボットに没入し遠隔操作を行う研究や [Zhu, Aoyama, IEEE RA-L 2020 等]、ロボットをあたかも自分の身体の一部のように感じ操作する「ロボット身体化」に関する研究を行ってきた[Aoyama et al., AR 2019 等]。これらの研究が発展していき、遠隔ロボットを自分の身体のように感じるようになり、我々が活動する生活空間がスマート化されていくものと考えている。このような遠隔ロボットの研究開発は、国内外の多くの研究機関やスタートアップで研究開発されており、推進すべき重要な課題となっている。これまでの遠隔ロボットに関する研究では、操作する側の「人 (マスター) 」と操作される側の「ロボット (スレーブ) 」間の違和感をなくすべく、通信時間遅れの問題や視覚・触覚フィードバック能力の向上を中心とした課題が取り組まれてきた。
②目的
本研究はこれまでの研究から一歩進んだ発想で、高速画像計測による少し先の未来を予測する「未来視」を基盤とし、ロボットを操作する「人」の能力を超えた動作を操作される側の「ロボット」が実現するシステムについて研究開発する。まるで、映画「マトリックス」において人が仮想世界で人間の能力を超越した運動を行っていたように、サイバー空間を通して、現実世界で人が生来持つ能力を超えた運動を実現しようというアイディアである。また、提案するシステムが人の運動能力や運動学習記憶に与える影響を行動神経科学に基づき調査する。
基本テーマ1
助39-10
新物質探索によるスキルミオン物質空間の拡張
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景 ②目的
半導体素子や磁気記録デバイスに代表される機能性電子材料は電子の基本的自由度であるスピン・電荷・軌道を理解し制御するものであり、現代社会を支える基盤である。一方、持続可能な社会の実現に向けて、従来の機能性材料に比して革新的な省エネルギー電子材料の創成が求められてきた。
2009年に固体中で観測されたスキルミオンは、従来の基本的電子自由度の制御に基づいた機能性材料に変革をもたらす可能性から大きな注目を集めている。スキルミオンは電子スピンの配列が作る渦状構造であり、トポロジー学の観点から安定性が担保される磁気欠陥である。スキルミオンは、生成と消滅を任意に制御することが可能であり、また近年盛んに研究されてきた強磁性体中の磁壁操作メモリに比べると、1000分の1程度の電流密度でスキルミオンを操作することが可能であるため、革新的な省エネルギーメモリデバイスの創成に発展すると期待されている。一方、従来の研究からスキルミオンの創発には「反転対称性の破れた結晶構造を有する物質であること」、「Dzyaloshinskii–Moriya (DM)相互作用が働くこと」など、その実現可能性には厳しい制限が課されていたため、スキルミオンが発現する物質は限られていた。
2021年にM. Hirschberger、速水、十倉による新しい理論(以下、新理論と呼称)が提案された[1]。この理論はスキルミオンエレクトロニクスに大きな前進をもたらす知見を含んでおり、結晶構造に反転対称性の破れがない物質においても「異方的交換相互作用が有効に働くこと」によりスキルミオンが生じることを明らかにした。つまり、一般的な反転対称性のある物質や絶縁体を含む広い物質空間においてもスキルミオンが生じる可能性を示唆している。
本課題は、新理論に基づきスキルミオン創発空間を拡張し、スキルミオン材料科学の発展に貢献することをグランドビジョンとし、具体的には 1.申請者の先行研究によって発見したモデル物質Gd3Os4Al12について物性評価を行い新理論を検証すること、2.空間反転対称性を有し、且つ異方的交換相互作用が働く新規モデル物質を開発しスキルミオンを実験的に観察することを研究期間における目的とする。
当該理論は2021年に提案された新しいモデルであり、この理論を検証する新物質の開発はまだ始まったばかりである。申請者は先行研究で理論を検証可能な新物質Gd3Os4Al12の開発に成功しており、このことは本研究の独創性を担保している。本課題を達成し、多彩な物質において新理論に基づく創発スキルミオンを実証することは、従来知られていたスキルミオン発現条件を広げることを意味しており、トポロジカル欠陥としてのスキルミオン生成がより普遍的な現象であることを示す。スキルミオンメモリデバイスの省エネルギー性は持続可能な社会に欠かすことのできないものであるため、本研究によりスキルミオン創発物質空間を拡張することができれば新たなデバイスの開発を加速度的に進めることが可能となり、革新的材料に支えられた豊かな社会の実現に寄与すると期待される。
助39-11
ノンコリニア反強磁性の電流誘起高速ダイナミクスの直接観測と新機能スピントロニクスデバイスの創製
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景 ②目的
電子の“電荷”と“スピン”の両方を活用することによって生じる新規物理現象の発見やデバイス応用を目指すスピントロニクスでは、“磁気構造の電気的制御”が最重要課題である。従来、磁気構造として強磁性体の磁化が研究されてきたが、近年、磁化がゼロの反強磁性体が注目を集めている (反強磁性スピントロニクス)。反強磁性体は一般的に高速動作・高密度化が可能であるが、正味の磁化がゼロであるため電気的に磁気状態を検出するのが難しいという課題がある。この課題の解決に向けてスピン構造が非共線的(ノンコリニア)な構造を有するノンコリニア反強磁性体に注目が高まっている。ノンコリニア反強磁性体は磁化がゼロであるにもかかわらず、巨大な異常ホール効果を有するなど特異な物理現象が観測され、かつ電気的検出が容易であるため様々なデバイス等への応用が期待されている。
このような中で、最近、申請者らは世界で初めてノンコリニア反強磁性体Mn3Snのエピタキシャル薄膜の作製に成功し[J.-Y Yoon, Y. Takeuchi et al., Appl. Phys. Express (2019), 研究業績1]、次いでMn3Snに直流の電流誘起トルクを作用させることで、ノンコリニア磁気構造の恒常回転の兆候を観測した[Y. Takeuchi et al., Nat. Mater. (2021), 研究業績2]。このスピン構造の回転現象は従来の共線(コリニア)磁気構造の磁性体には見られないノンコリニア反強磁性体特有の現象である。一方で、応用上重要となるノンコリニア反強磁性体にRF信号や短パルスの信号等を入力したときの磁気構造の応答や高速ダイナミクスについては未解明のままである。そこで、本研究では、ノンコリニア反強磁性体の高速ダイナミクスを直接観測してその機構を解明し、その特異な磁気応答を利用した新機能デバイスへ展開することを目的とする。
助39-12
少数の受信信号データに基づく複数ネットワークによる抽出特徴量の最大化と人工データセットの生成
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
Society5.0の実現を目指す上で、サイバー・フィジカル空間をデータにより密接に結ぶデジタルツイン技術の発展に伴い、無線通信における機械学習の応用はますます重要性を増してきている。現在まででは、学習に使用される信号のデータセットには膨大な数が要求されるため、データセットをシミュレーションで生成し評価を行う検討が大多数となっている。しかしながら、無線通信シミュレーションでは統計的に伝搬路を生成するため、現実環境との剥離は避けられない。このギャップを埋め、実用に耐えうる評価を行うためには、実際に測定された受信信号データが必須ではあるが、無数に存在する伝搬路に対し学習要求を満たすほどのデータの収集は容易でない。そのため、極めて現実環境に近い受信信号のデータセットを共有・提供することは無線通信を基盤とした社会の発展に大いに貢献し得る。
②目的
本研究では、極少ない現実の通信環境の測定データでも十分な学習を可能とする擬似的な信号データセットの生成を目指し、無線信号の特質に適った高精度な敵対的生成ネットワークの構築を行い、生成したデータセットの有効性を明らかにする。
助39-13
メゾスケールトポロジカル発光マテリアルの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
環状分子をいかなる結合をも用いずにメカニカルに重合させることで得られるポリカテナン(カテナは鎖の意)は、従来の高分子よりもはるかにダイナミックな動きを実現することができ、剛直さとしなやかさを兼ね備えた次世代の高分子材料として期待される。我々の身の回りにおいても、金属(剛直)からなる鎖(しなやか)が多く利用されていることが、同様の構造がナノスケールでも有用であることを物語っている。しかしながら、ポリカテナンの合成は未だ極めて困難であり、世界でまだ一例が知られるのみである(S. J. Rowanら、Science 2017, 358, 1434)。また、得られたポリカテナンはポリマーであるが故に結晶化できず、その構造や分子レベルでの性質に関して深い知見は得られていない。このような状況の中、申請者はつい最近、分子が自発的に集合する現象(自己組織化)を利用した極めて簡便な手法により、顕微鏡で観察可能なスケールのポリカテナンを世界で初めて構築することに成功した。
この成果は、極めて複雑な微細ナノ構造の構築と可視化に成功したというだけでなく、“二次核形成”と呼ばれる現象を分子の新たな自己組織化制御法に利用したことで話題を呼んでいる。すなわち、数千個のπ電子系モノマー分子からなるリング構造に逐次的にモノマー分子を加えると、リングの内部から次々と新たなリングが二次的に自己組織化するために、高確率で連結する。本成果は、一種類の分子が階層的に自己組織化して自発的にポリカテナンに至るという点で、従来の自己組織化の概念を大きく変革する成果として、Nature誌のNews&Viewsをはじめとして各種メディアで広く紹介され(Nature 2020, 583, 361)、大きな反響を呼んでいる。
②目的
本研究では、上記の「自己組織化ポリカテナン」を基軸に、わが国発のメゾスケールトポロジカルソフトマテリアルを世界に先駆けて開発することを目的とする。そのため、ポリカテナンを光物性および構造の両面から強化する。光物性に関しては、発光特性の強化を図る。構造に関しては、リング構造の外殻(シェル)の重合により機械的な強度の増強を図る。発光特性と構造が強化されたポリカテナンに対し、メゾスケール(10〜1000nm)での機械的運動と発光特性の変化を精査する。
助39-14
有機合成に頼らない有機EL材料開発:アントラセン発光体分子のナノ空間閉じ込めによる発光色変調
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
有機物の電界発光(EL)現象を利用した有機ELディスプレイは、高画質(高精細・高コントラスト比)、高速応答性、フレキシブル(曲げられる)性を有し、従来のディスプレイを遥かに凌ぐ情報交換機能を次世代スマートフォン・テレビに与えることができる。有機ELの発光材料には、ベンゼン環を基本単位とする特定の分子が用いられる。発光挙動制御に対するこれまでの戦略は、「特別な有機分子を合成する」ことに大きく依存してきた。およそ35年間の研究蓄積によって膨大な数の発光体分子が開発され、発光挙動制御のための分子設計に関する学理も十分に整っている。しかし、有機EL材料開発は次の2つの内在的な問題によって頭打ちになりつつある。
色純度が低い(=発光スペクトル幅が大きい)ため、再現できない色が存在する。
複雑な有機分子の生産には高環境負荷の化学プロセスを必要とすることが多い。
以上の課題を克服する、有機EL材料開発のための新たなパラダイム・戦略が切望されている。
②目的:学術的独自性と意義
本研究では、従来の合成化学的手法とは一線を画し、発光性有機発光体分子を結晶性アルミノケイ酸塩の孔内に導入することによる発光挙動の自在な制御を目的とする。結晶性アルミノケイ酸塩は[SiO4]4-四面体ネットワークによって構築され、3次元細孔構造および2次元層状構造などの様々な「孔の形」を作り出す。一部のSi4+はAl3+に置換しており、Al3+は孔の壁面の「電子源の位置」として作用する。この孔に有機発光体を密接させると、発光挙動は「孔の形」と「電子源の位置」の影響を受ける。申請者がこれまでの無機固体合成化学、ホスト-ゲスト化学分野で培った能力を集結して、このような有機発光体が孔に「ぴったりと嵌め込まれた状態」を創出する。これにより『ナノ空間閉じ込めによる発光色変調』を目指し、学理探究および有機EL材料開発への応用を目指す。
助39-15
光によって低侵襲的な脱着を可能とする矯正歯科用接着剤の開発に関する研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
歯科では治療用器具を歯質表面に直接「接着」する治療が行われており、接着は現在の歯科治療の基盤技術である。湿潤環境の口腔内で歯の表面に材料を接着する技術は40年以上前より研究が進められおり、歯質表面のカルシウムに結合する接着性モノマーの開発がブレークスルーとなって、歯質へ安定して人工材料を接着する技術が確立された。歯科用接着剤はう蝕治療などにおいて長期間金属やレジンを歯質表面に固定するだけではなく、矯正治療のように歯質に治療用器具を短期間だけ固定する場合にも用いられている。しかし、強固に固定された治療具を歯質表面から脱着するための方法は、力学的な剥離、脱着以外の選択肢がないのが現状である。矯正用治療器具(ブラケット)を脱着する場合に、力学的な脱着では歯質再表面のエナメル質も同時に剥離してしまい、エナメル質が損傷することが問題視されている。エナメル質は再生しないため、エナメル質の損傷は健康な歯を生涯維持するための大きな障害となる。よって、脱着を容易にする新たな接着剤の開発が非侵襲的な歯科治療具の脱着には必要不可欠だと考えた。
②目的
任意のタイミングで脱着可能な歯科用接着剤開発を目的に、紫外光の照射により接着強度が低下する接着剤を考案した。紫外光照射で接着強度を低下させるための成分として、環状糖類シクロデキストリンの空洞部に高分子鎖が貫通し、軸高分子末端がかさ高い化合物で封鎖された構造の超分子ポリロタキサンに着目した。ポリロタキサン中のシクロデキストリン部位は接着剤成分との架橋に利用することで従来と同等の接着強度を示す。一方、紫外光照射によって脱離する機能を封鎖基に賦与することで、紫外光によりポリロタキサンを分解させることが可能となる。これにより、架橋構造が崩壊するため接着強度の低下につながる。光分解性ポリロタキサンを用いる利点として、片方の封鎖基が脱離するだけで、多数の架橋構造が崩壊するため効率的に接着強度を低下できる点が挙げられる。本申請では、紫外光分解性ポリロタキサンを設計し、歯列矯正を想定したエナメル質における接着と、光照射による接着強度低下を評価することで、紫外光照射で脱着を容易とする歯科用接着剤の確立を目指す。
助39-16
CO2を化成品原料へ再資源化するための革新的な微生物電気合成システムの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
CO2は温暖化の原因として、排出削減や回収・貯留について技術開発が行われてきた。近年、逆にCO2の再資源化を図る挑戦的な研究開発が急速に進展している。
CO2を炭素源として利用できる微生物には光独立栄養と化学独立栄養に大別される。そのうち、化学独立栄養細菌とは、炭素源としてCO2、エネルギー源としてH2や酸化鉄(II)などの電子供与体を利用して生育する細菌である。特に、エネルギー源としてH2を電子供与体として生育する細菌を、水素酸化細菌という。一方、2010年、微生物電気合成 (Microbial ElectroSynthesis) の最初の論文が発表された。微生物電気合成とは、水の電気分解(アノード電極におけるH2Oの酸化によるO2発生、そして、カソード電極におけるH+の還元によるH2発生)と、カソード電極側での水素酸化細菌の培養を組み合わせたものである。これにより、炭素源としてCO2、エネルギー源として電気を用いることによって、水素酸化細菌に有機物(酢酸)を生産させることが実証された。(ここで、微生物電気合成に用いる電気は、太陽光をはじめ風力・水力・地熱など様々な自然エネルギーにより得られる電力を用いることができる。)
しかしながら、現状では、(1) 微生物電気合成で生産される物質は酢酸であり、それ自身の付加価値が極めて低い、そして、(2) 微生物電気合成における生産速度が極めて遅い、という質的・量的な問題がある。これらが解決されれば、微生物電気合成によるCO2の再資源化が実用に近づくのではと考えた。
②目的:課題設定とねらい
そこで、本研究では、化石資源由来CO2の再資源化を目指し、微生物電気合成によるCO2から化成品原料(エタノールとイソプロパノール)への連続・高速変換のための技術開発を行う。具体的な革新ポイントは以下の2点である。革新ポイント(1)水素酸化細菌の一種である絶対嫌気性のアセトジェンについて、微生物電気合成における最終代謝産物を、酢酸ではなくエタノールとイソプロパノールになるよう代謝工学的に改変を行う。革新ポイント(2)微生物細胞が付着しやすいような多孔質で正の表面電荷を有し、また、導電性を示す安価でスケールアップが容易な3D微生物カソード電極を作製する。
助39-17
大面積フィルム処理のための大気圧長尺マイクロ波プラズマにおける酸素ラジカル空間分布計測
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
近年の電子デバイス製造においては、フィルム上へのデバイス形成など新しい展開が始まっており、これらに伴い革新的なプロセス技術が要求されている。高価な真空容器が不要な大気圧プラズマ装置は次世代のフィルムプロセス装置として期待されるが、従来技術では処理速度や処理面積に限界があり、実用化に向けてプラズマ生成・応用技術のさらなる向上が求められている。このような中、申請者は独自に考案した電磁波伝送系によりメートル級幅を均一かつ高速に処理できる新たなマイクロ波大気圧プラズマ源を提案し、様々なガスにより高密度・長尺・均一なプラズマ生成に成功した。そして、本プラズマ源により、広幅のフィルムの高速表面親水化、高速アッシング(有機物分解)処理を実現する等、大きな成果を得ており、国内外の学会において高い評価を得ている。
上記のアッシング処理においては、先行研究と比較して非常に高速な処理結果が得られている。しかしながら、大気圧プラズマの計測の困難さから、本研究はこれまで、応用研究が先行していた。これまでの研究成果をさらに展開させるためには、プロセスにおいて重要となる化学活性種の密度及その空間分布の調査、及び、反応モデルの理解は不可欠である。
②目的:課題設定とねらい
本研究では長尺大気圧マイクロ波プラズマにおける原子状酸素(酸素ラジカル)密度とその長手方向の空間分布を光学的手法及び粒子計測を用いて調査することを目的としている。酸素ラジカルはアッシング等の酸化処理において重要な活性種である。
また、別の実験により、プラズマからフィルム基板に供給される熱量を評価し、アッシング進行の化学反応について検討する。さらには、マルチフィジクスシミュレーションを援用することにより、基板上でのラジカル拡散の分布と熱量を推定し、実験結果との比較を行うことで、大気圧下におけるプロセスの反応メカニズムを明らかにする。
助39-18
SrTiO3系新規光触媒電極の作製とプラズモニック増強による太陽光水分解性能の向上
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
自然エネルギーである太陽光を利用した水の分解による水素エネルギー製造技術は、1972年の本多・藤嶋効果の報告以来、枯渇や環境汚染の心配がない「夢のエネルギー源」として注目を集めてきた。この研究分野は、現在でも日本がイニシアチブを持っており、最近では実用化に向けた具体的な検討も始まっている。しかし、実用化に求められる最低限のエネルギー変換効率は約10%(太陽光エネルギー→水素エネルギーの変換効率、STH)と考えられているのに対して、これまでに報告されている実用的なシステムにおける最大のSTHは1%程(Hisatomi and Domen, Nature Catalysis, 2, 387-399, 2019)であり、大きなブレイクスルーが必要とされている。
STHの向上に最も効果的なのは、太陽光の大部分を占める可視光の利用効率を向上することであり、イオンドープによるバンドエンジニアリングや、新規化合物の開発、2種類の光触媒を用いたZスキームの利用などが広く検討されている。それらに加えて、2009年に命名されたプラズモニック光触媒を太陽光水分解に利用する検討も始められているが、こちらは未だ参入している研究者も少なく今後の大きな発展が期待されている。
②目的:課題設定とねらい
本研究では、紫外線照射時の光→水素のエネルギー変換効率をほぼ100%にできることで知られる助触媒担持AlドープSrTiO3をベースとして、還元処理やプラズモニック粒子の添加により、可視光応答性を付与する。さらに、試料合成条件や外部電界印加条件を最適化することにより、太陽光照射時のSTHを10%超に向上させる。同時に、プラズモニック光触媒電極におけるSTH向上に有効な因子の詳細を明らかにすることで、新しい学理の構築も目指す。
助39-19
太陽光発電パネル用の静電砂塵クリーニングシステムにおける摩擦現象が粒子除去性能に及ぼす影響
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
持続可能な開発目標 (SDGs) を達成するべく、クリーンな太陽光発電の重要性が高まっている。発電を効率的に行うために、日射量も多く、降雨の少ない砂漠に太陽光発電パネルを大量に設置して集中的に運用することが計画されているが、その地域特有の課題として砂嵐により舞い上がる砂が太陽光パネル表面に堆積し、しかも降雨がないのでその砂が除去されないという、泥臭くも看過できない喫緊の課題がある。砂漠のような過酷な環境下では、貴重な資源である水の利用を抑制し、ダスト清掃を実施する人やロボットへの負担を軽減するようなクリーニング技術が求められている。そのような課題に対し、静電気力のみを使用して非接触かつ自動で太陽光発電パネル上の砂をクリーニングする技術が開発されている。
②目的:課題設定とねらい
本研究の目的は、太陽光入射を妨げてその性能低下を招く砂を静電気力により自動除去するシステムについて、粒子・システム間の摩擦現象の影響を解明するものである。本システムは静電気力で粒子を浮かせるように除去する仕組みであり、これまでの研究では最適な静電場を形成するべく、システム側の電気的パラメータ (電圧、波形、電極配置など) に着目した研究が行われてきた。しかし、パネル上の電気力線はパネルを貫くように形成されており、静電場中で粒子は飛翔・パネルとの接触を繰り返しながら少しずつ除去されていくため、物体間の摩擦現象の影響を無視することはできない。また、自然環境下に存在する粒子は不均一な機械的性質をもっており、その差異がクリーニング性能に及ぼす影響についての詳細な検討は行われていない。そこで本研究では、粒子・パネル表面の機械的性質、特に摩擦特性が静電場中の粉体ダイナミクスやその除去性能に及ぼす影響についての体系的理論を構築することを目的とする。
助39-20
光ポンピング法によるプラズマ励起粒子時空間分布の3次元可視化
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
近年の先端プラズマ技術、特に半導体デバイスやナノテクノロジー分野において不可欠なプラズマ薄膜材料プロセスにおいて、プラズマ状態の基板面内均一性の高度制御や3次元形状を有する対象物へのプロセスなど、従来法では計測困難なプラズマ状態の複雑な時空間分布を適切に捉え、制御することが求められている。また、2000年代以降、大気圧程度の雰囲気内で小型プラズマを生成する、いわゆる「大気圧プラズマ」分野が急速に発展した。大気圧プラズマではプラズマ状態の時空間分布がマイクロ秒・マイクロメートルオーダー以下のスケールで変化し、プラズマ状態の時空間的挙動を精密かつ高速にモニタリングする技術の確立が求められている。このように、今後のプラズマ応用技術では、プラズマ状態を監視し続ける”プラズマモニタリング技術”の重要性が指摘されており、計測技術の革新に向けたアプローチが進められている。
②目的:課題設定とねらい
本研究は、申請者独自の着想による「プラズマ励起粒子の多次元可視化計測技術の実現」を目指すものである。プラズマ工学において、「励起粒子密度の時空間分布」は非常に重要なパラメータの一つであるが、
[1] プラズマ状態が計測機器や測定作業により変化することがない(非擾乱)
[2] 軸対称などの仮定をおかずに多次元(2D or 3D)空間分布を取得できる
[3] 測定対象粒子の絶対点密度の時間変化を外部環境に関わらずに連続計測できる
という要素をすべて満たす計測技術は申請者が知る限り存在しない。そこで、本研究では上記要素を満たすプラズマ中励起粒子の高度可視化技術の実現を目指し、【光ポンピングという従来プラズマ計測に活用されたことのない物理現象】を活用した計測技術に取り組む。
助39-21
次世代バイオマス構造体:100%セルロースナノファイバー成形体の機械要素用切削加工法に関する研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、次世代のバイオマス産業資材としてセルロースナノファイバー(CNF)の研究開発が進められている。CNFは、セルロース分子が集合したセルロースミクロフィブリルから構成されるファイバー状の構造体であり、鋼の5倍以上の高強度と1/5 の低比重を有したバイオマス材料である。この優れたCNFの特性を生かして、石油由来素材の代替としてCNFの産業利用が拡大しつつある。一方、CNFの新奇な利用法として、CNFのみで構成された100%CNF成形体(以下、CNF成形体)がある。CNF 成形体は、CNF分散液を加圧・脱水成形することで得られる高強度、軽量、高熱伝導率及び高加工性を有するバイオマス成形体である。CNF成形体は代表的な機械材料である鉄鋼・エンジニアリングプラスチックに匹敵する強度を有しているが、機械要素への応用が学術的に検討された事例はない。このことは一方で、CNF成形体の機械要素への応用が実現すれば、CNF成形体の構造材料への応用を加速させるブレイクスルーと成り得る。CNF成形体の構造材料への応用を考えた場合、機械要素で必要となる力学的強度のみならずその加工法の確立が必須となる。CNF成形体の加工法の確立のためには、CNF成形体-切削工具間における摩擦・摩耗現象すなわちトライボロジー現象を把握することが重要となる。切削加工時の材料間におけるトライボロジー現象は、材料の機械特性・化学的性質や潤滑油の化学組成に支配されており、摩擦場の真実接触部における摩擦界面層(表面近傍の数nm~数十nm)の分子状態や構造がマクロな切削特性に多大な影響を及ぼす。しかしながら、CNF成形体の種々の材料間におけるトライボロジー現象や潤滑油種の影響等については全くの未知である。
②目的
CNF成形体のトライボロジー特性に及ぼす種々の切削加工材料・潤滑油の影響を系統的に調査することで、CNF成形体の潤滑・加工メカニズムの解明を試みる。得られた知見に基づき、次世代のバイオマス構造体になり得るCNF成形体の高効率・高精度な加工法の提案を行う。
助39-22
電界による局所カイラル磁気構造誘起を利用した磁壁伝送に関する研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
磁石(強磁性体)細線中の磁区(スピン)方向を情報担体(“0”および”1”のビット)とし、その境界である「磁壁」を電流でシフトさせて動作する磁壁移動型のデバイスは、不揮発なスピン情報が電気信号(電荷)に変換されることなく回路中を伝送されるため情報のロバスト性が高い。この特性ゆえにSociety5.0社会を支えるストレージクラスメモリとして世界中で盛んに研究されている[Parkin et al., Science (2008)]。一方、磁壁デバイスにはまだ実用化に向けた課題が残されている。特に、一度入力されたビット情報の書き変えあるいは消去(フォーマット)を行う技術が確立されていないという問題がある。現状では磁場印加に頼らざるを得ず、消費電力を増大させる要因となっている。次世代コンピューティングのためにはこれらの動作を頻繁に行う必要があるため、上記の動作を高速かつ省エネルギーに実行するための基盤技術の開発が必須である。
②目的
磁壁デバイスのビット情報書き換え・フォーマット動作を高速かつ省エネルギーに行うための基盤技術の確立を研究のターゲットとする。そのためには全く新しい原理に基づく機能を生み出さなければならないと申請者は考えた。本研究では、「電界効果による局所的な磁性制御」と近年スピントロニクスにおいて注目されている「カイラル磁気構造」を組み合わせて問題解決を目指す。詳細な原理は研究計画の項で説明するが、スピンの旋回性が一意に決められたカイラル磁気構造を局所的に電界誘起することで、可変的な磁区の反転伝送ができることを示す。
助39-23
傍熱型ホローカソードを用いたプラズマウィンドウの実用化
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
プラズマウィンドウの実用化に向けた研究開発
プラズマウィンドウ(PW)は、プラズマを用いて大気圧(100kPa)と真空(~1 Pa)を遮る革新的プラズマ応用技術である。PWは内部で生成した超高密度プラズマが大気圧側から流入する中性ガスを加熱・超高温化し、高粘性効果によりガス流れを凍結することで大気圧と真空を隔てる働きを示す。PWが実用化できれば、ガラス窓を通過できない軟X線や荷電粒子を真空から大気側に取り出すことが可能になり、量子ビームの応用範囲が大幅に広がる。
PWを量子ビーム分野への応用を目指した研究は世界的に進められている。米国ブルックヘブン研究所ではPWを用いて大気圧下で電子ビーム溶接を行う実験が行われた。しかし超高密度プラズマを長時間維持することが困難であることからPWの実用化には至っていない。また、ミシガン州立大学で行われた研究では、PWに用いる針状陰極が長時間放電の熱負荷により激しく損傷することが報告されている。以上のように、PWの実用化には (i)超高密度プラズマの発生、(ii)熱負荷問題の解決、が求められる。
②目的:課題設定と狙い
ホローカソード電極によるPWの実用化
本研究では、上記の課題を解決するためにホローカソード(HC)と呼ばれる円筒陰極を世界で初めてPWに採用する。HCを用いることで陰極の表面積を増やし、熱負荷問題を解決できる。さらにHCの特徴である高密度プラズマ柱を生成することでガスを超高温化できる。本研究ではHCを用いてガス温度を1万℃まで向上させPWの性能を飛躍的に向上させることを目的とする。具体的には大気圧100 kPaと1 Paの圧力差を装置長さ30 cmで実現することを目標とする。この圧力比・勾配は今までに達成できている値よりも2桁高い数値であり、極めて挑戦的な研究である。
助39-24
Tailor-made color filter -色覚異常の多様性を考慮するデジタルカラーフィルタ
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
日本の先天色覚異常者の割合は男性で約5%と言われ、特定の範囲の色に対する応答や識別が困難である。色覚異常者の色知覚を補助する着色レンズは、レンズが光の通過帯域を変化させることで網膜の錐体応答量が変化し、識別しづらい色の組み合わせに輝度や色味の差が生じることを利用している。一方で、表示デバイス用の色覚補正方法としては、画像処理によって識別困難な色を修正する、テクスチャや点滅で示すなどの手法があるが、画像のイメージが損なわれる、色数が多い場合リアルタイムで処理できない等、問題点が多く一般的な実用には至っていない。
②目的
申請者は、これまでに表示デバイスに実装可能な「色覚デジタルカラーフィルタ」の有効性を検証してきた(業績参照)。デジタルカラーフィルタは、着色レンズの原理を表示デバイスに応用する試みであり、一部の色を変換する既存手法よりもシンプルな手法で簡便に実装できる。申請者はカラーフィルタによって、ある程度識別性が向上することを確認しているが、異常の型や強度によって効果が様々であり、型の多様性、異常強度の連続性といった個々で異なる特性を考慮したフィルタの設計が必要である。本研究では、個々の異常特性に合わせた最適なフィルタを構築するため、色覚異常の型と強度に基づく錐体感度関数から最適化手法によりフィルタの透過率を算出する手法を提案し、さらにフィルタの有効性を実験によって示すことを目的とする。
助39-25
冷却速度を変えるだけで超伝導体にも絶縁体にもなる物質―何が超伝導に必要なのか、実験からの機構解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景と独自性
エネルギーの高効率利用は、環境問題にも繋がる重要で喫緊の課題である。日本の電力利用の場合、年間で原発7基分の発電量にも上るエネルギーが電線などの電気抵抗によって失われ、熱として放出されている。もし電気抵抗がゼロの物質があれば、それを電線などに用いることで、このロスはゼロにできる。その「電気抵抗ゼロ」という特殊な物質群が超伝導体である。しかし超伝導体の数はごく限られており、しかも-260℃といった極低温や100万気圧といった非日常的環境でしか見つかったことがない。従って、より日常的な環境で超伝導体になる物質を探すことは、重要な研究課題である。一方、超伝導体の対極にある、電気を全く流さない物質を絶縁体という。本研究では、超伝導体と絶縁体とでは原子レベルで見てどこがどう違うのかを明確にする。そうすれば「より日常的な環境で超伝導体になる物質」を合理的に探せるようになる。その為に本申請者はある「物質A」に注目した。この物質は主に有機分子からなり、超伝導体(電気抵抗がゼロ)と絶縁体(電気抵抗が無限大)という、相反する二つの物質の中間に位置し、冷却の仕方によってどちらかになる。現在この物質を合成できるのは、世界中で本申請者のグループしかない。これまでの常識では、一つの物質はある決まった構造(原子配列)を持ち、それによって決まる一つの性質しか示さない。しかし物質Aでは、一つの物質で二通りの性質のどちらかが現れる。その理由は、固体(結晶)内でその分子末端(エチレン基)の構造に2通りのパターンがあるという、この物質特有の事情による。ねじれ型と重なり型である。現在、いくつかの方法で片方からもう片方のパターンへ(どちら向きにも)切り替えることに成功した。
②目的
以上を受けて本申請書の研究では、物質Aを超伝導体にするには 1.エチレン基の何%以上がねじれ型を取る必要、また 2.冷却速度を毎分何℃以下にする必要があるかを明らかにする
助39-26
錯体分子集積による極性配位高分子合成と機能開拓
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
チタン酸バリウムを代表とする極性構造物質は強誘電性、圧電性、焦電性を示す機能性材料である。極性構造中の「高度に揃った構造ひずみ」がダイポールを生み出し、電場や圧力に対する応答性に繋がっている。既に実用化もされている一方で、極性構造の設計は極めて難しく、化学的な物質開発において極性物質を設計・合成するためのブレークスルーが求められている。そこで、申請者は、構造ひずみが熱や電場といった本質的な物理刺激応答性に関わると考え、「構造ひずみの設計」を機能性材料開発の指針ととらえてシアノ架橋配位高分子を基盤に極性構造を目指して研究を進めてきた。シアノ架橋配位高分子は、金属イオン間をシアノ基により架橋された固体物質である。シアノ基はベンゼン環有する有機物と比較して短く強直であるため、シアノ架橋配位高分子は一般的な金属錯体物質群とセラミックスなどの無機物のちょうど中間に位置するとみなすことができ、磁気的特性や金属イオン間の電荷移動、負の熱膨張挙動など様々な物理的性質が見出されてきた。申請者は、対称性を落とした五配位型極性錯体ユニット [MN(CN)4]2-(M = Mn, Cr, Re)に着目し、様々な構築素子と組み合わせることで物質開発を行ってきた。四つのシアノ基がxy平面からズレた傘型であるため、分子ユニットとしてダイポールを持つ点やシアノ基の配位角度により分子ダイポールの変化を誘起できるといった特徴をもつ。中心金属イオン種の選択により、酸化還元活性な Mn、スピンをもつ Cr、発光する Re を作り分けることができる。本申請研究では、これらを最小のダイポールユニットと捉え、錯体ネットワーク中での配列制御を行うことで、高度に設計された構造ひずみを有する極性配位高分子の合成と機能開発を行う。
②目的
五配位型極性錯体分子ユニットの一次元、二次元、三次元配列により、一連の極性配位高分子の合成を行い機能開拓することで、構造ひずみに着目した極性材料開発設計指針を確立する。
助39-27
非太陽周回小天体ミッションにおける天体暦エラーの影響の定量化と軽減
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
Many small celestial bodies (i.e. comets, asteroids, and small planetary moons) preserve pristine relics of the early solar system. Small-body missions Hayabusa-1, -2, Rosetta, and Osiris-REx have returned notable samples and data. The confirmed MMX (JAXA) and HERA-Juventas (ESA) missions will explore Martian moons (i.e. Phobos and Deimos) and the binary asteroid Didymoon, respectively, which are secondary bodies orbiting a primary body. In such missions, not only the gravity of the primary body, but also the position of the secondary relative to the primary, the ephemeris, perturbs the orbiting operations as well as the science return.
One objective of a small-body mission is to uncover the interior structure of the target, or to achieve geodesy. A technique to identify physical parameters is to perform radiometric measurement while the spacecraft orbit closely around the target. Therefore, it is necessary to secure long-lasting orbiting near the target. However, maintaining the orbit in such highly complex dynamic environment is challenging. Accurate orbit information (i.e. position and velocity) is necessary. Inaccurate information of the orbit state will lead to misjudgment in orbit control (i.e., correction in velocity, Δv). Consequently, orbiting and mission failures (e.g., crashing or escaping) can happen.
A work by the applicant implies that the ephemeris errors affect the accuracy of orbit determination of the spacecraft and geodesy of the target. When the ephemeris error is not considered, the error of estimated physical parameters of the target can be as good as 0.5% and that of spacecraft orbit is 0.4 m. However, as the ephemeris error is present, the error increases to 35% and 30 km, respectively. Such a low orbit determination accuracy cannot permit safe proximity orbiting, let along exploration and understanding of the target. While the influence of ephemeris error is experienced, its impact on orbiting operation and geodesy is not yet understood, quantified, nor tackled. Pre-studies for MMX and HERA that neglect this disturbance may lead to inaccurate conclusions that misguide the operation planning and lead to mission failures.
②目的
The objective of this research is to reveal and mitigate the impact of ephemeris errors on the non-heliocentric small body mission.
助39-28
外場応答性金属錯体を用いた多機能性電子材料の創出
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
電荷移動錯体は、電子ドナー(D)∙アクセプター(A)分子間の電荷移動に伴い電子や磁気スピンが相乗的に機能するため、特異な電気伝導性や磁気特性を示す。π-πスタック等非共有結合により弱く集積したDA孤立分子系と比べ、DA分子が共有結合的に連結するDA型金属錯体は強固な電子的∙磁気的相互作用の発現や空孔の設計∙制御が期待できる。さらに、DA分子のフロンティアオービタルを精密に設計することで外場誘起電子移動を制御し、電子状態変化を利用した多重安定性の創出、および物質物性変換が可能である。DA型金属錯体は、これまでに金属イオン間での電子の非局在化や多段階酸化還元挙動、強磁性/フェリ磁性的なスピン配列による量子磁性/バルク磁性について研究が行われてきた。
②目的
本研究では、熱や光に応答してFeイオンとCoイオン間で電子移動を示すCoFe二核錯体を合成し、電子移動に起因した双極子モーメントが生み出す分極反転を制御し、新たなメカニズムを用いた強誘電金属錯体の構築を目指す。結晶内での分子配列および電子移動方向を制御するために、補助配位子や対イオンに光学部位(キラリティ)を導入し、電子移動型極性結晶の合理的合成法の確立および分極の方向制御を達成する。
助39-29
SEUを利用した高位置分解能型半導体検出器の実証試験とシミュレーション
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
半導体検出器は、放射線計測において、素粒子・原子核実験のみならず医療・非破壊検査などの分野でも広く用いられている。放射線計測の要諦は、エネルギーの測定と飛来方向の同定である。飛来方向の同定において、半導体は、その微細加工技術と電気制御技術を駆使して、放射線が通過した位置(ピクセル)を精度良く決定できる事から用いられている。デジタルカメラのように光子を検出するのとは違い、素粒子・原子核反応から生じる荷電粒子(電子など)は、半導体を貫通するので、半導体検出器を幾層にも重ねて、通過位置を3次元的に検出する。磁場中を運動する荷電粒子を3次元的に再構成すれば、その粒子の運動量が求められる。したがって、高位置分解能を持つ検出器の開発は、実験精度を左右するため、当該分野では重要な研究課題である。しかしながら、荷電粒子の飛跡を同定する半導体検出器は、しばしば大きな有効面積を必要とするため、高額であり、読み出しチャンネルの多さから、システム設計の技術的なハードルは極めて高い。
②目的
本研究は、汎用のSRAMメモリセルを応用して、従来の半導体検出器の100倍以上の位置決定精度を可能とし、且つ、安価な検出器開発を目指す。
近年の半導体加工技術は、電子記録媒体に見られるように、メモリセルのピッチ間隔が数ナノメートルのオーダーにも迫り、技術的な限界が指摘されている。理由は自然界に存在する自然界に存在する自然放射線が各メモリセルとの衝突によって、メモリに格納された情報を書き換えてしまうからである。この効果は広義には、Single Event Upset (SEU)として知られている。一般にSEUを起こさせないためには、十分に配慮した大きな電気容量を確保する必要があり、微小の領域に大容量の電荷を確保するために、ゲート電圧のアスペクト比と干渉効果、制御技術の難易度は困難を極める。我々は、むしろ、この事実を逆手にとり、積極的に自然放射線がメモリ情報を書き換える粒子放射線検出器を開発する。近年では3次元的に積層したメモリチップが商用として開発されており、研究者用の製作ベンダーでも多層構造の加工が可能となってきた。そこで、多層構造のメモリチップに着目し、3次元的に配置されたメモリセルの中を荷電粒子の通過とともに、飛跡に沿ってビットフリップ(SEU)を起こさせれば、従来型の検出器のように、単層の検出器を空間的に多重に重ねなくとも、本検出器一つで、粒子飛跡を再構成することができる。これは安価な検出器を実現するかもしれない。また、SEUを引き起こす確率は、メモリセルのサイズとセル内の電気容量の大きさによって決まる。最適な設計値は、セルサイズ、容量、多層構造のバランスによって求められる。簡易計算によると、従来型の検出器に比べて、最大100倍以上の位置分解能が得られることが分かった。本研究は、このアイデアに基づいた新規検出器開発を行うための原理実証試験をすることが目的であり、萌芽期の研究である。
助39-30
フォトクロミックエレクトロニクスを利用した新しいエステルフリー型分解性高分子材料の分解制御
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
SDG’sに示されるように、全世界的に持続可能な地球にやさしい素材開発が求められている。特に、海洋におけるマイクロプラスチック問題を解決するためには、従来の汎用樹脂に替わる新しい高分子材料の開発が必要となる。分解性高分子材料は、ポリエステル類であるポリ乳酸、ポリカプロラクタム、ポリブチレンサクシネートのほか、ポリトリメチレンカーボネート(PTMC)など、限られた高分子骨格しか用いられておらず、材料使用の際に必要となる力学的特性や熱的特性を満足に満たすためには、新たな分解性高分子材料の開発が求められている。これらの中でも、PTMCは加水分解により二酸化炭素とジオール化合物に分解され、一般的なポリエステル化合物が酸性有機化合物を生成することと比較すると、分解しても中性を保つことが特徴といえる。高分子素材の原料となる新規モノマーとして、このPTMCの側鎖に様々な機能性置換基を導入した様々なトリメチレンカーボネート(TMC)誘導体が報告されている。
②目的
本研究では、新しい機能生分解性高分子材料を創りだすことを目指して、新規TMC誘導体を合成する。ここでは、光エネルギーを吸収する化合物を材料に混ぜ込んでおくことで、屋外の強い紫外線に暴露されると、分解が促進されるという、新しいエステルフリー型PTMC誘導体を合成することを目的に設定した。
助39-31
医薬品製造用3Dプリンターに関する萌芽研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
3Dプリンターは、産業分野においてものづくりをする工作機械・加工技術として広く知られており、機械・航空分野の他、建築・食品・教育、そして医療分野までその裾野を広げてきている。申請者の出身分野である薬学分野(製薬業界)では、2015年にBinder jet方式3Dプリンターで製造された錠剤(Spritam、精神薬)が米国で認可されており、新しい製造様式を活用した革新的な医薬品の誕生が期待されている。
申請者は、日本の研究グループでは初めて3Dプリンター錠剤に関する論文を報告し、「3Dプリンターに関する医薬品のものづくり研究」を推進してきた。3Dプリンターは、従来の製造法ではできない形状・内部構造の医薬品・錠剤を作製できることから、患者一人一人に対する「オーダーメイド医薬品」に適していると考えられており、小型で卓上で設置するのに適した材料押し出し方式3Dプリンターを用いて病院で医薬品を製造することが議論されている。
②目的
医薬品製造に特化した材料押し出し方式の3Dプリンターが論文報告されているものの、まだ成功・普及していないのが現状である。その原因として 1.本方式の3Dプリンターの生産性の低さと 2.多様で複雑な医薬品材料の物性が実用化を妨げていることが挙げられる。1.は、例えば、少なくとも患者に1週間分の医薬品を翌日に手渡すことが必要となり、2.は、錠剤(固形)や坐薬・ゼリー剤(半固形)、フィルム剤(ゲルを乾燥して作製)まで取り扱う必要がある。これらの課題点を解決するため、申請者は、生産能力を改善する材料押し出し方式3Dプリンターの特殊な部品の製作と、最適なプリンター条件とインク組成を予測する機械学習モデルを構築することを本研究の目的とする。
助39-32
内包フラーレンの精密秩序集積による超原子物質科学の開拓
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
地球規模での環境・エネルギー問題を解決し、存続可能な人間社会を実現する戦略目標として、新規機能物質を応用した省エネルギー化や再生可能エネルギーの創出・利用に関するナノテクノロジー研究に焦点が当てられている。中でも数~100個程度の原子で構成され、高い幾何対称性をもつ有機半導体分子やナノクラスターは構成要素そのものが一つの原子のように振る舞う「超原子」としての電子的性質 (電子軌道) を有しており、新しい概念の高効率ナノデバイスの実現に向けた研究が展開されている。超原子に由来する電子軌道は、原子間に局在する通常の電子軌道と異なり超原子骨格の外側数ナノメートルにまで及んでいる。そのため、超原子がナノスケールの周期で秩序集積体を形成すると、極めて有効質量の小さい自由電子バンド (超原子電子バンド) が形成され、常識を超えた電荷移動度を有する超原子新素材の創成が期待できる。しかし現在のところ、超原子物質群を固体表面上に秩序集積させることの困難さから、超原子電子バンドの概念を積極的に取り入れた物質機能創成や制御は行われていない。
②目的
本研究では超原子的な性質が最も顕著に表れる機能物質として、原子や分子を内包した構造を持つかご状炭素分子である内包フラーレンを対象に、その秩序集積化を2次元層状化合物基板を用いることで達成し、超原子電子バンドの形成とそれに関与する励起状態の超高速ダイナミクスを精密に観測する。この研究の推進により、超原子秩序集積体としての高い機能を見出すとともに、機能の起源を電子状態観測の視点から明らかにすることで、これを制御する新しいナノテクノロジーを開拓する。
助39-33
ナノスケール分子磁石の縮重電子軌道を利用した新しいマルチフェロイクスの開拓
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
複数の強的な性質を持つマルチフェロイクスは多値演算メモリ材料への応用の観点から興味が持たれ、遷移金属化合物磁性体において強磁性強誘電マルチフェロイクスが報告されている。遷移金属マルチフェロイクスの研究は日本が先導し、アメリカやヨーロッパでも行われているが、物性を制御するためのボトムアップ合成法は確立していない。
②目的:課題設定とねらい
有機ラジカル磁性体のボトムアップ合成により、戦略的に強誘電強磁性マルチフェロイクスの創成を目指す。従来の磁気誘電現象はスピン-軌道相互作用を起源とするが、本研究では、縮重電子軌道に由来する新しい量子化機構によって発現する強誘電強磁性マルチフェロイクスを開拓する。具体的には、三角形の頂点にS=1/2スピンを配置し、辺に相当する反強磁性相互作用で結ぶことにより、4重縮重した電子軌道を基底状態として実現する。縮重電子軌道を持つ分子内には電気分極が生じ、これを結晶中で緩く連結することによって、巨視的な強誘電秩序を生じさせる。磁場や電場によって磁気秩序と誘電秩序を制御し、新しい強磁性強誘電マルチフェロイクスの創成を目指す。
助39-34
昆虫の眼を超える偏光と位相を検出する2Dセンサー
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
●昆虫の眼は偏光を検出することができる。
●偏光を感じとる眼をもつ生き物は意外に多いが、人間は偏光感受能力がほとんど残っていない。
●2020年、微細周期構造を用いた偏光カメラが市販され、昆虫と同等の眼を手に入れた。
●しかしながら、円偏光の感度がないといった技術的課題も生じている。
●昆虫の眼も光の波面(位相)の検出はできない。
●波面の検出には干渉計やシャックハルトマンセンサーなどが提案されているが、偏光は同時に検出することができない。
●偏光と波面を画像化する2Dセンサーは、虫の目の構造と偏光カメラ
» 緑内障による網膜の神経線維減少に伴う複屈折変化
» 網膜上の白斑による偏光解消
» 手術前後および術中の波面検出に有効であるが、これらを一括で行える診断治療支援装置はこれまでに提案されていない。
●申請者らは、独自技術からなる
» 波長依存性のない軸対称波長板
» シングルショット分光偏光決定技術
の開発に成功した。
②目的
色と偏光、波面を同時に計測できる昆虫の眼を超える2Dセンサーの開発を目的とし、眼科学に応用できるセンシング技術に発展させる。
色と偏光、波面を分離してイメージング
目標値:空間分解能 30 μm,300 × 300 画素、RGBのカラー画像を30 frame/秒
助39-35
光圧増幅ナノ構造体を用いたナノ物質マニピュレーション法の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
分子やナノ粒子を捕まえ自在に操る次世代型の新奇光ピンセット法の実現を目指す。提案する操作法は、分子に結合させたマイクロ粒子を光ピンセットにより捕まえて、分子を間接的に操作する従来法ではない。本手法は、プラズモンナノ構造や申請者らが発見した半導体ナノ構造による光圧増幅効果を光ファイバ先端で利用し、分子やナノ粒子に光圧を直接作用させ操作する手法である。本手法を実現し、光ピンセットによる化学反応操作や分子に作用する力のin situ分析など、夢に掲げた光圧化学の実現に近づくであろう。
①背景
力学的運動で誘起される化学現象(相転移・化学反応など)が近年注目を集めている。例えば、凝集誘起発光に代表される分子集合による光機能の発現や、力学刺激による自己修復ゲル、最近ではボールミルを用いた酸化還元反応などが挙げられる。このような現象の理解に向けて、ナノ粒子・分子レベルで力を直接的に分子・ナノ粒子に作用させ現象を追跡する分析手法は皆無であった。これに対し、申請者が見出したプラズモンナノ構造体やシリコンナノ構造体などを利用すれば、分子やナノ粒子を捕まえ、操るだけでなく、力学応答型の分子やナノ粒子ひと粒に光圧を直接的に作用させ相転移や化学現象を誘起し、その現象を分光追跡できるのではないか、と着想を得た。
②目的:課題設定とねらい
光圧増強ナノ構造体を付与した光ファイバを作製し、ナノチップ増強光ピンセットを開発する。シリコンナノ構造体による光圧増幅効果は、申請者らが発見した新しい光ピンセット法である。しかしながら、ナノ構造を施した基板上でなければナノ粒子を捕まえることができないため、実験の制約が高い。一方、光ファイバ先端上にナノ構造を作製すれば、溶液中や気相中での光捕捉だけにとどまらず、固液界面や液液界面、気液界面などあらゆる環境下での分子・ナノ粒子の光捕捉が可能となり汎用性が飛躍的に向上する。
助39-36
カイラリティーを特定した2つの単層カーボンナノチューブ間の熱伝導の解明
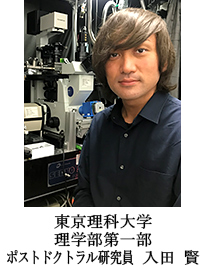 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ナノ材料として単層カーボンナノチューブ(SWNT)は、化学的に安定で真空では2000℃で加熱してもその構造は壊れないことから将来の配線材料として精力的に研究されてきた。沢山のSWNTを網状にしたSWNT薄膜は、高い性能と共に柔軟性があることからウェアラブルな熱電材料として世界中で盛んに研究が行われている。しかし、現実のSWNT材料による熱伝導はSWNT自体の熱伝導だけでなくその接点の熱伝導特性に影響され、理想的な値には程遠いのが現状である。ナノスケールでの熱制御を行うためには、まず、構造が明らかなSWNT間の熱伝導特性を精確に理解することが不可欠である。これまでは、ナノスケールの物質であるSWNT接点での熱伝導特性の実験的な計測は極めて困難であり、信頼できる報告は皆無であった。
②目的
本研究では、SWNT薄膜の熱電変換効率の制御に不可欠なSWNT間におけるナノスケール熱伝導機構の解明を目指し、カイラリティーを特定した2つのSWNT間における熱伝導特性を光学イメージング法を駆使した温度分布測定により非接触計測する技術を開発する。
助39-37
表面プラズモン共鳴型光ファイバーセンサーによる地熱スケールの計測
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
日本は地熱資源量が世界3位の地熱大国です。地熱発電は純国産の再生可能エネルギーを安定に利用できるため、持続可能社会の新エネルギーとして、特に3.11の震災以降、期待されています。一方、地熱発電設備内にて地熱水から大量に析出・生成するスケール(水垢)は、設備の故障や熱交換効率の低下を引き起こすことから、地熱普及にとって最大の障害の一つとなっています。スケールの抑制のため、薬剤の開発や電磁波照射など様々な検討が進められていますが、迅速にスケール生成を評価する方法が確立されていないことが研究の発展を遅らせています。
申請者は、光ファイバーを利用した「スケールセンサー」を開発しました。光ファイバーの石英コアをむき出しにし、表面でのスケール生成に伴う屈折率変化を伝搬光強度から計測することが可能です。これにより、これまで数週間~数か月を必要とした試験を、センサーによって1日程度で達成できました。これまでの成果から、生成するスケールへのセンサー感度は、試験時間へ直接関係し、感度をこれまで以上に高めることで、より短時間でスケール生成の潜在力を評価できることがわかりました。
屈折率を検出する手法として、前述の全反射減衰法の他、表面プラズモン共鳴(SPR)と呼ばれるものがあります。これは金や銀などの金属の光共鳴によって生じる光の減衰に基づいており、その高い感度によってバイオセンサーの分野などで実用化レベルまで用いられています。これを光ファイバーに落とし込んだSPR光ファイバーセンサーは研究レベルではありますが、感度だけではなく取り回しの良さや遠隔利用性により着目されています。特に、先端の金が光を反射させることで試料に直接挿入できる使用性の高さがあります。
②目的
本研究では、SPRによって既存のスケールセンサーを高感度化した、SPR型光ファイバーセンサーを地熱や温泉水スケール計測へ展開し、その性能を明らかにすることを目的としました。より高感度で、すなわち短時間でスケールを検出でき、スケール抑制評価法として地熱利用への大きな貢献となります。
助39-38
光エネルギーによる新たな無痛性不整脈治療の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
◆心房細動は最も頻度の多い不整脈であり、脳卒中、心不全および死亡のリスクとなる。加齢は心房細動の重要な発症リスクであり、高齢化が進む日本において心房細動の患者数は急速に増加している。心房細動治療において薬物療法やカテーテル心筋焼灼術の進歩がみられるが、有効性や安全性には未だ不足な点がある。最も確実な心房細動の停止法は電気的除細動であるが、無鎮静では患者に苦痛を与える。このため、無痛性除細動治療の開発は生命予後やQOLの観点から重要な研究課題である。
◆光遺伝学は、ベクターによる遺伝子導入やトランスジェニック動物を用いて目的細胞に光駆動型チャネルであるチャネルロドプシン(ChR)を発現させ、光を当てることでイオンの流入・流出による細胞膜電位の変化を起こし、目的細胞の生理現象を制御する新しい技術である。特異的なプロモータを用いることで細胞選択的に生理現象を修飾することが可能であり、心房筋に特異的にチャネルロドプシンを発現させることで、骨格筋には影響を与えずに心房筋の電気生理特性を変化させ、無痛的に心房細動停止を成し遂げられる可能性がある。
◆近年、光遺伝学を用いた不整脈停止効果を検証する基礎実験が行われており、申請者もin-situでのリエントリー不整脈停止を報告した(Watanabe M. Cardiovasc Res 2017)。しかしながら、背景にある電気生理的機序についてはこれまで殆ど検討されてない。Vivoでの電気生理現象の解析には、空間・時間分解能で優れる光学マッピングが広く使われるが、光遺伝学を用いた実験では光の干渉により、光学マッピングでの解析は不可能だった。申請者らは、10msの短い光照射でもマウスの心臓では心房細動を停止し得ることを確認し、更に、この条件では光学マッピングによる活動電位波形の変化を詳細に観察し得ることを初めて確認した。
②目的
本研究の目的は、「ChR発現マウスの心房において、光刺激が活動電位波形に与える変化を解析し、光除細動に必要な電気生理的条件を解明すること」である。
助39-39
培養皿の中で運動を再現する - 培養骨格筋への電気刺激システムの開発を通じた運動応答遺伝子の解析
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
サルコペニアとは加齢による骨格筋の萎縮のことであるが、実際には30歳前後から骨格筋量は減少し始め、70歳になるとピーク時の70%程度まで低下すると言われている。この骨格筋量の減少に対して、運動が効果的であることは感覚的、経験的には理解できるものの、どのようなメカニズムが骨格筋維持に働いているのかは未だ完全には分かっていない。
これまでに運動によって活性化されるシグナル伝達経路がいくつか同定されているが、運動時に骨格筋細胞内で起こる変化についてはまだまだ未解明な点が多く、効率的に解析を行っていく必要がある。一般的に運動を解析する方法として、マウスを用いた動物実験が行われている。しかし、動物実験に頼る方法では、実施に長期間を要し、労力、費用の面から効率が悪い。さらにはマウスとヒトの種の違いが存在しているため、マウスで得られた知見が必ずしもヒトでは当てはまらないという懸念もある。一方、動物実験を代替する実験系として、培養皿上に形成させた培養筋肉に電気刺激を加え、強制的に収縮させる電気刺激装置が市販されている。しかし、培養骨格筋に電気刺激を加えた際の遺伝子発現などの応答が、生体の筋肉の運動への応答と一致しないことがあり、完全に運動を代替できる実験系とは言い難いという問題点がある。
②目的:課題設定とねらい
「背景」で述べた問題点を解決するために、我々は独自に培養筋肉への電気刺激装置を設計し、作製した。本研究では、培養筋肉への電気刺激実験系の改良を通じて、(1) 生体の運動に限りなく近い実験系を培養皿上で実現すること、(2) 電気刺激装置を代謝解析装置などの外部測定装置と連携させることで個体を用いた実験では困難なきめ細かな解析を可能とすること、(3)運動に応答し活性化する遺伝子の同定と機能解析を行い、将来の筋萎縮予防に向けた礎とすることを目的とする。
③学術的な独自性と意義
我々はすでに運動に応答して活性化し、筋萎縮に拮抗的に働く新規遺伝子を発見しているが、本研究による解析の効率化によって、新規で、かつ重要な機能を持つ運動応答遺伝子を同定することが可能となる。
助39-40
末梢伝搬メカニズムの解明に基づく軟骨伝導デバイス群の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
骨伝導音は外耳・中耳の障害に起因する伝音性難聴の補聴手段として用いられてきた。しかしながら、乳様突起に振動子を押しつけて呈示する従来の骨伝導には、痛みが生じる、振動子がずれやすいという欠点があった。また、デザイン的にも改良の余地が大きかった。対して、申請者や奈良県立医大らの共同研究グループは、このような骨伝導が持つ問題を解決する手段として“軟骨伝導”を提案し (阪口ら 2008)、補聴器(Nishimura et al. 2013) やスマートホン (Nakagawa et al., 2013,) への応用を図ってきた。軟骨伝導は骨伝導の一種であるが、耳介等の外耳を構成する軟骨部に振動子を呈示する。軟骨部は骨部に比べて軟らかく、弾性を持つために痛みを生じにくい。また、使い方を工夫することで騒音下でも聞きやすい、耳栓やイヤホンを装着した状態でも利用できるというメリットがある。このように、軟骨伝導は、装用感や美容上の問題という骨伝導の欠点を解決することで、その応用範囲を情報端末やオーディオ機器へも広げる技術であり、その意義は大きい。
②目的:課題設定とねらい
しかしながら、軟骨伝導機器のさらなる普及を考えた場合には、以下に示すような課題が残されている。
課題1: 知覚メカニズムの解明による理論的基盤の構築
骨伝導の知覚特性についての報告は以前から存在するが、そのほぼ全てが側頭骨の乳様突起への刺激呈示によるものであり、それ以外への刺激呈示は、ごくわずかに申請者らの報告(Nakagawa et al. 2013:耳珠、Nishimura et al. 2015:耳甲介)があるのみである。呈示部位や振動子と皮膚組織とのカップリングによって各経路を伝搬する骨伝導音の様相は変化すると思われるが、乳様突起や耳珠以外に呈示した場合の末梢伝搬の詳細は不明のままとなっている。
課題2: 伝音性難聴の補聴効果の増大
現在の軟骨伝導では、伝音性難聴に対する十分な補聴効果は得られない。現在の方法では、外耳道を伝搬する気導音に加えて、一端は生体内に入るものの外耳道内に気導放射される“外耳道内放射成分”が顕著に発生する。その適用は、鼓膜が健全であるものの外耳孔が塞がった外耳道閉鎖症(発症率:1万人に1人)におよそ限定されたものとなっている。軟骨伝導方式の補聴器やスマートホンをより一般的な伝音性難聴に適用するには、中耳や内耳に直接到達する成分(慣性骨導成分や圧縮骨導成分)を増加させる刺激呈示方法が必須となる。
課題3: 製品開発に必要な基盤情報・基盤技術の確立
軟骨伝導には出力校正法を始めとする工業規格が一切存在せず、開発効率が向上しない要因となっている。
本提案では、軟骨伝導の末梢伝搬過程の詳細を明らかにすることで、十分な伝音性難聴の補聴効果を持つ軟骨伝導補聴器/スマートホンやさらなる派生機器の開発に有用な知見の獲得を目指す。また、軟骨伝導の出力校正機器の開発を試みる。
助39-41
てんかん入院診療における医療者を支援するためのてんかん発作予測・アラームシステムの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
てんかんは、突然のけいれんや意識障害をきたす発作を繰り返す神経疾患で、国内には約30万人の薬剤抵抗性患者が存在する。脳内のてんかん焦点部位を特定するためには、数日間ビデオ撮影下で持続的に脳波を記録して発作時の所見をとらえる長時間ビデオ脳波検査や、待機室で発作の発来を待ち、発作開始直後にアイソトープを投与して発作時の脳血流を評価する発作時SPECT検査が行われる。予測不能の発作に合わせて診察や検査を行うことは医師に大きな負担を強いる。また、検査入院中は発作時の受傷を防ぐために看護師が患者を常時保護観察する必要があり、トイレ等の棟内歩行にも付き添いを要する。すなわち、発作の予測不能性のために、てんかんの入院診療では、医師、看護師において、高い人的コストと心身の負担が発生している。
申請者らは、てんかん発作前の心拍変動の変化を、機械学習による異常検知手法によって検出することでてんかん発作を予測するアルゴリズムを開発してきた。また本アルゴリズムをスマートフォンアプリ化して独自開発のウェアラブル心拍計と組み合わせ、リアルタイム発作予測システムのプロトタイプを構築した。本技術の応用により、入院中のてんかん患者の心拍をモニタリングして、発作の発生を医師や看護師に事前に知らせるシステムの実現が期待される。
②目的
てんかんの入院診療に携わる医師、看護師をサポートする人間支援システムとして、ウェアラブルてんかん発作予測・アラームシステムを開発する。心拍変動に基づく発作予測AIアプリ、ウェアラブル心拍計測技術などの申請者らによる基盤技術を統合して医療者支援に最適化したシステムを構築し、実用化を目指す。
助39-42
脳への微弱な電気刺激がリハビリテーションを促進する分子細胞機序の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
脳梗塞に代表される脳血管障害は、我が国の主要な死因の一つであり、高齢化や生活習慣によってリスクが高まるため、超高齢化社会の昨今、さらに深刻化することが予想される。さらに、一命を取り留めたとしても脳機能に重篤な障害が残るなど二次的な影響が問題となり、長期にわたるリハビリテーションや介護などの必要性から、生産性の低下や経済的な損失も無視できないため、早急な解決が急務である。したがって、発生を予防するのはもとより、リハビリのパフォーマンスを向上し、回復を促進する治療法の開発が喫緊の課題である。
経頭蓋直流電気刺激法(tDCS)は、脳梗塞を含む疾患からのリハビリテーションを促進する補助法として注目されており、基礎研究および臨床研究の両方において研究がなされている(Zhangら2020)。tDCSは慢性脳卒中に対して積極的な治療効果があり、失語症や運動機能の改善効果が報告されている(Bakerら2010、O’Sheaら2014)。さらに最近では、急性脳卒中に対して、tDCSが積極的な治療効果があることも報告されている(Bornheimら2020)。ところが、tDCSの作用機序は完全には解明されておらず、安全性も不明確なため未だ医療行為としては認可されていない。
tDCS法において陽極電極は大脳皮質に対して促進作用があり、陰極電極は抑制作用があることや(Schlaugら2008)、シナプス伝達効率の向上(シナプス可塑性)を引き起こすことが断片的に報告されている(Reisら2009など)。しかしながら、その詳細な脳の分子・細胞メカニズムは不明である。
一方、脳の健康を守り保つ仕組みには、血流のみならず脳脊髄液と細胞間質液の交換(脳リンパ流)が重要な役割を果たしていることが報告されており、脳梗塞によって脳リンパ流が滞留してしまうことが報告されている(Mestreら2020)。一方、申請者らは、マウスを用いた研究から、脳梗塞後、脳リンパ流を改善することで、余剰の老廃物を排出し回復を促進する薬理学的な手法を提案してきた(毛内ら2019)。
②目的:課題設定とねらい
申請者らは、これまでマウスを用いた研究から、tDCSがシナプス可塑性を誘導するメカニズムに、脳細胞の一種であるグリア細胞のアストロサイトが重要な役割を果たす可能性を提案してきた(毛内ら2016)。アストロサイトは、脳リンパ流を制御している重要な細胞であるため、アストロサイトの制御によって、脳リンパ流を改善できる可能性がある。本研究では、tDCSによってアストロサイト機能に介入し、脳リンパ流の改善効果を検証する。さらにそれによって老廃物を排出し、シナプス可塑性を誘導することによってリハビリのパフォーマンスが向上できるかどうかを詳細に検証する。
助39-43
神経情報の操作計測のためのフレキシブルマイクロLEDシートの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
薬によって疾患を治療するという従来の手法に加えて、小型デバイスを生体に埋め込み電気的に治療するという新たな治療手段(ペースメーカーや脳深部刺激装置や人工内耳等)が注目を集めている。2014年にアメリカにおいて「Electroceuticals」という医学・生物学・工学を融合した研究領域が立ち上がり、神経ネットワーク理解に基づく疾患の理解やそれに基づく治療手法の開発が進められている。電気的な治療法は効果的であるが周囲の神経細胞にも影響を与えることから、生理機構理解における直接的なエビデンスが得られず、治療法への応用では副作用が課題となる。一方で、光スイッチによって選択的に神経活動を遠隔操作できるオプトジェネティクス技術は、特定の神経活動と行動発現を直接的に結び付けることが可能であり、選択的な操作のため副作用が出にくく、神経ネットワークの解明や革新的診断・治療・予防法の創出が期待できる。しかし、これまでに一般に行われてきた光ファイバや顕微鏡による生体光操作では、生体侵襲性や限定的な光刺激範囲、対象の拘束などが課題であり、特に治療法への応用に向けては小型デバイスの実現がカギになる。小型の光操作デバイスとしてLEDが注目されているが、脳や臓器に密着して広範囲を自在に光操作できる技術は見出されておらず、LEDによる効果的な光操作の時空間的な制御法についてもわかっていない。
②目的
本研究では、1)任意領域の神経情報を光操作するためのフレキシブルマイクロLEDシートの開発、2)効果的なLED光刺激法の確立、3)フィードバックのための神経情報計測技術との集積化に取り組み、小型生体光操作デバイスの基盤技術の構築を目的とする。
助39-44
神経サーキット特異的光操作による精神疾患への新たなアプローチ
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
光刺激を用いて神経細胞の活動を操作する光遺伝学(オプトジェネティクス)は、時間分解能の高さという工学的利点と、特定の細胞のみを制御しうる遺伝学的利点を併せ持ち、脳内の神経ネットワークレベルの活動を制御しうる現時点で唯一の技術である。この技術を用いて精神疾患の新しい治療の可能性を探る試みが国外では既に始まっており、例えば腹側海馬を起点とする神経ネットワークの活動を光制御することにより不安障害的な行動を制御しうることが報告されている(Padilla-Coreano et al., 2019. Neuron)。統合失調症や注意欠陥障害(ADHD)の分野においては、未だにこの試みは取り組まれていないが、それらの症状も神経ネットワークの異常が関与しているため有効なアプローチだと考えられる。
②目的
本研究計画では、オプトジェネティクスを用いることによって、特定の神経回路のみを狙って操作することにより精神疾患の行動異常(社会行動の低下など)が再現できるかどうか試み、神経ネットワーク活動異常と精神疾患との間に存在している因果関係を明らかにする。さらに健常脳で記録されるネットワーク活動を模した刺激によって精神疾患様の行動異常を軽減することができないか検討し、新たな治療法の可能性を探る。
助39-45
収束超音波のニューロモデュレーション効果の作用機序の解明とこれを用いた神経ネットワーク活動の制御
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、低強度の収束超音波(focused ultrasound: FUS)が非侵襲的に神経機能を亢進あるいは抑制する効果(ニューロモデュレーション効果)を示すことが報告された。FUSで経頭蓋的に特定の脳領域を刺激すると、運動機能や知覚機能に影響を及ぼす他に、細胞間隙に存在するGABAやドパミンの濃度を可塑的に調整する作用が観察されている。しかし、FUS刺激による機械的・熱的作用がどのような分子機序により神経機能に作用しているのかは不明である。
FUSのニューロモデュレーシ作用に関する研究は国際的にも始まったばかりである。現時点では主に動物モデルでの基礎研究が動き始めた段階で、ヒトを対象とした研究は海外の2施設のみである。先ずはFUSの神経機能への作用機序を解明することが求められている。
②目的
本研究では、1. FUSによるニューロモデュレーション効果の作用機序をシナプス伝達のレベルで解明するとともに、2. 初代培養した海馬神経のネットワーク活動を、FUSを用いて可塑的に制御する刺激法を開発することを目的とする。さらに、熱性痙攣・てんかんモデルマウスを用いて、FUSのニューロモデュレーション作用によりシナプス伝達機能を制御し、神経ネットワーク活動を抑制する手法を開発する。この技術をてんかんに対する新たな非侵襲的治療法として応用することを目指す。
助39-46
原因不明の心筋症におけるラマン分光顕微鏡による自動診断法の確立
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
わが国の死因の1位が悪性腫瘍であることは国民にもよく知られた事実であるが、75歳以上人口では、現在脳卒中を含む循環器病が死因の第1位である。心不全とは、心筋自体に異常が生じているために心室の収縮性あるいは拡張性が障害(これを心筋症という)されて、その結果心不全をきたす。心筋症は、肥大型心筋症、拡張型心筋症、不整脈源性右室心筋症、左室緻密化障害などが主に分類される。肥大型心筋症と言うと同一の疾患と考えられるが、その中にはファブリー病やアミロイドーシスの蓄積病、サルコイドーシスやミトコンドリア病などが含まれている。このように詳細な診断がつけば、治療法が確立されている疾患があるため、適切な治療が可能となる。しかし、確定診断をするためには現在では心筋生検の結果を待たないと確定診断が不可能である。よって、心筋症の詳細な早急な、診断技術の開発が必要である。
現在は、組織を観察する電子顕微鏡が開発され、組織形態をより微細に観察することが可能となった。また抗原抗体反応を用いた免疫組織化学技術の進歩により、組織の識別は単に形態のみでなく、分子レベルでも行えるようになった。これらの技術革新が医学・医療にもたらした恩恵は計り知れないものがあることはいうまでもないが、光学顕微鏡・電子顕微鏡の観察はあくまで基本的には形態観察の技術であり形態学的に識別不能な物質の場合、また免疫組織化学は既知物質に対しては有効であるが未知物質や想定外の物質の場合、それらを観察・同定するには限界があった。
ラマン散乱光を顕微鏡に追加したラマン分光イメージング顕微鏡を活用することで、細胞や生体組織を無標識に生きたまま1細胞レベルで観察することができ、かつ(色素分子で標識できな いような小分子も含めて)試料内分子を網羅的に分析することが可能となる。近年になりラマン分光イメージングを病態解析、診断、再生医療、薬剤活性の評価等への応用が期待される。
②目的
本研究では、心筋症の病理検体を、ラマン分光イメージングに活用することで、網羅的なタンパク質および代謝解析を詳細に検討することで、非染色的に心筋症の診断をおこなう新規診断法を確立する。さらに、心筋症診断で必須と考えられた生検もなく非侵襲的に心筋組織を診断することが、究極的な目的である。
助39-47
行動・ドーパミン・神経活動の同時計測による注意欠陥多動性障害の予測アルゴリズムの創出
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
注意欠陥多動性障害(ADHD)とは不注意、多動、衝動性の行動がある神経発達性精神障害であり、小児の5〜8%が罹患する。現在のADHD診断には、問診や知的水準を計測する心理検査が中心である。そのため、子供の時に診察機会に巡り合えず、成人後にADHDと診断されるケースも増加しており、ADHDを簡易計測にて早期診断できる機器の開発は重要である。過去の研究により、ADHD患者を対象として、ポジトロン放出断層撮影法(PET)で計測した結果、ADHD患者のドーパミン放射活性の低下していることがわかっている(Forssberg et al., 2006)。また、ADHD患者は前頭前皮質や尾状核などの脳容積が減少していることがわかっている(Valera et al., 2007)。しかし、計測機器の分解能や環境の制限などにより、1.前頭前皮質のドーパミン濃度が変化することにより、ADHD症状の行動と神経活動がどのように変化するのか?さらに 2.精神刺激薬によりドーパミン濃度を上昇させることで、なぜ症状が改善するのかについては、未だに不明なままである。
②目的:課題設定とねらい
本研究の目的は、ADHDモデル動物を対象に、前頭前皮質の神経動態を解明し、ADHD簡易診断用の予測アルゴリズムを創出することである。申請者のこれまでの研究で、マウスの側坐核に対し、ドーパミンの蛍光バイオセンサ(生体分子と結合して蛍光するセンサ)であるd-Light (Sun et al., 2018)を発現させ、行動とドーパミン濃度の同時計測に成功している(これまでの研究の実施状況参照)。この方法を発展させ、ADHDモデル動物の前頭前皮質のドーパミン・神経活動を計測し、行動との連関を解明する。本研究の成果から、ADHDの症状である多動・衝動性の行動が表出している際の神経活動が明らかになり、ADHD行動の予測アルゴリズムが創出につながると、申請者は考えている。
助39-48
中枢および自律神経系情報に基づく複合型ニューロフィードバックによる注意機能訓練系の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
本研究の基盤となるニューロフィードバックとは、計測した神経活動を本人にリアルタイムでフィードバックする技術である。この技術を用いた訓練により、神経活動が望ましい状態へ人工的に誘導される結果、神経系における様々な認知・運動機能が改善・向上する(Marzbani et al., 2016; Kadosh et al., 2019)。しかし、ニューロフィードバックによる訓練効果には個人差が大きいことも問題視されており(Alkoby et al., 2018)、訓練者が平等に訓練効果を得るためのシステム確立が望まれる。従来提案されてきたニューロフィードバック訓練システムにおいて、このような大きな訓練効果差が生じる第一の要因としては、獲得すべき脳活動状態(ゴール)が画一的に設定されていた点が挙げられる。つまり、このような画一的なゴールの下での教師あり学習則では、ある訓練者にとっては適切なゴールであったとしても、別の訓練者にとっては獲得しにくい不適切なゴールとなり、十分な訓練効果が得られないリスクを伴う。第二の要因としては、訓練時における訓練者の心理状態を考慮していないことが挙げられる。実際、訓練効果差が生まれる要因としてリラックスや集中の度合いなどの心理要因の影響が指摘されている(Kadosh et al., 2019)。これは、訓練効果を得やすい脳機能特性を有する訓練者であっても、訓練中に集中できていなければ効果が減弱してしまうことを意味する。しかしながら、訓練中において訓練者の心理状態をモニターするシステムは未だ提案されていない。
②目的
本研究では、ヒトの注意機能を訓練対象とし、この認知機能を向上するために必要な中枢神経系の活動獲得を促すニューロフィードバック訓練システムを開発する。この際、訓練者間の訓練効果差を克服するため、中枢神経系において獲得すべきゴールを設定しない柔軟な訓練過程を採用する。さらに、個々人の訓練効果を最大化するため、心拍変動に基づく自律神経系のリアルタイム解析を組み込み、訓練中における心理状態も同時にモニターする系を構築する。つまり、中枢神経系と自律神経系の活動を実時間で並列処理し、それらの複合的情報を呈示することで、適切な心理状態の下でのニューロフィードバック訓練を実施する。これにより、より多くの対象者に対して平等かつ最大の訓練効果(望ましい神経活動の獲得)をもたらすことを目指す。
助39-49
マタギの知と技術の継承に関する社会学的研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
失われつつある技術と智慧をいかに継承するか。本研究はこの問題意識を出発点とします。申請者は昨年5月から秋田県湯沢市秋ノ宮の湯ノ岱マタギの調査を行ってきました。「獣害」問題に象徴されるように、人間生活と自然のバランスが著しく乱れ始めた昨今、両者を仲介するような役回りを担ってきたマタギの知と技術を引き継ぐ可能性を考えたからです。調査を通じ、それら「現場の知」ともいうべき全体像は教科書的には扱いきれないことに行き当たりました。たとえば、対峙するクマに引き金を引く瞬間をどう選ぶか、目の前にあるマイタケを採るか残すかという選択の数々は、それまでの経験や現代的な社会背景、道具の性能、天候や市場価格など、多様な網の目の中でなされているものでした。「現場の知」の粋は、現場をかたちづくる具体的な状況抜きに継承されるものではありません。「獣害」対策とハンター養成が叫ばれる昨今、改めて現場の具体性に即した知と技術にこそ目を向ける重要性が認められます。
②目的
これを踏まえ、本研究は「現場の知」がどのように生み出され、共有され、引き継がれていくのか、その実践を湯ノ岱マタギの事例に学ぶことを課題とします。変わりゆく自然環境と人間との関係のただなかで、どのような創意工夫があてがわれているのか。マタギとして60年近く活動を続けるS氏とその弟子のH氏を研究対象とし、「現場の知」の変容と継承の過程を記録します。
助39-50
「心の目」の欠如:国内における新奇事例「アファンタジア(aphantasia)」の提唱
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
“みなさんの目の前にない物(例えば、リンゴ)を頭のなかで思い浮かべてみてください。”
この機能は「心的イメージ」といい、“現実に刺激は存在しないが、頭の中でそれを疑似体験できること”と定義される。最近、アファンタジア(aphantasia)といって、イメージが思い浮かべられない新奇事例が報告されている(Zeman et al., 2015)。
①背景:内外における当該分野の動向
アファンタジアの定義は、“実際の知覚に異常はないが、イメージを形成できない状態”(Zeman et al., 2015)である。出現率は十分にはわかっておらず、その様態も明らかでない。提唱者のZemanをはじめ海外の研究チームでも知見が得られ始めた段階であり、国内ではその存在すら知られていない。心的イメージに関する研究は、心理学の歴史において100年以上前から取り組まれてきたが、イメージの形成(どれだけ鮮明にイメージを形成できるか)については、そもそも大きな個人差が指摘されてきた。アファンタジアは「心の目」の欠如とも言われ、個人差の極端な事例と考えられる。
②目的:課題設定とねらい
本研究は、国内先駆的研究としてアファンタジアの「出現率」と「イメージ特性」の解明に取り組み、科学的知見とともにその存在を社会に発信して、研究の初期段階として人々の理解(気づき)を促進しようとするものである。発達障害の例に見るように、新奇事例はその存在を「知られていないこと」が偏見・差別の対象となるし、特に感覚・知覚・認知に関わる内的な現象は主観的なものであるので他者から理解されにくい。本研究で知見を得て、それを社会に発信することで、国内においてもアファンタジアの存在を提唱したい。
助39-51
青少年の非認知能力の向上に有効な体育授業時の教師行動の特徴
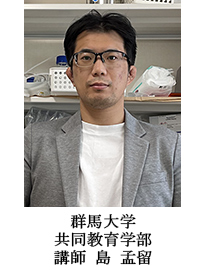 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
持続可能な社会の実現には、次世代を担う子どもたちの育成が必要不可欠であり、その上で学校教育の役割は極めて重要である。近年、認知機能以上に非認知能力が社会的な成功や健康長寿の実現に重要とされ(Heckman and Masterov, NBER Working Paper, 2007)、学校教育を通じた子どもたちの非認知能力の向上に期待が集まっている。
教育現場が抱える問題として、いじめの増加や(文部科学省、令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指 導上の諸課題に関する調査、2020)、運動・スポーツに意欲的でない子どもの増加(スポーツ庁、令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果、2020)などあるが、これらは非認知能力のうち「共感性」や「自己効力感」と関連する。青少年の運動不足がいじめ行動と関連すると示唆されていることから(Arufe-Giráldez et al., Int J Environ Res Public Health, 2019)、共感性や自己効力感を養う学校教育が教育現場の抱える問題の解決につながる可能性がある。
運動・スポーツ活動は共感性や自己効力感を高めうることから(Shima et al., J Phys Edu Sport,2021; 神藤ら、体力研究、2017)、学校教育における体育・保健体育授業の効果が注目されるが、どのような要因が共感性や自己効力感を高めるのか詳細に迫った研究はない。「授業中、先生に個別にコツやポイントを教えてもらった」ことが、子どもたちの意識や行動の変化に大きな役割を果たすことから(スポーツ庁、2020)、本研究では、子どもら個人への声かけが生じやすい器械運動領域を対象として、共感性や自己効力感を高める教師の声かけ行動を探索する。
②目的
共感性や自己効力感を高める教師の声かけ行動を明らかにし、子どもたちの非認知能力の向上、ひいては教育現場の抱える問題の解決に貢献する体育・保健体育授業の発展を目指す。
助39-52
高性能インターネット望遠鏡の制作と高校生を対象とした新しい遠隔授業の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
本研究の目的は、高等学校の教室や生徒の自宅から利用できる高性能インターネット望遠鏡を制作し、それを活用した試行授業を通して、高校生を主な対象とした教育効果の高い天文学の新しい遠隔授業を開発することである。
天文学は自然の美しさを実感することのできる学問であり、生徒の自然科学への興味付けに最も適した分野の一つである。我が国では、高等学校の「地学」の科目でかなり高度な天文学まで学ぶことになっている。自然科学を深く理解し、その面白さを実感するためには、本物の自然の観察や実験を授業に取り入れることが重要であり、高等学校理科の新学習指導要領(平成30年度告示)でも実験・観察を通した探究活動の重要性が明示されている。しかし、天体観測は夜間にしか行えないため、授業運営の難しさから、天文学の授業はもっぱら日中に座学のみで行われているのが現状である。
教室や自宅からの遠隔操作が可能な天体望遠鏡があれば、上記のような状況は劇的に改善し得る。そこで、本研究では東京学芸大学に新設された口径40cmの光学式望遠鏡(以後、40cm鏡)を整備・改良してインターネットに接続し、教室や自宅から本格的な天体観測や解析作業をリモートで体験できるインターネット望遠鏡を開発する。さらに、学習指導要領に合わせて教育コンテンツ(学習教材)を作成し、近隣の高等学校の協力を得て試行授業を行う。遠隔観測を授業に取り入れる際の利点や問題点を洗い出し、その結果をフィードバックすることにより、教育現場で活用できるインターネット望遠鏡と教育コンテンツを完成させる。
助39-53
本物体験を提供するツアーガイドのトレーニング構築〜持続的な観光におけるガイドの質の向上に向けて
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
COVID-19による観光業の停滞は持続性について再考する好機である。訪日観光および観光立国推進法は経済の活性化という肯定的な影響を与えた一方で、急速な観光開発と訪日観光客への過度な依存を引き起こしていた。観光客増に沸いていた筆者の居住地でも、街中の混雑、観光資源の損傷、住民生活の質の低下など観光地に影響を及ぼし、文化・自然の真価が認識・伝承されない体験を提供していた。いわゆるオーバーツーリズムの問題である。オーバーツーリズムは観光客数を求める「質より量」を目指した結果であり、資源とコミュニティを維持する観光には本物体験を促す「量より質」への転換が必要である。
オーバーツーリズムを防ぎ持続的な観光にするためには、そこでの自然・文化資源を育んできた住民の長年の営みを維持しながら観光体験に組み込まなくてはならない。これには資源の意味とコミュニティの成り立ちを来訪者に伝え、それらの価値を体験してもらい、来訪者との個人的なつながりを示すことができるツアーガイドが欠かせない(Weiler and Black, 2015)。優れたツアーガイドは資源やコミュニティの価値を最大限に活かしながらストーリーを通して本物体験を提供できる(Albrecht et al., 2021)。ツアーガイドの効果を高めて質の高い持続的な観光へ一層寄与していかなければならない。
ツアーガイドの効果を高める一手法としてトレーニングがある。これまでツアーガイドの効果やトレーニングに関する研究報告例は少なく、関連した国内施策もエコツーリズム推進法(環境省、2010)に限られており、ガイドの育成体系が整備されているとは言えない状況にある。また、資源保全や本物体験においてガイドの果たす役割が十分に評価されておらず、報酬面でも施策面でも不安定で専門職として確立されていない(筆者によるインタビュー調査)。資源保全と本物体験を促進するためにはツアーガイドの効果を高める必要があり、技能の向上を図るトレーニング体系を検討しなくてはならない。
②目的:課題設定とねらい
オーバーツーリズムからの脱却には本物体験を提供できるツアーガイドの普及が不可欠な一方で、ガイドの活用、社会的認知、技能向上が遅れている。本研究ではCOVID-19による観光の変容を踏まえて今後の持続的な観光に必要となるガイドの技能と機能を検証し、ガイド育成の方策を検討することを目的とする。具体的には住民およびガイド参加者へのインタビューを通して観光の変容を多面的に捉え、本物体験を提供できるガイド要素(例えば態度、知識、スキル)を明らかにし、そのガイド要素を習得できるトレーニング体系を検討することを目指す。
助39-54
ビジョン介入を用いた英語学習に対する動機づけ向上に関する量的・質的検証
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:英語学習における動機づけとビジョンの役割
第二言語習得において、学習者の動機づけは学習成果に大きな影響を及ぼす一つの要因である。
Dörnyei (2009) のL2セルフシステム理論は、第二言語学習の動機づけの一つの要因として将来の自己像の明確さを取り上げ、(1) 将来目標言語を理想的に使っているような将来なりたい自己像「L2理想自己」、(2) 将来の目標言語使用に関連して、将来避けたい自己像「L2義務自己」、(3) 現在の学習状況への態度の三つの要素と動機づけの関連性について言及した。特に、この理論の中心となる将来の自己像に関するビジョンが鮮明であり、学習者がそのビジョンに向かって学習する動機づけが高まると述べている。Sato and Lara (2019) がチリ人英語学習者を対象に実施した研究では、8回にわたって学習者のビジョンを明確にするビジョンを明確化する介入指導を実験群に実施した結果、介入指導を行わなかった対照群と比較して、L2理想自己ならびに現在の学習状況に対する態度に高まりが示された。しかしながら、これらの理想自己や義務自己と動機づけの関係性については学習者のバックグラウンドによって違いがあることがわかっており(八島、2019)、前述のような国外の研究成果が日本における学習環境に直接当てはまるとは結論づけることはできない。また、学校環境以外の場面において実際に英語を用いる経験や将来の英語使用場面を想像する機会の乏しい日本の英語学習環境においては、学習者の自己像やビジョンを授業内で養うための指導を行うことに一定の効果があると考えられる。そこで、本研究では、Sato and Lara (2019) がチリ人英語学習者に対して行った介入指導を日本人英語学習者向けに改良し、動機づけに対する効果の検証を行う。
②目的:ビジョン介入による動機づけ向上の効果検証
本研究は「日本人英語学習者に対する、ビジョンを明確化する介入指導の効果を検証する」ことを目的とする。この目的のため、介入指導が学習者の動機づけの増減に対して与える影響を 1.事前・事後に行う質問紙調査を用いた量的分析ならびに 2.事後インタビュー調査による質的分析を通して明らかにする。
助39-55
自律型モビリティと共生する社会におけるヒトの移動・回避行動特性の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
新技術や各種データ活用を積極的にまちづくりへ取り入れることで、市民の幸福度の向上を目指した「スマートシティ構想」が政府主導のもとで強力に推進されている(内閣府統合イノベーション戦略2020)。特に、ヒト・モノの自由な移動・配送のために、ヒトと共生する「自律型モビリティ」の活躍が期待されており、自動車会社がモビリティカンパニーへのシフトを宣言し、まちづくりに取り組み始めるという、これまでにない業界の大きな動きがその重要性を物語っている。
スマートシティでは、ヒトとモビリティの共生のために街や道路の構造は大きく見直され、移動に対してはより負荷なく、物流は的確にコントロールされる。ヒトを運ぶだけでなく、モノを運ぶ自律型モビリティが闊歩している街の中で、私たちの日々の行動はどのように変化するのだろうか。例えば、歩道で自律走行する物流用モビリティと正面からすれ違うときに、私たちは人間の歩行者と同じように振る舞うことができるのだろうか。人間相手には、周囲の状況から「相手が避けてくれるだろう」と認知・判断する私たちの予測行動も、モビリティを相手にした場合に通じるかどうかはわからない。誰もが安心・安全のモビリティ社会の実現には、自律型モビリティと関わる際のヒトの行動特性を明らかにすることが求められる。
②目的:課題設定とねらい
本研究の目的は、「ヒトが自律型モビリティに対してどのように振る舞うか」というヒトの行動特性を明らかにすることである。具体的には、来たるスマートシティ時代を想定した物流用自律型モビリティを用いて、そのモビリティと関わる際のヒトの移動・回避行動の特性を明らかにする。実環境をリアルに再現する物流用自律型モビリティを開発すると同時に、実際にそのモビリティを用いてヒトを対象とした心理物理実験を実施し、ヒトの移動・回避に関わる行動データを取得する。
助39-56
医看工芸連携を促進する共創型知的財産教育とその手法についての実証的研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
医療現場における現場改善の活動は、従来から行なわれているものの、繁忙な日々の改善活動が中心で、現場のニーズ提供者が、新たな医療機器などの製品化に関与する時間の確保は難しい現状にある。一方で、医師、看護師などの医療・介護従事者、工学研究者、技術者、デザイナーの知的財産に対する関心は高まっているが、啓発活動の機会が十分に行き渡っていないことが考えられる。このような状況で、良いアイデアが生まれたとしても、その成果である知的財産を正しく認識することができない恐れがある。そこで、異なる専門分野であっても知的財産マインドが、共通の価値観としてコミュニケーションを助け、円滑な製品・サービスの開発による新たなイノベーションの可能性となることを期して、研究開発のプロセスに沿った実践的な知的財産マインドを養成していく必要がある。
②目的
「医看工芸連携」とは、従来の医工連携の範囲を広げた医療・看護・工学・芸術分野の連携活動を促進啓発し、有益なアイデアを円滑に医療機器や医療サービスの開発に活用するための活動である。例えば、具体化したアイデアを製品化する場合、必ず特許や意匠、商標、著作権といった知的財産が関わりをもつことになり、誰が創作に関与したのか、どんな役割を果たしたのかということを把握しておく必要がある。本研究では、このような医看工芸連携に関与する人材が、効率的に共通の価値観として知的財産マインドを醸成するための実践的なケーススタディ教材、およびその教育手法を開発することを目的としている。
助39-57
評価表現分析で読み解く医学論文査読者の嗜好と思考:査読自動化へ向けた基盤研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
「医学研究の質を評価する仕組み」として広く採用される現行の査読には多くの課題がある。最大の問題は査読プロセスの不透明性であるが、それ以外にも、良質な査読者の不足に始まり、実体を伴わない査読で研究者を食い物にするハゲタカジャーナル、論文著者による査読者へのなりすまし、査読者による研究の盗用など、解決されるべき問題は山積する。さらに日本では、査読の仕組み自体を学ぶ機会が極端に少なく、そこに英語の問題も加わる。我々はこれら諸問題への解決策として査読者教育に焦点を当て、教材開発やワークショップ開催など様々な活動を行ってきた。その中で、これまで解明されてこなかった査読者の嗜好や思考を明確化する作業にも着手し、自身の専門である臨床疫学的手法を用いて理論構築まで行った。
②目的
この理論的枠組みを検証するための実証的エビデンスとして、我々はオープン査読制を採用する雑誌で公開される電子データの存在に着目した。本研究では、一部の雑誌で電子データとして公開されるようになった査読レポートを言語データとして蓄積・データベース化し、言語学的解析と臨床疫学的解析とを組み合わせて、査読者が医学論文の何をどのように評価しているのか明らかにする。今後の人工知能を用いた査読の自動化と研究者教育への応用を見据えた基盤研究である。
助39-58
プロジェクションマッピングを用いた3次元コンテンツ提示による幼児教育のための能動的学習支援システム
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
幼少期は生涯に渡る人間形成の基礎を培う重要な時期であり、幼少期における教育は成長に大きな影響を与える。少子化が進む現在、教育への関心は増してきている。特に昨今の新型ウィルスの蔓延防止対策により自宅で過ごす時間が増加する中で、家庭における教育の重要性は益々高まっており一般家庭にも導入可能なより質が高く効果的な教材が求められている。例えば、3次元的な空間認識能力を育む目的では、積み木や嵌め合いパズルなどの知育玩具が提案・開発されている。また感受性や自立性を育むことも重要であり、そのための絵本の効果が明らかになっている[藤田2019]。特に本を開くとコンテンツが飛び出す立体的な仕掛けが施されている「仕掛け絵本」は、その3次元的な視覚効果や絵本とのインタラクションにより想像力などと同時に空間認識能力をも鍛える有効な教材として知られている。同様に、児童館などの公共施設で公演されてきた人形劇も、人形を立体的に動かすことがより豊かな感情表現を可能とするため、情緒的発達面で有効な教材であることが知られている [金城2009]。近年の教育現場ではタブレット端末などを活用した教育用デジタルコンテンツの導入が進んでいる。デジタル化することで多様な教材を省スペースで準備でき、幼児の個性や発達状況に応じた適切なコンテンツの提供が可能となるため、一般家庭向けコンテンツとしても有力である。しかし、仕掛け絵本のページをめくると飛び出す効果や、人形劇における人形の立体的な動きによる感情表現は、アナログならではの特長である。仕掛け絵本や人形劇などの3次元的な体験を損なうことなく、電子的に提供可能な教材が必要である。
②目的:課題設定とねらい
本研究では、コンピュータビジョン技術やICT技術を活用することで一般家庭において手軽にインタラクティブな体験を提供可能なデジタル教材を実現する。近年では、新型ウィルスによる感染症対策による巣ごもり需要もあり、デジタルコンテンツの鑑賞手段として一般家庭におけるプロジェクタの普及が進んでいることから、本研究ではプロジェクションマッピングを用いてコンテンツの3次元的な視覚効果を電子的に実現する。特に、主に幼児を対象とする上で、大きなスクリーンに投影可能である点と、3Dメガネなどの特別な機器を必要としない視聴する上での手軽さを重視する。大きなスクリーンに投影することで、子供の背丈と同程度の大きさのコンテンツの提示が可能となり、子供との親和性を高め効果的なインタラクションを実現できる。また、ヘッドマウントディスプレイで指摘されている眼精疲労や斜視のリスクが低いという利点は極めて重要である。
助39-59
立体視180度動画を用いたVR建設現場教材の開発と脳波・脈波モニタリングによる学修効果の評価
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
建築施工学とは、建築生産の根幹であり、いわゆる職人と呼ばれる技能労働者を指揮して建築を完成させるための経験工学である。ゆえに建設現場での実習を取り入れた学修を含めるべきであるが、危険が伴うため大学教育では座学や動画視聴による単方向の指導や限定的な現場見学に留まっている。建築系大学卒業者を前提とした新入社員研修のための仮想体験型VR教材の開発が進む一方、基本的な専門用語や施工手順などの知識を有さない初学者向け教材には及んでいない。この要因として、膨大な建築現場知識の網羅的な学修は容易でなく、対費用効果の面からも開発メーカーが消極的であることのほか、あらゆる分野に浸透しているVR教材に対して、学修効果の定量的な評価方法が確立されていないなど、学修ツールとして未成熟であるのが現状である。
②目的
建築系大学生の革新的な体験型授業の創出を試み、建築施工学と生体工学の学問的なアプローチを融合させた新時代の人工現実感(VR)教育システムの確立を目的とする。本研究計画では、建設現場の経験工学に基づいたVR建設現場シミュレータを構築するとともに、そのVR現場見学の学修効果を脳波解析による脳活動特性および心拍変動による自律神経系の評価から検証する。
助39-60
AI技術援用による科学的事実に基づいたエネルギー政策の構築
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
日本はこれまで「科学技術立国」を掲げて世界の科学技術の進歩と発展を担ってきた。しかしながらその科学振興に社会的懸念を与えた事例が2011年3月の福島第一原発事故といえる。事故では複数の原子炉で炉心溶融と水素爆発が発生した結果、広範囲の土壌、水や食品が汚染され、約16万人以上の福島県民が避難し未曾有の社会的混乱となった。事故から10年を迎える現在も廃炉作業は続き避難は続いており、経済産業省による2016年の試算では、廃炉、除染、損害賠償等に22兆円が必要とされている。
一般的には、事故の原因は大規模な地震や津波等の自然災害、そして政府や電力会社による安全対策の軽視だとされている。しかしながら実は、事故の根本的な原因として、エネルギー・原子力政策の審議会では、原子力業界の利害関係者によって主観的・楽観的・非科学的で一方的な議論が行われ、かつ原子力業界の調整の場となっていたことが挙げられる。この根本的原因への社会的な分析や解決は行わないまま現在に至ることは、日本のエネルギー政策は現在も危険な状況にあるともいえる。
従来、日本のエネルギー政策は、経済産業省などを事務局として経済界を中心とした利害関係者から構成される審議会により、省庁の考えを示した資料を元に有識者の意見を聞きながら決定されてきた。審議会は専門家の様々な意見を効率的に反映させて公開で行える利点があるものの、経済的に強い業界の主張や思い込みが議論に方向性や影響を与え、また根拠や論理性の精査のない結論に陥りやすく、かつ弱い業界や一般市民、特に将来世代への配慮も少なくなる傾向がある。エネルギー分野の公共政策は一般社会や将来世代などに影響を与える重要なものであるにも関わらず、日本政府の政策立案の意思決定プロセスは利害関係者の思い込みや議論の誘導、科学的妥当性について不明瞭な状況であった。そして客観的で科学的かつ独立した立場からの政策分析は事故後の現在でさえ十分に行われていない。
科学的根拠に基づく政策の必要性は、少なくとも欧米諸国では公共政策の一つの分野として議論が進められている。またエネルギー分野については古くから科学的に議論されており特別視さえされていない。一方の日本では世界に遅れること2017年、政府がEBPM推進委員会(EBPM: Evidence-Based Policy Making, 証拠に基づく政策立案)を立ち上げたものの、いまだ十分な議論は行われておらず、エネルギー・原子力政策といった、政府と国民感情が剥離したテーマについては踏み込んだ議論や学術的研究は国内では進んでいない。
②目的
本研究では、将来の日本社会にとって望ましい「科学的事実に基づいたエネルギー政策」(Evidenced Based Energy Policy)の手法を構築することを目的とする。AI技術、特に機械学習と深層学習の援用により、福島第一原発事故後の日本のエネルギー・原子力政策の議論の構造や傾向から、過去と現状の意思決定プロセスを明らかにし、科学的事実に基づいたエネルギー・原子力政策の在り方を提示する。
助39-61
身体と社会:乳幼児の運動協調が社会関係の形成に及ぼす効果
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
動きの同期(synchronous)とは「自分の身体動作と他者の身体動作が呼応すること」と定義される(Tichko, Kim, & Large, 2021)。互いの動作のリズムやタイミングが一致する時間的側面は、脳内の前帯状回の神経機構に統制され、互いの動作の形態が類似・一致する空間的側面は、筋肉運動機能の発達的拘束を受ける(浅田、2009)。前者は、運動協調の問題(松島・神園、2004;吉田、2012;吉田・石黒・浅田、2009)、後者は、動作模倣の問題として扱われる(古畑・板倉、2016;板倉・開、2015;加藤、2016;宮﨑、2015)。動作模倣は、その後の社会認知の発達にも影響を及ぼすため、乳幼児を対象に研究の知見が蓄積されてきた。申請者も動作模倣と社会関係の形成に関わる研究を精力的に行ってきている(秋元・大石・若井・藤島、2020;中内・藤島・大石、2019;大石、2019;坂本・須藤・渡邉・金谷・大石、2020)。けれども、乳幼児の運動協調に関する発達研究は、必ずしも十分に行われているわけではない。
②目的:課題設定とねらい
乳幼児の運動協調は、後年の社会関係形成を導く重要な心理学的現象である。しかしながら、同年齢の乳幼児の間に、(1)運動協調がどのようにして生起するのか、(2)何を契機に運動協調の意図が発現するのかは未解明である。また、(3)保育・療育場面で発達過程を縦断的に観察した知見もない。発達に心配があり、後年に自閉スペクトラム症の確定診断を受ける乳幼児の場合、運動・動作の「ぎこちなさ」が見られ、生後30か月までに定型発達児との発達的分岐が生じると指摘されている(松島・神園、2004)。よって、本研究では、この問いを解き明かす創発的な試みとして、自閉スペクトラム症児と定型発達児がインクルーシブ教育を受ける特別支援学校・幼稚部で実験的観察を行う。乳幼児の運動協調において、他者の身体が存在する意義の指摘をねらいとする。
