受領者紹介
特別テーマ
助40-01
廃プラスチックのビッグデータ分析による識別モデルの構築と評価手法の確立【SDGs 12】
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
海洋汚染に代表される廃プラスチック問題の解決のためには,多様なプラスチックのビッグデータ分析と最新の技術を活用した自動選別システムが不可欠である.プラスチック製容器包装にPE, PS, PP, PETといった異なる素材が含まれており,各素材に応じた再資源化を行うための選別が行われている.現在,多くのリサイクル工場では手作業による選別が行われており,選別の効率性やCOVID-19禍での安全性が課題となっている.昨年度,共同研究者らは,テラヘルツ波を照射したときに観測される廃プラスチックの性質(透過率)を用いた廃プラ選別装置を開発した.しかし,廃プラスチックの形状や状態は多用かつ, 複雑であり, 実際の観測データから各素材を,より高精度に識別するモデルの構築が課題であった.
一方,観測データから特定の素材を識別する技術は,廃プラスチックの識別に関する研究は世界的に見ても,実証データ分析が遅れており, まだ始まったばかりである.また,これらの研究における識別モデルの性能評価は,識別モデルが素材を正確に識別することができた割合(正答率など)による評価が主である.本研究では,リサイクル現場のビッグデータ分析の結果に基づき, 正答率が異なると,廃プラスチックの再資源化量も結果的に異なることに着目し,各識別モデルの適用により,最適なリサイクル手法の選択によって期待できる再資源化の経済価値という新たな観点からの評価を検討する.
②目的
本研究の目的は,市中で回収された廃プラスチックの素材の識別方法を確立することにある.具体的には,実際に市中で回収された容器包装系の廃プラスチックに対して,異なる周波数を持つ複数のテラヘルツ波を照射し,観測データを取得する.観測データに対して複数の識別モデルを適用し,それぞれの性能・特徴を比較し,廃プラスチックの識別に適した方法を明らかにする.また,識別モデルの性能を評価する指標の一つとして,各識別モデルによって識別され,最適技術で再資源化されたと仮定したときに期待される経済価値や環境負荷を考
助40-02
高開口率の細胞足場シートを用いたサスティナブル食肉培養システムの開発【SDGs 2】
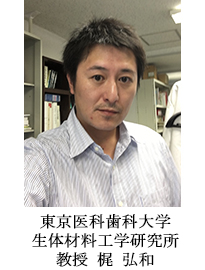 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
現在の漁業や畜産業に依存した食肉供給システムでは将来的に需要に対して供給が追い付かなくなると懸念されている。特に、健康志向の高まりから魚類の消費が増加しており、漁業の生態系への影響と環境負荷が問題視されている。一方で、環境汚染により魚に水銀が含まれる場合があり、健康への影響が懸念されている。したがって、持続的に供給できる安全な魚肉の作製が社会的な課題である。持続可能な食糧供給システムとして細胞農業が注目されている。細胞農業とは、動物や植物から収穫される産物を、人工的に細胞を培養することにより生産する方法である。2040年には世界で約60兆円の市場になると考えられており、多くの企業が細胞農業の技術に注目している。また、細胞農業は世界的に高まる動物福祉への要求に対応することができる。2020年にはシンガポールで培養鶏肉の販売が世界で初めて承認されている。
②目的
上記のように細胞農業は世界的に開発が進んでおり、これまでは牛や魚の筋肉細胞の入手条件や培養液(培地)の組成が主に研究されてきた。現在は、培養肉の成形技術(細胞の積層化など)やマテリアルの比率に関する以下の課題がある。
1.成形技術が未発達(たとえばペースト状の培養肉になっている)
2.足場材料の存在比率が高い(細胞以外のマテリアルが多く存在している)
3.本来の動物や植物などの食品と比較してコストが高い
これらを解決するために、組織工学分野の研究開発動向として、細胞を三次元的に培養・増殖させる「三次元培養法」が注目されている。本研究では、申請者らが開発した三次元培養法の「三次元メッシュ培養法」により実際の魚肉に似た層状の組織を効率的に作製し、上記課題の解決を目指す。これまでのメッシュシートは食用に利用できない材料で作製されていたが、本研究では、カニやエビなどの殻の主成分であるキチンに由来するキトサンを細胞足場材料とした食べられるメッシュシートを作製する。
③学術的な独自性と意義
申請者らが開発したメッシュ培養法は、底面から浮かしたメッシュシートの上で細胞を培養するこれまでに無いタイプの細胞培養法である。この培養法では、微細な目を持った網の上に細胞を接着させ、増殖した細胞がその目(開口部)を埋めることで細胞シートが形成される。この培養法のユニークな点は、メッシュの目の中の細胞は、生体内の細胞と同様に主に細胞間接着に頼って生存しており、細胞培養に通常使われるプラスチック基板などに張り付いた細胞とは状態が異なるという点である。この様な状態の細胞は、容易に立体化(三次元化)することができる。したがって、メッシュ培養により、簡単に厚みを持った細胞シートを作製することができる。メッシュシートの線幅は5-20ミクロン程度であり、メッシュの開口部の一片の長さは直径100-200ミクロン程である(開口部の形は自由に決められる)。したがって、作製した細胞シートに対して足場材料の混入が極めて少ない。メッシュで補強された組織であるため、細胞シートとして取り扱いが容易であり、積層化もできる。さらに、メッシュ開口部の形をひし形や長方形にすることにより細胞の向きを揃える(配向させる)ことができ、細胞の配向性の制御は筋肉繊維を作製する上で極めて重要である。
基本テーマ2
助40-03
磁性扁長粒子の形状異方性を利用したナノ複相膜の磁気光学効果の高感度化
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
磁気光学効果は、近年の高度情報化社会を支える光エレクトロニクスの分野で光の変換・制御を司る中心であるが、代表的な磁気光学材料はフェライトガーネット(YIG)が不動である。一方で、高品質な結晶性が求められるYIGにはナノサイズの微細化が望めず、光エレクトロニクスと高度集積化を基盤とするナノエレクトロニクスの融合においては、材料学的な発想の転換が求められる。申請者らは、透明セラミクス中に磁性金属ナノ粒子を分散させた「ナノ複相膜」において、YIG結晶の40倍のファラデー回転角(θF)が得られることを見出した(N. Kobayashi, et al.,Sci. Rep.8, 4978, 2017)。これはYIG結晶の原子に束縛されるスピン依存電子より、ナノ複相膜の強磁性ナノ粒子間のスピン依存トンネル伝導電子の方が、外部磁界への感受率が大きく、誘電率の非対角成分に大きく寄与するためと考えられる。
②目的
本研究提案では、ナノ複相膜中の金属ナノ粒子を「球」から「扁長」形状へ変化させ配列させることで、形状異方性を利用し磁気光学効果の高感度化を実現することを目的とする。ナノスケールの極限的な磁気-光変換機能の基盤技術を確立することは、情報化社会において通信の高速化・低電力化やデバイスの小型化を可能にする。既存のYIG系光学結晶は、qFが小さく、十分なθFを得るために強力(巨大)な磁石が必要である点が、素子の小型化・薄型化に向けた課題であった。本研究提案の狙いである磁気光学効果の高感度化を達成できれば、わずかな磁界で大きなθFが期待でき、磁石の体積を減少または磁石自体を省けるため、光学素子の小型化・薄型化に貢献できる。
助40-04
磁性ワイル半金属のトポロジーに由来する駆動力を用いた磁気秩序の高効率制御法の確立とプロトタイプ実証
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、物質の特性をトポロジー(位相幾何学的性質)によって特徴付け、材料やデバイスの機能創発を図る研究が多くの領域で活発になっている。スピントロニクスはその代表例である。ワイル半金属はトポロジカル物質の一種であり、強磁性体やカイラル反強磁性体と呼ばれる磁性材料の中には、このワイル半金属に該当する物質が存在する。これらの物質ではバンドが交差した点(ワイル点)の近傍で数千テスラもの仮想磁場が生じ、これにより例えばカイラル反強磁性体では磁化がゼロであるにも関わらず巨大な異常ホール効果が現れる。このようなワイル半金属の特異な物性は新規デバイス等への応用も期待される。
こうした中で申請者は世界で初めて反強磁性ワイル半金属Mn3Snのエピタキシャル薄膜の作製に成功し、スピン軌道トルクと呼ばれる電流誘起駆動力によって、そのスピン構造の回転すなわちワイル点対の回転現象を発見した。申請者らの研究をはじめ、ワイル半金属におけるトポロジーの電気的制御の研究は近年増加しているが、その一方でワイル半金属のトポロジー由来の駆動力による磁性材料の電気的制御に関する研究は極めて少ない。
②目的
本研究では強磁性・反強磁性ワイル半金属を用い、トポロジー由来の駆動力の利用方法の確立に挑戦する。新規量子効果がもたらす巨大な駆動力によるスピン構造の高効率制御法を構築して、ナノスケールの磁気トンネル接合や細線素子でのプロトタイプ実証を行い、超低消費電力デバイスへの道を切り拓くことが本研究の目的である。
助40-05
食道癌リンパ節転移を見落とさず検知するPETを応用した術中計測支援機器の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
内視鏡手術やロボット支援手術の進歩にともなって,外科の「取る」技術が進歩を続ける今,「術中にがんを見る」技術が求められている.特に,術中における食道癌のリンパ節転移の見極めは,術前の画像診断を用いても,術前・術中での患者の体位差や呼吸運動の影響などから非常に難しい.術中にリンパ節転移を目視することはほぼ不可能であるため,現状の外科治療では,転移する可能性のあるリンパ節をすべて切除する治療を標準とし,根治性を高めてきた.しかし,高侵襲な治療となるにも関わらず,切除後の病理検査で転移が認められたものは極めて僅かであると報告されている(S.Yoshimura Clinical Nuclear Medicine 2020, Y Kakeji, Journal of Thoracic Disease 2017).術後の死亡率の高さも指摘されている(H.Takeuchi, Ann Surg Oncol 2017)ことから.術中において適切な切除範囲の決定が課題となっている.
②目的
先行研究として,陽電子放出断層撮像(PET)を小型化し,術中利用する鉗子型ミニPETの開発を行い,PET機能を応用した癌検知の可能性を確認した.しかし,鉗子構造を模したことで,検知精度が対象部位の大きさや使用者の技量に大きく依存することが確認され,術中に安定かつ正確に計測することが課題となっている.そこで,鉗子型ミニPETを基本構造とし,体内自由度の拡張と計測動作を支援するロボット技術の組込み,および強化学習を利用した検知支援機能の構築により,適切な食道癌の切除範囲をヒトの技量に依存せず術中に決定する手法の実現を目指す.本申請では,実験的検討段階として,提案システムに必要な機構面と制御面における仕様選定と試作開発を主たる目的とする.
助40-06
超臨界CO2が創出する量子空間欠陥に基づいた可視発光ドットの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ZnOは紫外発光特性を有するワイドギャップ半導体であるが,量子化することで欠陥構造に起因した可視発光特性が発現するため, GaやInといった希少元素に代わる次世代の発光材料として期待を集めている.一方で,量子化されたZnOドットは高い表面エネルギーに起因して容易に凝集し,「発光強度とハンドリング性の著しい低下」が頻発することが問題として知られている.有力な解決策として,量子ドット表面に界面活性剤が結合した「有機修飾量子ドット」が提案されている(Angew. Chemie. Int. Ed., 44 (2005) 6712).量子ドットの表面に有機分子が化学的に結合することで,粒子の粗大化による発光強度の低下を回避できるだけでなく,有機溶媒への完全分散性を付与できるため,製膜や配列制御といったデバイス実装面でのハンドリング性を著しく向上させることが可能である.しかしながら,有機修飾量子ドットを合成する現在主流のHeat-up法(ACS Nano, 13 (2019) 7716)や水熱法(Cryst. Growth Des. 14 (2014) 5388)は,「量子化」を達成できる一方で, 300℃以上の高温域の利用が不可欠であるため,粒子の結晶化がいち早く進行し,欠陥構造の導入や制御が困難な点が問題である.
②目的
前述の問題に対して,本研究課題は「超臨界CO2による有機修飾量子ドット合成技術」を用いる.超臨界流体は分子の運動が激しい高拡散場であり,高い過飽和度を得られるため,合成粒子の「量子化」を達成できる.また,高拡散性を有する超臨界流体場では,核生成・結晶成長プロセスにおける非平衡性も大きいため,欠陥構造の導入にも有利である.しかしながら,これまで量子ドットの合成に利用されてきた超臨界流体は,水(Adv. Mater., 19 (2007) 203)やアルコール(J. Supercrit. Fluids, 52 (2010) 76)といった200℃以上の臨界点を有する物質群であり,粒子の結晶化も迅速に進行するため,欠陥構造の導入や制御には困難な側面も有していた.一方で,超臨界CO2は31℃という低温の臨界点を有するため,「高拡散×低温」という,「欠陥導入」と「欠陥量の制御」の双方において理想的な条件を達成できる媒体である.更に超臨界CO2は,脱圧するのみでCO2が分離される「無溶媒プロセス」であるため,従来技術と比べ,「有機溶媒の使用回避」や「後処理工程の大幅な簡素化」といった優位性もある.従って,超臨界CO2を用いた量子ドット合成技術は,「欠陥導入」と「欠陥量の制御」の双方を満たしつつも,合成過程で有機溶媒を排出しない革新的なドライ合成法へと昇華していく潜在性がある.以上より本研究課題は,超臨界CO2を用いた欠陥内包ZnOドットの合成と欠陥制御に基づいた可視発光特性の創出を目的とする.
助40-07
マルチロボティック測位システムの開発:リアルタイム測位の普遍化・高精度化が変える未来の情報化社会
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
移動体の位置を即時に測定する「リアルタイム測位技術」は,現代社会において様々なサービスを受けるために欠かせない.特に,GPSによる屋外測位は,カーナビゲーションやスマートフォンによる誘導など日常的に利用されている.今後は準天頂衛星システムみちびきによって測位精度が飛躍的に向上することで,自動車の自動運転,農作物の自動収穫,ドローンでの自動運送など,あらゆるシステムの無人化・自動化を実現することができる.
一方,建物内部やその周辺のようなGPS電波が届かない非GPS環境における屋内測位も重要である.一般に,屋内測位には,ユーザーが外部測位装置(カメラや電波受信機など)を設置する手間がかかり,また,装置を設置した場所でしか利用することができない欠点がある.外部測位装置に頼らないSLAM(自己位置推定と環境地図作成)のような自己測位技術もあるが,精度が低い,遅延が大きい,重量のあるセンサを測位対象に取り付ける必要があるという欠点がある.これらはペイロードの小さい小型ドローンなどの測位には致命的である.いまだに,屋内測位の技術には多くの欠点があり,さらなる技術革新を必要としている.
②目的
本研究の目的は,非GPS環境,外部測位装置を事前に設置しない,自己測位では低精度になる,という既存システムでは高精度なリアルタイム測位ができない状況に対応する「マルチロボティック測位システム」を開発し,リアルタイム測位の普遍化・高精度化を図ることである.本システムは多点に配置された測位装置を能動的に動作させる新しい構成のシステムである.対象物と測位装置を協調的に移動させることで測位情報の高精度化を実現することが可能となる.ハードウェアを試作,本システム特有の制御・計測の技術的課題を克服した協調測位法を考案し,その社会的ニーズを検討することが本研究における課題となる.
助40-08
紫外光励起-可視光検出-遷移状態分光装置開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
5フェムト秒パルス光を用いる遷移状態分光 〜化学反応に伴う分子構造変化の直接観測〜
人の目でみることが困難な高速現象は、高速ストロボ光を用いて連続写真を撮影することで可視化できる。分子振動周期より閃光時間が短い、5フェムト秒パルス光をストロボ光として用いると、分子振動を振動の実時間で計測でき、反応に伴う結合解離・生成過程を可視化できる(遷移状態分光法)。しかし、研究成果は特定の分子内光反応に限定されていた。この状況下、申請者は、光を利用して瞬時に電子基底状態の擬似熱反応を誘起する“コヒーレント分子振動励起反応”を開発し、熱反応を、金属イオンを用いて反応基質を会合させ、分子衝突によるコヒーレンスの消失を回避し、分子間反応を、可視化した。
②目的
紫外励起-可視検出-遷移状態分光法の開発 〜種々の反応への応用を目指して〜
さらに、反応系中に微量に存在する会合体のみを選択的かつコヒーレントに励起可能なスペクトルに整形し、整形-5フェムト秒パルス光(5-fs光)を用いて分子間光反応を可視化した。しかし、これまでの研究において構築してきた遷移状態分光装置では、励起光の整形と同時に検出光も整形されるため、検出可能な波長域が限定されるという欠点がある。本研究では、励起光と検出光の波長が異なる「紫外励起-可視検出遷移状態分光装置」を新たに構築し、より広範囲な化学反応への応用を可能にする。
助40-09
電気光学変調コムを用いた広帯域周波数可変かつ極低ノイズなマイクロ波発生
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高精度な時刻周波数同期は金融・証券分野における高頻度取引,エネルギー分野におけるスマートグリッドの蓄給電タイミング合わせ,IoT,及び,高度交通システムの自動運転補助等への活用が期待されている[信学誌 vol.100, p.112 (2017)].国際機関ITU-Tはその時刻配信マスタークロックを現在のCs原子時計から光格子時計に変更することを検討している.光格子時計に変更した場合,正確な時刻の校正作業が300年間も不要となり、通信機器の消費電力を大幅に削減できる.更に,上下回線の干渉防止用帯域を新たにデータ通信利用できる為,無線通信の大容量化も同時に実現できる.LNE-SYRTE(仏)グループはモード同期(ML)レーザーを用いて超低雑音なマイクロ波(12 GHz)の発生に成功した[Nat. photon.11, 44(2017)].一方、高繰返し周波数かつ超小型なマイクロコムによる光電変換は共振器のQ値がMLレーザーより低い為、低ノイズのマイクロ波発生は困難である.時刻同期応用には3周波数以上の極低ノイズな電磁波発生が必要となる.
②目的
本目的は電気光学変調(EO)器ベースの光コムの,連続的に繰り返し周波数を可変できる特徴に着目し,光とGHz周波数を自在に結合することや連続可変かつ低ノイズなマイクロ波を発生することを目指す.そのため,世界でNIST(米国)と研究代表者しか実現できていないEO変調器コムの絶対位相制御技術を発展深化させ,変調器駆動用の信号発生器の発振周波数帯域の拡大や波形整形器を駆使して,GHz~THzのマイクロ波周波数領域(ミリ波~サブミリ波)までの帯域にわたる低ノイズ電磁波発生を実証する.本研究の狙いは,光格子時計をマスタークロックとした時刻周波数配信の際、各局舎の通信機器の動作RF周波数へ高品質な“時”をつなぐ為に,その機能を担うEOコムを用いた“真の光電変換”を実現することである.
助40-10
ウェブゲームと計算論的モデリングを通して、人の汎化及び弁別能力を測定し、統合失調症との関係を評価する
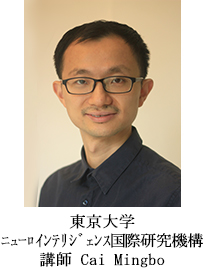 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
Schizophrenia (統合失調症) is a mental disorder that creates a huge burden to the society. Altough with intensive research, its cause remains unclear. The major medicines to treat schizophrenia target a neural transmitter receptor for dopamine named D2 (ドーパミンD2受容体). Recently, my collaborator found that this receptor is critical for animals to learn to discriminate the difference between similar situations in their predictability of future outcome (Iino, et al., Nature 2020). In other words, there is deficit in D2 receptors, animals over-generalize (過度の汎化) what they have learned. Arguably, over-generalizing in a similar but different situation from past experiences can lead to wrong prediction, and cause people to misattribute the surprising outcome to the wrong cause. It is possible that frequent confusion caused by over-generalization and misattributing causes may eventually lead people to have a disorganized view of the world, developing into delusion (妄想). However, this hypothesis has not been tested. Importantly, in order to eventually transform biological findings into the understanding of schizophrenia, behavioral experiments on human participants have to be conducted to confirm that people who have tendency to develop schizophrenia indeed over-generalize or under-discriminate different situations. Towards this goal, we have designed a web-based game to measure the degree by which people can generalize and discriminate when they need to learn to obtain better outcome.
②目的
The purpose of this study is to apply computational modeling (計算モデリング) to investigate how the ability to generalize and discriminate (汎化と弁別) during learning differs in people who have tendency to develop schizophrenia (統合失調症) with a web-based game (ウェブゲーム). We will develop computational models to quantify people’s behavior in a cognitive experiment and analyze a big database (from 1007 volunteers) we have collected across a wide range of age (distribution of participants’ age shown below.). In addition, we will test the game on a cohort of adolescent identify the potential correlation between over-generalization / under-discrimination and minor symptoms arising earlier that may eventually develop into schizophrenia.
助40-11
機能性磁性ナノ粒子を用いた磁場誘導型がん温熱療法の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
我が国における癌の死亡者数と罹患者数は高齢化を主な要因として増加し続けており、根治を目指した強力かつQOLの高い(侵襲性の低い)治療法が望まれる。高周波磁場は生体における透過率が高く、かつ影響を及ぼさない一方で、磁性ナノ粒子は交流磁場中でヒステリシス損失、超常磁性緩和(ネール緩和)および粒子の回転運動の摩擦によるブラウン緩和によって発熱することから、薬物送達システム(DDS)で腫瘍内へ送達された磁性ナノ粒子を体外から高周波の交流磁場を照射して発熱させることで腫瘍特異的であり低侵襲な(通院治療可能なQOLの高い)新しい癌治療が可能となる。
②目的
本研究では、高分子化学に根ざした戦略により、生体親和性が高くステルス効果が知られる2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine(MPC)ポリマーで被覆した磁性ナノ粒子を完成させる。これにより、全身投与による癌のナノメディシンを成功させ、体内の癌に広く適用できるよう限定解除を実施する。また、ステルス化磁性ナノ粒子の体内分布、癌への集積挙動をMRIで追跡し、治療前診断と治療を同時に可能とする医療技術を確立する
助40-12
多品種少量の放射性薬品を精緻に調製するための唯一無二の自動化システムに関する研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
微量の放射性核種を用いた非破壊的な画像診断技術は、がんの診断だけでなく社会的関心の高い疾患(アルツハイマー病や、パーキンソン病、糖尿病など)の確定診断や、創薬分野のリード化合物の評価検証に有効性が示されており、世界的にその重要性が増してきている。一方で、普及を妨げている致命的な二つの課題がある。
課題の一つは、放射性薬品の調製にかかる膨大な運用コストである。放射性薬品を調製する際に使用する容器や機器は、放射性物質で汚染された箇所を洗浄・廃棄しなければならない。市販されている半自動調製装置でも同様の洗浄・廃棄作業が必要なため、運用コストは増加する一方である。
課題のもう一つは、人材の不足である。日常診療や新薬開発に用いられる放射性薬品の多くは、物理的半減期が短いため病院や創薬機関の中で現場調製される。その中でも、テクネチウムの放射性同位体(99mTc)を標識した検査薬については、放射性核種の製造から検査薬の標識調製に至るまでを、放射線技師が行わなければならない。しかし、多くの病院が放射性薬品の調製に携わる資格保有人材を確保できていない。海外に目を向けてみると、米国、ヨーロッパ諸国や、韓国では99mTcだけでなく既に68Gaについても院内で製造できるジェネレータが普及しており、90Yや225Acのジェネレータの開発も進められている。これに伴い、人材不足も世界規模で生じている。
②目的
核医学と創薬の発展の妨げになっていた運用コストと人材不足の致命的な課題を、ロボティクスと微小液滴の操作技術によって解決し、健康長寿社会の新しい枠組みを拓く。
基本テーマ1
助40-13
機動的レーダリモートセンシングの実現に向けた小型無人機搭載合成開口レーダの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
合成開口レーダ(SAR: Synthetic Aperture Radar)は能動的にマイクロ波を送信・受信することにより地球の情報(画像)を得る環境リモートセンシング技術の一つである.SARデータは,多偏波観測(複数アンテナによる観測)によって対象物の構造・形状を推定できる点や,地表面の変位量(沈下や隆起)を面的に画像として推定できる点といった,唯一無二の特徴を持つ.そのため農作物の収量観測,地殻変動計測,水害範囲の推定,土壌水分量推定,橋梁・ダム変位モニタリングなど,様々な場面で応用・実装されている.
人工衛星は広域に観測できる(観測幅20〜50km)といったメリットがある一方で,回帰日数が数日のため,希望する時間・場所での観測が困難である.更に橋梁の床版裏やトンネル内部など,人工衛星とターゲットの位置の関係上観測できない箇所が存在する.こういった課題を解決するため,航空機搭載型SARや地上設置型SARが近年研究開発されている.しかし,航空機搭載型SARは運用に膨大なコストがかかる,地上設置型SARは定点観測のため観測範囲が限られる,などといった問題が残る.災害発生時の迅速な観測や準リアルタイム広域観測が可能な新たなSARリモートセンシング技術の開発が現在望まれている.
②目的
本研究ではSARを小型無人機に搭載した,小型無人機搭載型SARを開発することを目的とする.特に,小型無人機のうちマルチロータ型のドローンに搭載することを考える.これにより,機動的かつ準リアルタイム広域SAR観測が可能な計測技術を目指す.本研究の最終目標として,多偏波観測が可能なシステムを目指す.
助40-14
多元系スピネル酸化物ナノ粒子の合成と水分解触媒への応用
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①研究背景
持続可能な社会の実現のため、高効率な物質・エネルギー利用を支えるエネルギー変換系の確立が求められている。電極触媒(電気化学触媒)は、電位印加により常温常圧でエネルギー変換反応を進行させることが可能であり、特に近年は太陽エネルギー等の再生可能エネルギーを用いた水素製造の手法として注目されている。電気化学的な水分解による水素製造プロセスは、還元反応である水素発生反応(HER: hydrogen evolution reaction)と酸化反応の酸素発生反応(OER: oxygen evolution reaction)により達成される。この一連の反応では、アノードでのOERが4電子反応であり過電圧(すなわち、エネルギーロス)が大きく、電気化学的な水分解のボトルネックになっている。
②研究目的
以上の背景から本研究では、高活性なOER触媒の開発を行う。特に、既報より高効率なOER触媒として期待されているスピネル構造を有する金属酸化物(以下スピネル酸化物)からなる高活性OER触媒の開発を目的とした。特にスピネル酸化物のうち、近年磁性材料として注目されている多元金属元素からなるハイエントロピースピネル酸化物(HE-SO)に着目したOER触媒開発を行う。HE-SOは一般に、構成する金属元素が多成分(概ね5成分以上)であるスピネル酸化物を指す。HE-SOを始めとする多元系金属材料(合金、酸化物)は、原子同士の電子的相互作用により特異な電子状態を有することから、磁性材料や構造材料として近年着目を集めている。
助40-15
ハロゲン架橋銅(II)錯体一次元鎖のスピン量子ビットへの展開
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ノートパソコンやスマートフォンといった小型で高性能な半導体の電子機器は我々の暮らしを便利にして来た。その半導体コンピュータを超えると期待されているのが量子コンピュータである。量子コンピュータは、「0」と「1」の重ね合わせ状態にある量子ビットと呼ばれる素子を用いる。この量子ビットを多数並べて量子もつれ合い状態にすることで、同時並列的に、膨大な量の計算を一瞬ですることが可能になると期待されている。量子ビットになる物質は数多く見つかっているが、量子ビットを多数並べることは難しく、極めて重要な課題である。
②目的
ハロゲン架橋金属錯体は、金属イオンとハロゲン化物イオンが交互に一直線に並ぶ鎖構造の一次元錯体である。これまでの研究で、金属イオンにニッケル、パラジウム、白金が用いられ、金属イオンのdz2軌道とハロゲン化物イオンのpz軌道が重なることで一次元電子系の半導体となることが明らかにされている。ところが最近、銅(II)のハロゲン架橋金属錯体が見つかった。銅(II)イオンは磁気異方的なS = 1/2の電子スピンを持つ。したがって、一次元上に並んだ銅(II)の電子スピンは、遅い時期緩和を示すスピン量子ビットとして使える可能性がある。そこで本研究では、ハロゲン架橋銅(II)錯体の合成と構造、磁気特性、スピン量子ビットとしての振舞いを明らかにする。
助40-16
電荷移動錯体導入による多積層型ペロブスカイト量子ドット創出と高効率・長寿命LEDの開発
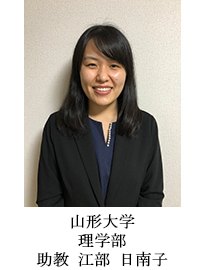 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ペロブスカイト量子ドット(PQD)は、優れた発光量子収率と色純度、化学組成制御により全可視域の発光色を再現することができ、次世代の発光デバイス(LED)材料として期待されている。PQDは、長鎖アルキル配位子で被覆されたコロイド状の半導体ナノ結晶であり、簡便かつ安価な製造プロセスにより合成することができる。しかしながら、イオン結晶のPQDは、精製過程やデバイス駆動時に表面イオンや配位子が容易に脱離し、低い材料安定性や消光サイトの形成が課題である。また、長鎖アルキル配位子は、有機溶媒中における均一分散性を担う一方、絶縁性により電子デバイスにおける電荷輸送を阻害し、デバイス性能の著しい低下を引き起こす。さらに、PQDの高い分散性は、薄膜状態の低い溶媒耐性を意味し、全塗布法による多積層化が極めて困難であり、デバイス設計が著しく制限される。以上より、従来の長鎖アルキル配位子は、優れた光物性を担保する一方、低い電子物性や材料安定性、溶媒耐性により、PQD-LEDの性能低下が課題であった。
②目的
本研究は、PQDの表面保護層として高い電子物性と材料安定性を示す電荷移動錯体(CT)を導入し、高発光かつ超安定なPQDの創出により、PQD-LEDの高効率・長寿命化を目指す。CT層は、既に申請者らにより確立されている配位子置換技術により導入を試みる。また、PQDのハロゲン組成比率の制御により青・緑・赤色発光を有するPQDを合成し、全可視域のPQDにおけるCT層の導入を試みる。さらに、CT間の強固な架橋構造の形成により、優れた溶媒耐性を示すPQD膜を開発し、全塗布法による多積層化技術を確立する。これらの技術により、これまで成し得なかった新規ヘテロ型PQDを創出し、高効率・長寿命PQD-LEDを開発する。
助40-17
機能性ドメイン境界における相転移・物性発現機構の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
強誘電体や強磁性体, 強弾性体に代表されるような強的秩序を有するフェロイック物質群は有用な機能性を有することから多くのデバイスに利用されている。これらの物質群においてはエネルギー的に等価で方位の異なる領域(ドメイン)が必然的に存在し、それらドメインを隔てているのがドメイン境界として知られている。ドメイン境界はこれまで単にドメインを隔てている壁としてのみ取り扱われてきたが、2000年代以降バルクとは異なる独自の性質を示す可能性が理論的に示唆され、実験的にも確認されるようになったことから注目が集まり、特に欧米を中心に盛んに研究されるようになってきている。一方で、ドメイン境界は数格子分と非常に薄いことから物性計測や内部構造を評価できる実験手法が限られており、研究が大きく進展するのを妨げている原因となっていた。これまでに申請者は非線形光学効果の一つである光第2高調波を用いた顕微システム(SHGM)を開発し、ドメイン境界に適用してきた。その結果、SHGMがドメイン境界に対して有用な実験手法であることを確立してきた。また、応力によって機能性を有するドメイン境界を生成・移動させることができることを世界に先駆けて明らかにしてきた。しかしながら、なぜドメイン境界でバルクとは異なる物性が発現するのか、その起因については未だに明確な結論が得られていないのが現状である。
②目的
本研究はドメイン境界において発現する極性を外部制御が容易な温度や電場,光などを用いて外部制御を行うことで、ドメイン境界で発現する物性の起因を明らかにすることを目指す。これによりドメイン境界を積極的に利用した新しい材料設計の指針を築く。これまでのドメイン境界に関する研究は、その構造や物性を評価するにとどまっており、応用を見据えた実践的な研究は殆ど行われていない。例えば、ドメイン境界は幅が狭いことに加えて高い電気伝導度や極性を示すことから高密度メモリへの応用などが期待されているが、実現にあたってはドメイン境界への情報の書き込み・読み出しが不可欠となる。本研究では世界に先駆けてこの課題に取り組む。すでに応力によって機能性ドメイン境界を生成・移動可能であることを実験的に示してきているが、応力は他の外力に比べて制御が難しいという問題点がある。そこで、制御が容易な温度や電場,光などに着目をし、ドメイン境界における機能性の制御を目指す。
助40-18
省エネルギー技術の実現に向けた強磁性酸化物材料の開拓
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
本研究課題の焦点は、熱電効果と呼ばれる、廃熱を有用な電気に変換するプロセスである。現在、民生用・産業用プロセスの多くで、エネルギーが廃熱として失われている。例えば、大規模計算機施設の電子回路や自動車などがその例である。この問題を解決するのが熱電効果であり、ゼーベック効果とネルンスト効果の2種類に分類される。前者は1990年代から盛んに研究されているが、磁性材料におけるネルンスト効果がエネルギー効率の良い熱変換の代替手段になることが最近の研究で明らかになってきた。申請者は、2021年10月より東京大学で独立した主任研究員として新しい研究室をスタートさせた。
②目的
本研究では、酸化物強磁性体および反強磁性体のネルンスト効果を探索することで、ネルンスト効果の研究をさらに発展させる。酸化物は300℃以上の高温でも化学的に安定であるという特徴を持つが、そのネルンスト効果についてはこれまで詳しく研究されてこなかった。
助40-19
強分極薄膜を自発形成する極性分子の開発 -分子の末端構造による分子配向制御-
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
一部のアモルファス極性有機分子は、真空蒸着過程で分子の永久双極子モーメント(permanent dipole moment: PDM)を膜厚方向に配向し、大きな膜分極を発生する(J. Appl. Phys. (2002)、自発配向分極、図1 )。このような分極膜は、有機EL素子の低電圧化(Appl. Phys. Lett. (2013))や振動発電(Sci. Rep. (2020))へ応用可能であると報告されており、高性能なデバイスを実現するには膜分極を大きくする必要がある。従来の分子蒸着膜では膜厚100 nmで5 Vの表面電位を発生する。
蒸着するだけで形成できる分極膜は様々な応用が考えられるが、分極膜を形成する自発配向のメカニズムは明らかになっていない。膜分極を大きくするには、分子のPDMを高秩序に膜厚方向に配向させる必要がある。実際、既報分子のPDM配向度は10%以下であり、大きな改善の余地がある。
②目的
本研究では膜分極を形成する分子配向メカニズムを明らかにし、高配向性の極性分子を開発する。従来分子の10倍以上、すなわち100 nm膜厚あたり50 V以上の強膜分極を実現する。特に、膜分極形成のためには分子の向きを揃えて配向させる分子設計が必要であり、気相成長の分野では未踏の研究領域といえる。
助40-20
鋭利なガラス管先端を利用した超電導ナノセンシング技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
極めて微弱で局所的な磁場をナノスケールの分解能で可視化し,凹凸のトポグラフィー像などと組み合わせるセンシング技術は,ナノサイズの磁性粒子や磁気構造あるいは電流分布を扱うさまざまな分野で強い関心を集めています。微小化したホール素子やスピン偏極した探針,最近ではダイヤモンド量子磁気センサを用いた磁気顕微鏡の開発が進められ,測定対象となる試料の表面状態,磁場の大きさや向き,温度などの条件に合わせ,最適な磁気センサを選択できるようになってきました。
超伝導量子干渉計(SQUID)は,測定感度が量子限界に迫る究極の磁気センサです。物質材料の磁気特性だけでなく,脳磁図などの医療分野,資源探査を含む地質学にまで幅広く普及しています。センチメートル程度の平面基板上に微細加工したSQUIDがこれまで一般的でしたが,最近では微小化したマイクロあるいはナノSQUIDも報告され,これを用いた磁気顕微鏡も開発されています。しかし,微小SQUIDを支持する基板(の角)が測定対象物と物理的に接触するため,十分に近づけることができず,本来の磁気感度,空間分解能を活かすことができませんでした。
最近,生物工学で用いられるナノピペット(先端径がナノサイズの針状ガラス管)を利用したナノSQUIDが注目を集めています。ガラス管の両側面と正面の3方向に超伝導薄膜を蒸着した素子で,先端部の超伝導ループ(2つのブリッジ接合を含む)がSQUIDとして機能します。アルミニウムや鉛,インジウムといった低融点の単元素金属超伝導体が好んで用いられ,単一電子スピンの磁気モーメントに匹敵する磁束感度が報告されています。鋭利な先端形状はナノSQUIDを測定対象物に近づけやすいので,本来の磁気感度を十分に活かせます。これを探針としてプローブ顕微鏡に用いれば,ガラス管先端が受ける力から凹凸像も同時に取得できます。しかし,露出された素子先端の金属細線が劣化しやすく,実用に大きな課題を抱えていました。
そこで本研究は,酸化に強い窒化物超伝導体を用いて,大気中で安定なナノSQUIDを実現します。さらに,これを探針としたプローブ顕微鏡を構築し,ナノスケールの磁気像と凹凸像を取得することで,素子の実用性を示します。
助40-21
元素戦略を考量した透明太陽電池の高効率化
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
太陽電池が透明であれば、窓にも設置できるため化石燃料使用量の低減に大きく貢献出来る。また、人体に有害な紫外線を吸収して発電するため、室内環境の改善にもつながる。これまでもいくつかの透明太陽電池が報告されているが、効率が高いものは透過率が低かったり、有機色素を用いているため耐久性に疑念があるなどの問題がある。我々の研究室ではこれら問題点に対応するため透明p型・n型半導体を組み合わせた太陽電池の研究を行っている。半導体を用いて透明太陽電池を作った場合、透明n型半導体中の自由電子が赤外線=熱線を反射する。そのため、夏は室内の温度上昇を、冬は熱が外に逃げるのを防ぎ省エネルギーに繋がるためさらにSDGs達成に繋がるという利点がある。
透明太陽電池を実現するには透明p型・n型半導体が必要である。透明n型半導体にはZnO:Al等、汎用元素で構成された優れたものが知られている。しかし、透明p型半導体は未だ研究段階にある。また,太陽光に含まれる紫外光は少ないので効率良く発電するには、p型半導体、太陽電池構造に工夫が必要となる。そこでこれらの問題点を解決するために以下の様に研究を進めてきた。
透明p型半導体についてはCuBr1-xIx(以下CuBrI)に着目した。 CuBrIは汎用元素である銅(Cu)、日本の生産量が世界2位のヨウ素(I)、5位の臭素(Br)からなり元素戦略において優れている。また、Brの量を変えることで、吸収光の波長が長くなってわずかに可視光を吸収するようになり、光の吸収量がx=0.0、1.0より4割程度増加し発電効率を改善することができる。
太陽電池構造については微細構造に着目した。通常の太陽電池はp型・n型の薄膜積層構造なのに対し、 Fig. 2に示す、透明n型ナノロッドの隙間を透明p型で埋める構造の太陽電池を検討してきた。これにより発電に不可欠なpn接合部分が増加し、また、電子移動距離が減り電子消滅確率が減るので発電効率が上昇することが期待できる。
②目的
これまで,低コスト化を目指し大気圧下にてFig.2に示す構造の太陽電池の作製・発電に成功している。しかし,発電効率が非常に低い。そこで、本研究ではp型半導体の高品質化、微細構造改善により効率改善を図ることを目的とする。
助40-22
二次元半導体を利用したマイクロ発光ダイオードへの機能付与
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
窒化ガリウム(GaN)系混晶の微細加工により作製可能な青色マイクロ発光ダイオード(µLED: < 104 µm2)は、安定して高い外部量子効率が得られるだけでなく小型端末への集積化の親和性も高いことから、「新しい発光素子のかたち」として強い関心が寄せられている。µLEDの開発で重要な技術の1つは、青色以外の放射色を実現する放射色の制御である。発光層であるInxGa1-xNのIn組成の増加により発光色を青色から緑色や赤色に制御可能であるが、結晶性の低下が懸念され結晶成長技術のみでは実現が容易でない。そのため、放射色変換のための発光材料を青色µLED上に直接塗布することで配置し、青色光を励起源とした光励起発光により他の放射色を得る手法が採用されている。青色µLEDの放射色変換材料には、単色性など視認の観点から、蛍光体や半導体微粒子(量子ドット: QDs)が用いられている。
他方、層状物質の単分子層(0.7 nm)からなる二次元半導体は、室温を超える励起子結合エネルギーにより、安定した光励起発光が得られる。また速い発光寿命や内因性の円偏光を放出可能なことから、新奇な機能性発光素子への展開が期待できる。しかし有効的な材料体積が小さく不純物添加によるpn制御が複雑であるため、その潜在能力はLED構造において電気的に制御が困難である。
②目的
本研究では、青色µLEDの放射色変換技術を二次元半導体に展開し、その光励起発光を利用した機能性発光素子の創生を目的とする。具体的には、青色光の導波の詳細解析に基づいた設計により、青色µLEDへの二次元半導体からなる積層構造の実装手法を検討する。また様々な二次元半導体を利用し、多機能化に資するµLEDの実現に挑む。
助40-23
反力可変触覚ディスプレイ用触知ピンアクチュエータ
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
触覚ディスプレイの触知部の情報提示は様々な手法での研究が行われており,触知ピンの上下運動や,振動刺激等の単純な情報提示が多い.特に力覚の表現は乏しく,振動刺激の振幅や周波数等で定性的な表現も試みられているが,受け手の個人差があるため,定量的な力覚の表現は難しい.力覚の表現できるデバイスとして,発生力の大きい形状記憶合金製触覚ディスプレイも検討されているが,その動作にはバイアスばね機構が必要で,小型化には不向きである.
申請者はこれまでに,非晶質時の粘性流動特性を利用して成形加工が可能な高成形性形状記憶合金(High Formable Shape Memory Alloy: HFSMA)の開発を行ってきた.本合金を用いることで従来にない3次元構造を持った形状記憶合金マイクロアクチュエータの実現可能となる.そこで,触知部と駆動部を一体化させた小型化した触知ピンアクチュエータと温度により触知部からの反力を制御できる,新しい触覚・力覚の表現可能な触覚ディスプレイ用触知ピンアクチュエータの構想に至った
②目的
本申請では,HFSMAの加工特性を活かした成形加工により,駆動部と触知部が一体化したマイクロアクチュエータ(以下,触知ピンアクチュエータ)を集積化した触覚ディスプレイを作製することを目的とする.新しい駆動原理に基づき,アクチュエータ温度を変えることで触知部からの指への反力の大きさを線形的に制御可能である.
助40-24
酸化物異相界面におけるバンド変調機構の解明と制御に向けた原子・電子レベル解析
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
異なる酸化物を原子層厚さで積層した酸化物薄膜は、極薄の電子・磁気デバイスや燃料電池電極として期待される。他方、異なる酸化物どうしの界面『酸化物異相界面』では、その特異な原子構造に起因し、電子バンド変調や電荷移動が生じ、構成材料の足し合わせではない特異な電子特性が発現する。よって酸化物薄膜の電子特性を精密制御し、また新奇な材料特性を付与するためには、異相界面における原子・電子構造の決定と、電子特性との関係の解明が必須である。
上記に対し、電子顕微鏡観察が用いられてきたが、多元系かつ複雑な原子構造をもつ酸化物異相界面に対する解析は今なお難しい。また量子力学にもとづく第一原理計算も用いられているが、計算コストが莫大なため、単純な組成や結晶構造に限定される。よって酸化物異相界面における電子特性の起源は多くが未解明なため、その制御方法は今なお経験則のみであり、最適な制御指針は確立されていない。
②目的
本研究では人工ニューラルネットワーク(ANN)、第一原理計算、電子顕微鏡観察による『人工知能技術、理論計算、実験』を融合させた方法を確立する。まず第一原理計算データを学習させた多元系ANN原子間ポテンシャルを構築して大規模分子シミュレーションを行い、異相界面の原子構造を高速・高精度で予測する。また得られた異相界面構造を用いて、スパコンによる大規模第一原理計算を実行し、電子バンド構造を決定する。そして電子顕微鏡観察により、計算結果と観察像を比較し、異相界面構造を正確に決定する。同様に界面の結晶方位や組成を変えて解析し、原子構造と電子バンド構造との関係を系統的に解明する。得られた知見から、酸化物異相界面の最適な設計指針を提案する。
助40-25
光生成キャリアの空間分離を特徴とする量子ドット太陽電池の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
申請者は自身の経験からも、災害時の電源確保は重要な問題と捉えている。しかしながら、非常用電源の法定点検は、東日本大震災を経験した現在でさえ、9割が未実施という危機的な状況が続いている。これは、定期点検にかけるコストや時間を割けないことなど、実質的な維持管理の限界の現れといえる。したがって、発電機のみに頼らない、メンテナンスフリーの非常用電源を用意することは極めて有効と考えられる。そこで本研究では、新奇化合物半導体材料 (GaAsPN) を開発することにより、高効率かつ高い設置性を有する非常用太陽電池を提案する。
②目的
仮設太陽電池:避難所における非常用太陽電池の活用例.非常用電源として軽量フレキシブル太陽電池を仮設し、避難所生活、救援ドローン等への電源供給を行う.
非常用太陽電池に求められるものは、1コンパクトな収納性と設置の簡便性、2備蓄時の定期点検が不要であること、3高い効率と経済性である。しかしながら、既存の太陽電池でこれらを満たすものはない。そこで、市販の太陽電池の材料として用いられるシリコン結晶と、新奇化合物半導体材料(GaAsPN結晶)を用いた新たな太陽電池構造を開発し、これまでに独自開発した転写技術と融合して上記1~3の条件を満たす太陽電池を実現することを目的とする。
助40-26
接合形成と機能発現を同時に成す半導体界面材料工学
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
異種材料の接合技術は、幅広い工学分野において要求される。特に、光・電子半導体素子の分野においては、低消費電力光通信・演算のためのオンチップ集積化発光・受光素子や、高発電効率を有する積層型ハイブリッド太陽電池等の実現に、高性能な接合技術が強く求められている。一方で近年、顕著な機械・光・電気的性質を示す単原子層材料や機能性固体・液体材料の進展が目覚しい。
②目的
界面材料に上記のような物質を採用することで、単一の作製工程にて高性能な接合形成と機能発現という一人二役のプロセスを提案するとともに、以下の二つの新規機能性接合技術を実現する。
1. 単原子層材料を介した半導体接合の開発および高性能光・電子デバイス構造の作製
2. 波長変換材料を介した接合とそれを利用した高効率多接合太陽電池の作製
1では、単原子層材料を活性層、接合される二つの半導体材料を電流の入出力や光閉じ込め用のクラッド層としたレーザや変調器等の超高性能光・電子素子を、2では、太陽光のうち各発電層の禁性帯幅に適した波長域の入射や発電層間の電流整合、また、光集積回路において光源層からの発光の接合された光導波路に最適な波長への変換のなされた高効率な太陽光発電や信号処理をもたらす。
助40-27
メタ表面を用いる光マネジメント科学の実践-蛍光の100%前方放出を目指して
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
白色LEDは青色LEDと、青色を吸収して黄色に光る蛍光体の組み合わせからなり、吸収されなかった青色と黄色の混色により白色を得る装置です。現在、より高輝度の照明応用に向け青色レーザダイオード(LD)を使った白色光源の開発が進んでいますが、青色LDは青色LEDに比べ直進性が強くハイパワーであるため、混色の問題(青色レーザが指向性をもって直進するのに対し、黄色蛍光は全方向に放たれるので均一な白色が得られない)が起こります。現状では青色レーザ光を散乱させて指向性を失わせて均一に混合した後、レンズやミラーなどの嵩高い光学系によって指向性を付与し使用しています。しかしながらこれは青色レーザの直進性を活かした解決策ではありません。他方ナノ光学分野で近年のトピックとなっているメタ表面は、高さ数百ナノメートルの平面構造で光を制御する新技術で、これを用いたレンズ(メタレンズ)やフィルタ(メタフィルタ)が開発されてきました。申請者はこの技術を白色光源に応用すべく研究を進め、黄色蛍光を垂直方向へ優先的に放つメタ表面と青色LDを組み合わせた“メタ表面蛍光体”を作製してきました。
②目的
現時点の課題として、まだ有効利用できていない蛍光成分があることが挙げられます。垂直方向で10倍の発光強度の増強を示す試料でさえ、蛍光基板内で発生した蛍光の50%程度しか前方に放てていません。残りの50%は後方に放たれるか、側方に逃げています。本研究では、これらをすべて前方に放つことでさらに蛍光強度を高め、高輝度・狭角配光の超小型非コヒーレント指向性点光源としての特性を評価することを目的とします。
助40-28
送受信回路系極低温組込み核磁気共鳴法による微小物質の高感度測定の開発と新奇物性探索
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
超高圧(270 GPa)の水素化物で超伝導転移点Tc = 288 Kという室温を超える高温超伝導体が2020年に発見された[1].鉄系物質においても超高圧下でTc ~60 Kに達する高温超伝導相が突如出現すること,超薄膜化によりTcが8Kから60 K以上にまで8倍も上昇するなど[2],Tcが劇的に上昇する高温超伝導現象が超高圧下や超薄膜で続々と報告されている.しかし,超高圧下や薄膜など超微小試料の実験の困難さから,その起源に迫る実験研究がほとんどない.原子スケールで動的な物性、揺らぎを検出できる核磁気共鳴 (NMR) 測定は超伝導機構の本質に迫る極めて重要な実験手法であるが,未だ行われていない.そのためTc向上の鍵となる超伝導機構は実験的に謎のままである.この機構が解明できれば、新しい原理の超伝導材料の探索の方向性が示され、室温超伝導体を応用した新しい超省エネルギーの未来が見えてくる。
②目的
超薄膜や超高圧下の実験が困難である最大の理由は,劇的に少ない試料の量にある.そこで本研究で、Tc向上の鍵となる超伝導機構の解明を目指し、微小物質に対して高感度・高解像度で測定を可能にするNMR実験の基盤技術開発に取り組む。具体的には、微小試料に伴う微弱NMR信号を検出するため、徹底的にノイズを抑制しながら信号強度の向上も図るアイデアとして,(1) 極低温に設置できる超小型プリアンプを開発し,(2) 薄膜試料に最も密着できる平面型コイルで感度増大を試みる.さらに、これら全てを極低温部に最短距離で組み込み、高感度・高解像度NMR実験の微小試料測定の限界に挑戦する.
助40-29
位相的データ解析による料理空間の構造解明とおいしい新料理の客観的な提案への応用
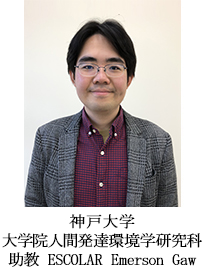 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
料理人が新しい料理を作る場合、通常は彼らのセンス、インスピレーションおよび経験から得られるアイディアをもとにして考案される。しかし、1人の料理人が考案できる料理の数には限界があり、その嗜好性には偏りが生じる。そのため、料理人の主観に頼らない客観的なアイディアの創出は、これまでにない食材・味付け・調理法の新たな組み合わせ(以下、新料理)の提案を容易にすると考えられる。我々は、既存の料理で用いられる食材や調理法のデータに位相的データ解析を適用することで、「料理空間」の構造を数学的に解明し、新料理をその空間の「穴」として特定できると考えた。位相的データ解析とは、対象データが持つ「穴」や「枝分かれ」といった構造や特徴を正確に捉える、適用範囲が広い解析手法である。例えば申請者はこれまでに、ガラス材料の構造解明や、企業の持つ技術の特徴を捉えるために本解析を応用してきた。本研究では、本解析が新料理の考案の客観的なアイディアを得るために有用であると予想している。なお、これまでにAI・ロボット技術・物理や化学の原理を調理の便利化や新しい調理法の提案に利用する試みはあるが、位相的データ解析を新料理提案に応用した例はない。
②目的
上述の背景をもとに、新料理のための客観的なアイディアの創出は料理人の新料理創作に資すると考え、本研究では、位相的データ解析を用いて既存の料理空間の構造を解明し、おいしい新料理の客観的な提案への応用を目指す。
助40-30
長波長側の可視光を利用可能にする螺旋型有機光触媒の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年の地球環境問題への世界的な取り組みとして「持続可能な開発目標(SDGs)」を目指した活動が活発に展開されており、有機合成化学の分野においても環境に対する負荷を軽減しうる新たな合成プロセスの開発が試みられている。可視光を光源とすることのできる光触媒反応はクリーンで持続可能な化学プロセスに応じる新戦略の1つであり注目を集めている。その一方で、現在報告されている光触媒反応は紫外領域に近くエネルギーの大きい短波長側の可視光である紫~青色光(波長380-490nm)を光源として使用しており低いエネルギー効率が課題となっている。太陽から地球に降り注ぐ光は長波長側の可視光が高い強度を有する波長域であることから、長波長側の波長領域の可視光を吸収することのできる光触媒を開発することは、効率的な太陽光エネルギーの活用に基づく持続可能な社会の実現のために欠かすことの出来ない研究課題である。
②目的
このような背景から、本研究では長波長側の可視光である赤色光(波長620-780nm)を光源として利用することの出来る新規螺旋型有機光触媒(TXTH)の開発を目標と有機EL材料合成への応用を目的とする。
助40-31
マルチモーダル分光計測による材料認識ペプチドの機能解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
無機固体材料の表面に特異的に吸着する材料認識ペプチドは、材料表面の電子特性や分子修飾性を改変・改質することが可能なため、バイオセンサーへの応用が近年盛んに行われている[Hayamizu et al., Sci. Rep., (2016)]。材料認識ペプチドと固体表面との相互作用を理解することは、バイオセンサーの多機能化や性能向上はもちろんのこと、生体1分子の生物学的振る舞いに関する基礎的な知見を得ることにも貢献する重要な研究である。しかしながら、これまでのペプチド–固体界面に関する研究は、材料表面上に形成する自己組織化構造の観察や、デバイスの電気特性の評価に集中しており、ペプチドの材料表面への吸着メカニズムを明らかにする試みは少ない。
ペプチドの材料表面への吸着機能の原理は、ペプチドの立体構造の変化(2次構造)と吸着するホスト材料の電子特性(バンドギャップ等)の局所的な変化の両方が重要であると予想されている。そのため、吸着機能の理解にはペプチドの化学構造とホスト材料の電子特性の両方の計測が必要不可欠である。生体分子の2次構造情報を1分子レベルで計測できる技術として、探針増強赤外分光法がある。この手法は、ナノメートルサイズの金属探針の先端に生じるナノ局在光で励起した分子の赤外吸収信号を計測する。同様の原理で、可視光で励起した分子のフォトルミネッセンスを検出することで、無機材料の電子特性は観察できる。したがって、フォトルミネッセンスと赤外吸収の両方を同時にナノ計測することで、吸着機能を支配する化学・電子特性を包括的に理解できる。しかしながら、これら2つの計測を共立するシステムは未だ実現できていない。その理由は、可視域と赤外領域の異なる波長領域の光信号を同時に検出するために、複雑な検出系を独立に必要とするからである。
②目的
本研究の目的は、フォトルミネッセンスと赤外吸収情報を同時にナノ計測できるマルチモーダル計測法を開発し、ペプチドの化学構造と無機材料の電子特性の相関を観察することで、材料認識ペプチドの吸着機構に新たな知見を与えることである。
助40-32
Si-CdTe一体型3次元半導体放射線イメージセンサの開発
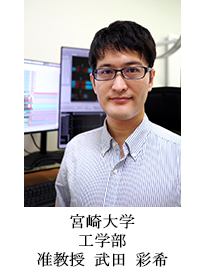 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
X線天文学は、アメリカ、ヨーロッパと並び日本が世界を牽引する分野のひとつである。これまで世界的にみて数多くの研究成果を挙げているが、それには優れた観測装置によるところが大きい。次世代の宇宙X線観測では、0.5−100 keVの広帯域な撮像分光が要求される。現在X線天文衛星の主力であるSiセンサは、高い撮像分光能力をもつが、現実的なエネルギー帯域は0.5−20 keVであり十分ではない。そこで、100 keV程度までのエネルギー帯域があるCdTeセンサをSiセンサの後段に配置(スタック)することで、広帯域な撮像分光を実現する。しかし、この形式ではSiセンサ・CdTeセンサを独立した基板に配置することになり、センサ間は最小4 mmの隙間ができる。このため焦点深度との兼ね合いで両者に対し同時に焦点を合わせることができない。つまり、ピンボケした画像となる。例えば、10 mの焦点距離では空間分解能が10秒角に制限される。また、Siセンサ・CdTeセンサは互いに独立するためシステムとして複雑になり、排熱や機械環境の成立性を難しくする。これらの課題を解決する方策として、Siセンサ・CdTeセンサを一体化した半導体イメージセンサが考えられる。一体化させることで焦点深度の制限が無くなり、システムとして単純化・小型化することができる。
②目的
本研究は、Siセンサ・CdTeセンサを一体化させた、これまでにない3次元半導体放射線イメージセンサを実現させることが目的である。軟X線(0.5-20 keV)のエネルギー帯域はSiセンサ、硬X線(20-100 keV)のエネルギー帯域はCdTeセンサで主に検出する。これにより、単一素子で0.5-100 keVのX線撮像分光が可能となる。本研究における具体的な開発項目は2点ある。1つ目は、次世代宇宙X線観測へ向け開発しているSiセンサ「イベント駆動型SOI-CMOSイメージセンサ」に対し、CdTeセンサ用の読み出し回路を組み込むことである。イベント駆動型SOI-CMOSイメージセンサは、Silicon-on-Insulator (SOI) 技術を基盤とする、Siセンサ・CMOS回路が一体化した放射線イメージセンサである。画素毎に放射線入射を感知する比較器回路を、またイメージセンサ内に独自開発したパターン処理回路を組み込むことで、放射線入射時のタイミング・入射位置・形状パターンの情報を出力する機能をもつ。本研究では、画素内に新たにCdTeセンサ用の読み出し回路を配置する。2つ目は、CdTeセンサ用読み出し回路を組み込んだイベント駆動型SOI-CMOSイメージセンサとCdTeセンサの接合である。イベント駆動型SOI-CMOSイメージセンサの回路側へ画素毎に配置した電極に対しマイクロバンプを用いてCdTeセンサを接合する。以上により、「Si-CdTe一体型3次元半導体放射線イメージセンサ」を試作し、動作試験を経て原理実証と技術的課題の洗い出しをする。
助40-33
伝搬型表面プラズモンを励起子と結合して発光として系外に取り出す技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
発光材料の励起子が金属の表面プラズモンと結合すると、発光の増強もしくは消光という両極端の効果を与える。発光の増強は、主に金属ナノ粒子の局在型プラズモンと励起子の共鳴効果によって起こる。他方、消光は、薄膜などのバルクの金属の伝搬型プラズモンに励起子のエネルギーが移動することによって起こる。 後者の効果は発光デバイスにおいて悪玉となる。この効果を抑えるために、たとえば有機ELでは、励起子と伝搬型プラズモンの結合を抑制するために分子配向の制御がなされている。つまり、発光デバイスの分野では伝搬型プラズモンによる消光を抑制するための研究が行われている。
②目的
励起子を消光する悪玉である伝搬型プラズモンを、発光の増強を生む善玉に変えるための研究を行う。伝搬型プラズモンが励起子を消光する原因は、プラズモンが励起子のエネルギーを吸収しつつ励起子のサイトから離れ去ってしまうことにある。そこで、伝搬型プラズモンを励起子の近傍に閉じ込める工夫を講じる。具体的には、金属薄膜と発光材料の薄膜を積層させたマイクロ共振器を開発し、伝搬型プラズモンによる発光の増幅に挑戦する。
助40-34
弾性偏光回折格子を用いた非メカ式レーザー偏向機の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
レーザー光を一次元もしくは二次元的に走査することを可能にするビームステアリングは,生体認証や高速3Dスキャナー,自動運転における障害物検知センサなどへの応用が期待されている。ビームステアリングはモーターや半導体微細加工により作製されたマイクロミラーを用いて機械的にビームの方向を制御するメカ式と,光音響効果をはじめとした媒体の屈折率・位相変調によってビームの方向を制御する非メカ式が知られている。メカ式は動作原理が明確で制御が容易である一方,非メカ式は構造が単純で小型軽量化が容易であるという利点を有する。非メカ式の中でも,偏光回折格子を用いた手法は,レーザー光を単一方向に回折できることに加え,円偏光を入力に用いることから反射光の分離が容易であるなどの利点を有し,精力的な研究が行われている。これまでに申請者らは軸選択的な光反応・光誘起配向・表面レリーフ格子の形成が可能な光配向性液晶ポリマーを用いて偏光回折格子を形成し、回折光の電気的スイッチングを実証した(crystals 2022, vol.12. 00273,図1)。これは偏光回折格子(図内LPG)に入射する光の偏光状態を,液晶セル(図内TNcell)の電場応答を利用してスイッチングさせることにより,偏光回折格子の回折方向をスイッチングする手法であり,多段化することにより高分解のスイッチングが可能となり,ビームステアリングへの応用が期待できる。しかし多段化は回折効率の低下や構造の複雑化を招くことから,より少ない素子を用いた連続的な回折角制御が望まれる。
②目的
以上の背景を元に,電場応答を利用した連続的な回折角変化が可能な偏光回折格子を,これまでの単純な延長である,多段化を用いることなく実現する。これまでに申請者らが報告してきた液晶高分子上に偏光回折格子を形成する技術を架橋高分子系に拡張し,電歪アクチュエーターの変形と連動した回折格子の弾性変形により,単純な電圧入力制御による連続的な回折角制御を実現する。
助40-35
デュアル光コムによる非接触リモート計測技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、カーボンニュートラルや脱炭素社会を実現するために、プラントや発電所、清掃工場などのエネルギー効率の改善や生産性の向上に対するニーズが高まっている。地球温暖化の原因物質と発生源を把握し適切な対策を組み合わせるとともに、工場エネルギー管理システムによるエネルギーの最適化と制御性の向上による省エネルギー化を進める必要がある。そのためには、センサーが不要な非接触リモートで簡便な装置による多成分ガスの種類や濃度の計測技術の創出が求められる。
プラントなどの煙突から排出されるガスを計測する従来技術としてガス分析計がある。ガス採取器を用いるサンプリング方式ガス分析計は、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)などの同時計測が可能である。しかし、ガス採取器とサンプリングモジュールを接続するための配管が必要となり、大型・複雑・高価という欠点がある。また、ガス採取器とサンプリングモジュールが物理的に離れているため、計測時間が長い。一方、レーザー方式ガス分析計は、半導体レーザー(LD)光源と受光器、および制御部で構成されており、非接触リモート・高速・小型・安価な計測装置が実現されている。しかし、一方、1台のLDにつき1種類のガス分子にしか対応できないため、多成分ガスの計測には複数のLD光源と受光器を用いる必要があり、大型・複雑・高価な計測装置となる。そのため、光・レーザーを用いた非接触リモート・高速・小型・簡便・低価格な多成分ガス計測技術を新たに開発する必要がある。
②目的
本研究では、高度レーザー技術である光コムを2台用いたデュアルコム分光法に基づく非接触リモートでの多成分ガスの計測技術を開発する。デュアルコム分光法では、2台の光コムのヘテロダイン検波を検出するため、単一の受光器と電子計測器による多成分ガス分子の高速・高精度な計測が可能である。本提案研究では、プラントなどへの設置導入を想定し、実用デュアルコム光源の小型・堅牢化を重要視した設計開発を行い、デュアルコム分光法を基本原理とした光コムガス分析計の実現を目指す。これにより、従来のガス計測技術における問題点を解決でき、カーボンニュートラル・脱炭素社会のへの配慮が必要な次世代産業に対し必要不可欠な技術になり得ると信じている。
助40-36
深層学習による遺伝子発現制御ネットワーク解析技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
生物・ゲノム科学の分野で私が所属した研究グループでは、ヒトや(研究に使われる)モデル生物の一種であるマウスの全遺伝子を集めるプロジェクト(完全長cDNAプロジェクト)が進められていた。マウスやヒトの様々な細胞から全遺伝子のクローニングと全長配列決定、遺伝子発現解析を行い、データベースで公開した(Okazaki Y,…, Osato N et al. Nature 2002)。この全遺伝子発現情報データベースから、胚性幹細胞(ES細胞)で発現している遺伝子を調べ、マウスiPS細胞の作成に必要な転写因子(遺伝子発現を制御するタンパク質および遺伝子で約1600種類存在する)の候補の絞り込みに使われ、実験の手間を減らし、幹細胞の機能をもつiPS細胞の発明に大きく貢献した。次の研究課題として、転写因子等による遺伝子の発現制御を理解し制御できれば、細胞分化のメカニズムの理解と制御や、遺伝子発現の異常による疾患の解明や治療法の開発などが期待される。
②目的
遺伝子発現制御のカスケードやネットワークを解析する手法を開発し、転写制御因子の発現量を変化させた時に、他の遺伝子の発現量がどのように変化するかを、遺伝子間の発現制御の相互作用を考慮して、定量的に予測できるようにする。遺伝子ネットワーク予測のための条件検討を行い、予測精度を向上し、遺伝子ネットワークに含まれる遺伝子発現制御の関係を予測し解明する。
助40-37
双方向ワイヤレス電力伝送のオンライン磁気パラメータ同定による高効率制御に関する研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、カーボンニュートラルの実現に向けて、自動車の電動化や再生可能エネルギーの普及が推進されている[1]。再生可能エネルギーは発電量が時間や気候によって大きく変動するため、発電した電気を蓄える蓄電システムが必要不可欠となる。そこで、台数の増加が見込まれる電動車を系統に連携し、「動く蓄電池」として活用する技術が国を挙げて推進されている[1]。
電動車は、バッテリの性能限界による航続距離の短さや充電時間の長さが課題であり、解決策の一つにワイヤレス電力伝送(WPT: Wireless Power Transfer/Transmission)がある。WPTは電動車の走行/停止中に無線給電を行う技術で、バッテリ容量の補填という点で注目されている[2]。
WPTは既に様々な機関において研究・実証が進められているが、多くが「系統→電動車」という一方向の給電のみを想定している[3]。しかし、上述した系統連系型電気自動車の実現には、「電動車→系統」という逆方向の電力の流れにも対応可能なシステムが不可欠である。そこで本研究課題では、双方向の給電が可能であるWPTシステムの実証と高性能化に取り組む。
[1] 経済産業省,「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を策定しました」,https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005.html(2022年5月10日)
[2] NEDO,「グリーンイノベーション基金事業」,https://www.nedo.go.jp/activities/green-innovation.html(2022年5月10日)
[3] H. T. Nguyen et al., IEEE Trans. Power Electron., Vol. 37, No. 4, 2022
②目的
双方向WPTシステムにおいて、センサ情報から磁気パラメータを正確に同定し、同定情報を利用した高効率制御法を提案する。
助40-38
高輝度円偏光発光材料創出を志向したキラルヘテロカーボンナノベルト開発とキロプティカル特性の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
円偏光発光(CPL: Circularly Polarized Luminescence)は,高輝度液晶ディスプレイ用の偏光光源をはじめ,3Dディスプレイ,セキュリティーペイント,光通信などの高度な光利用法が期待されている.そのため,優れた有機CPL材料の開発は,学術的にも産業的にも要請が高く,その分子設計の確立は重要な課題である.最近,高輝度CPLの実現には「剛直なキラル筒状構造」が重要であることが報告された(H. Isobe et al. PNAS 2017).この構造的要請から,芳香環が筒状に縮環したキラルベルト状分子(キラルナノベルト)はさらに剛直であり,魅力的な標的分子と期待される.さらに,そのベンゼン環の一部を他のヘテロ原子で置き換えたキラルヘテロナノベルトでは,立体構造および電子状態が変化し,特異な光物性の発現が期待される.しかし,高度な歪みを有するナノベルトの合成自体が極めて挑戦的であり,量的供給と物性解明が困難である.その解決には,まず,ヘテロナノベルトの効率的合成法の開発が求められる.
最近,申請者は,カルバゾール誘導体1に三臭化ホウ素およびルチジンを反応させることで,1の求電子的ホウ素化が進行し,ホウ素化体2が高収率で得られることを見出した(Chem. Lett. 2022).本手法は高度な歪みを有する分子も合成できることから,高度な歪みを有するヘテロナノベルトの高効率的合成も可能であると着想した.
②目的
カルバゾール誘導体の求電子的ホウ素化を利用して,巻き方向キラリティーを有するナノベルト(キラルヘテロナノベルト)を開発する.キラルナノベルトにおけるCPLなどのキロプティカル特性を解明し,高輝度CPL材料開発に挑戦する.
助40-39
脳-計算機-超音波閉ループによるてんかん発作の実時間制御
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
てんかんやアルツハイマー病などの神経疾患、うつ病や依存症などの精神疾患はしばしば薬物抵抗性である。これらの脳疾患は脳の働き方の障害であるためその症状制御には、ウェアラブル医療機器等を介した脳刺激で疾患症状を司る脳活動に直接介入して脳内神経細胞の活動操作することで、脳の働き方を整える戦略が効果的である。脳刺激による脳活動介入は、正常生理機能を司る脳活動の阻害回避による副作用減少のため、必要な際にのみオンデマンドに刺激を行うことが重要である。そのためには脳活動を常にモニターし、病態脳活動へオンデマンドに介入するウェアラブル・埋め込み医療機器の開発が必要である。脳活動のモニター・刺激介入をオンデマンドに行うウェアラブル医療機器により、神経・精神疾患を克服した社会の実現が求められている。
②目的
脳活動のモニターおよびオンデマンド介入を行うシステムにより神経・精神疾患症状を克服した社会を目指し、申請者はこれまでにてんかんを題材に、発作が生じるや否や脳深部を直ちに電気刺激することで発作を終息する“閉ループ脳深部刺激法”を開発した(Takeuchi Y and Berényi A, Neurosci Res 2020; Takeuchi Y et al, Brain 2021; Takeuchi Y et al, Front Neural Circuits 2021)。さらに非侵襲的かつ効率的な電気刺激法“経頭蓋集束電気刺激法”を開発した(Vöröslakos M, Takeuchi Y et al, Nat Commun 2018)。現在当該2技術の応用により、薬剤抵抗性てんかんの発作制御が可能というデータを得ており、てんかん患者を対象にした臨床研究を行なっている(https://neunos.com/)。しかしながら、閉ループ脳深部刺激法には刺激電極を侵襲的に脳実質に刺入する必要がある、経頭蓋集束電気刺激法には刺激焦点の空間解像度が低く脳深部刺激も困難である、という点がそれぞれ課題であった。そこで申請者は生体を透過する超音波を用いた神経活動操作法に着目した(竹内、関、Clinical Neurosci 2022)。超音波は既に生体イメージングは結石破砕などで臨床応用されている安全なモダリティーであるうえ、刺激の時空間解像度が高く、超微小刺激素子の開発により超音波刺激のためのウェアラブル機器実装も可能になる。
助40-40
ジュニアスポーツにおける主観的運動強度によるトレーニング負荷定量化の妥当性と障害との関連性の検討
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
生涯スポーツの普及やアスリートの強化において、外傷・傷害の予防やそのための知識は必要不可欠である。特にジュニア期 (小学生~中学生) における体づくりの時点で練習量を適切にコントロールし、外傷・傷害をいかに減らせるかが重要である。しかしながら、小学生からの時点で外傷・障害の発生は非常に多く、陸上やクロカンの全国大会に出場している選手では4割以上が外傷・傷害 (疲労骨折や肉離れなど) を経験していることが報告されている (日本陸上競技連盟. 2019)。また、この外傷・傷害の発生率は練習を週4日以上行うことで、週3日以内の練習よりも高くなることが報告されていることからも (日本陸上競技連盟. 2019)、普段の練習 (トレーニング) 負荷を適切にコントロールし、外傷・傷害を減らすことができるかが重要である。
トレーニング負荷の間接的な評価として、トレーニング時の主観的運動強度 (1~10段階で運動のきつさを測る指標) と運動時間の積によって負荷を定量する方法が用いられている (Foster. 1998)。この方法により定量化したトレーニング負荷は心拍数や走行距離などで定量化した客観的なトレーニング負荷と相関することからその妥当性が認められている (中垣. 2014; Takegami et al. 2021)。しかしながら、このような主観的運動強度により算出したトレーニング負荷の評価は成人を対象としており (Busso et al. 1994; Foster. 1988; Suzuki et al. 2004; Takegami et al. 2021)、ジュニアスポーツにおいて主観的運動強度を用いてトレーニング負荷を評価したもの、その評価した負荷を活動計などを用いて客観的に評価した負荷と比較し妥当性を検討した研究もない。さらに、主観的運動強度などで評価したトレーニング負荷と、身体 (脚など) の疼痛程度や全身の慢性的な疲労度、ストレス指標などの関連性を評価した研究もない。
②目的
ジュニアスポーツにおける主観的運動強度を用いたトレーニング負荷定量化の妥当性と障害との関連性の検討
助40-41
生体電気インピーダンス法を用いて骨格筋の量と質を評価するための電気的パラメータの検討
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
骨格筋の減少と栄養不良は、罹患率の増加、入院期間の延長、機能的能力の低下、多額の医療費、死亡率の増加など臨床集団における複数の有害な結果と関連している。近年、生体電気インピーダンスから得られる生体電気インピーダンス値、位相角をはじめとする生体パラメータが臨床集団における栄養状態の代替バイオマーカーとして使用されることへの関心が高まっている。
位相角の研究から得られた知見をさらに発展させたものとして、生体電気インピーダンスベクトル解析(BIVA)法がある。古典的なBIVA法と最近提案された特異的BIVA法はレジスタンスとリアクタンス、そして派生する変数の位相角とベクトル長(主にレジスタンスに起因するインピーダンス)を方程式が無くても、単独で解析するので、身体組成に関するより正確な情報を得ることができる。
しかしながら、生体電気インピーダンス法で使用される周波数は、50kHz以下の低周波であれば細胞内を通さず、対して高周波であれば細胞内を通すが、高すぎると生体情報を得るための適切な値とはならないという特徴がある。そのため、若年層やアスリートかといったヒトの集団の特徴により、電気インピーダンス値ひいては身体組成結果が影響を受ける可能性があることが報告されている。これまでに、生体が大きく変化する成長期の若年層やアスリートにおいて、どの周波数が最も適切な生体電気インピーダンス値や位相角を求めるポイントであるかは明らかになっていない。対象者の身体特性に応じて、どの周波数が最も適切であるかを明らかにするには、身体組成評価を行う数々の方法(磁気共鳴画像 (MRI)法、二重エネルギーX線吸収 (DXA)法、コンピューター断面画像(CT)法など)を使用した骨格筋「量」としての評価と筋力測定を行う骨格筋の「質」としての評価の視点から、複合的に評価する必要がある。
②目的
本研究は生体電気インピーダンス法を用いて得られる、電気インピーダンス値と位相角の適切な周波数のパラメータを活動的な若年層を対象として明らかにすることを目的とする。
助40-42
自動ヒト培養幹細胞動態解析による再生医療支援システムの構築
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
培養幹細胞を用いた再生医療が様々な疾患に対して応用されようとしている。しかしながら、発展途上にある培養幹細胞による治療は、幹細胞移植後の治療成果を予測できるほどの精度にはなく、熟練の細胞培養技術者による直感、いわば暗黙知によって、治療に最適な幹細胞が選別され、その治療が行われているのが現状である。ヒト表皮幹細胞を培養することで得られる培養表皮シートは、すでに臨床応用されており、多くの重度熱傷患者を救ってきた。しかしながら、その治療効果の決定要因である表皮シートの製造過程は細胞培養技術者の熟練度に大きく依存している。このことも要因の一部となって、実際に移植された培養表皮シートが正常に表皮として機能する割合は50~60%と低く、また培養表皮シートの製造プロセスに予測不能な要因が多いため、移植を待つ間に患者の約半数が死亡する。このような現状は、培養中の幹細胞の状態に関する情報と、最終的に形成される培養表皮シートの品質に関する情報、さらに移植後の治療効果に関する情報が全く乖離しており、再生医療システムの中に組み込まれていないことが原因の一つである。皮膚の再生医療だけでなく、今後の幹細胞を用いた再生医療をさらに前進させるには、これらの情報を統合した治療効果予測技術の開発、及び、そのフィードバックによる治療成績の向上が不可欠である。
②目的
本研究は、申請者らが独自に開発した自動細胞動態追跡システム (Hirose et al, Stem Cells 2021)を培養ヒト表皮幹細胞に応用し、細胞動態データを最終的な医療の成果(移植後の生体組織の状態)と紐付けすることで、移植が成功しやすい培養幹細胞の状態を明確にし、実際の治療に活かす再生医療支援システムを構築することを目的とする。
助40-43
MR(Mixed Reality:複合現実)を用いた気管支鏡支援
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
AR(Augmented Reality:拡張現実)やMR(Mixed Reality:複合現実)などのxR(Cross Reality)は現実世界と仮想世界を融合させ現実にはないものを知覚できる技術である。HoloLens2 (Microsoft)などのHead-mounted display (HMD)を使って現実空間で仮想の体験をしたり、遠隔地から仮想空間を通して現実空間の人に指示を与えたり共同作業をすることができる。xRは医療分野においても教育、医療者間のコミュニケーション、遠隔医療などにおいて広く活用が期待されており、いくつかのコンテンツがすでに実用化されている。気管支鏡は肺癌など呼吸器疾患の診断や治療に必須の内視鏡的手技であるが、その習得にはモデルを用いたシミュレーショントレーニングやエキスパートによる技術指導が欠かせない。しかしながら指導する医師は慢性的に不足しており、その教育方法も個人差がある。また、近年はCOVID-19の世界的流行に伴い直接対面を必要としない遠隔からの教育や技術支援の必要性がさらに増している。
②目的
本究の目的は、MRを用いて気管支鏡の教育・指導を支援する方法を開発することである。さらに大きく2つの目的に分けられ、一つ目は、HoloLens2の MR情報によるリアルタイムガイダンスを活用した教育用気管支鏡シミュレーションの開発・教育現場への実装と、二つ目は遠隔地からエキスパートがMRを活用して気管支鏡の支援を行う遠隔指導の実現可能性評価である。
助40-44
小児てんかん発作の頻度と気圧変動の統計的相関を調べる研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
てんかんは発作そのものの心身へのダメージだけでなく、発作の予測不能性が患者の生活制限を強くし、患者や家族の心理的ストレスを増大させる (Fisher Epilepsy Behav. 2000)。小児てんかん患者の10人に1人が、少なくとも1回以上、発作を契機に溺水や眼外傷などの重篤な外傷や事故を経験すると言われている (Camfield C, et al. Seizure. 2015。発作出現を予測することは、重大な合併事象を回避させることを可能にする。近年、気圧・気象の変動が、てんかん発作を増加させることが成人てんかん患者においては明らかにされているが、小児てんかん患者においては明らかになっていない。小児期には、発熱で発作が誘発される「熱性けいれん」、過換気で発作が誘発される「小児欠神てんかん」が多いことから、小児てんかん発作は何らかの機会によって誘発される傾向にあり、仮説としては、気圧・気象変動も成人に比べより明らかな発作誘発因子になると推測する。
②目的
我々は、小児のてんかん発作と気象・気候の関連性を明らかにするために、多施設共同前向き疫学調査を行う。また、睡眠不足、疲労、感冒などの既知の発作誘発因子を含めた気象・気候の関連についての詳細な分析も行い、小児のてんかん発作の高精度予測モデルを開発することを最終目標とする。
助40-45
パーキンソン病患者における頸部多チャンネル表面筋電図による嚥下動態の解析と電気刺激による効果の検討
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
パーキンソン病は運動緩慢、筋強剛、振戦を主症状とする有病率の高い神経変性疾患(国内の患者数が15万~20万人)で、その多様な症状のため生理学的評価やリハビリ介入が非常に難しい。特に嚥下障害の機序は複雑で、誤嚥性肺炎のリスクが高く死因の第一位である。
リハビリにおいて、生理学的な評価は極めて重要である。その中で、近年研究が進んでいる『多チャンネル表面筋電図』に着目した。通常の表面筋電図は、皮膚に一対の電極を貼付して神経筋の電気活動を検出する方法で、被検筋全体の振幅、周波数を計測することになる。『多チャンネル表面筋電図』は、一枚の貼付シートに60~120個程度の電極が高密度に埋め込まれており、振幅、周波数のみならず、複数のチャンネルに渡り伝播するように発生する電位の筋活動線維伝導速度を抽出することができ、個々の筋活動の特徴や構成、変動を調べることができる。すなわち、運動単位レベルでの筋活動評価や筋収縮メカニズムを明らかにすることが可能となる。特に神経疾患を中心とした疾病の生理学特徴を詳細に把握することができ、有用なリハビリ手法の探索にもつながりうる。
これまで当施設では、パーキンソン病患者の大腿四頭筋において『多チャンネル表面筋電図』での検討をおこなっている。その背景として、パーキンソン病モデルラットに対して筋内筋電図法(針筋電図)を用いて運動単位の発火頻度を調べた結果、正常ラットと比較して有意に運動単位の発火頻度が少ないという研究結果がある(Barghi E et al., Int J Mol Cell Med, 2013, 72-79)。そこで、当施設ではパーキンソン病患者を対象として持続的な筋収縮中の筋活動分布パターンを健常者と比較し、疾患特異的な筋活動パターンを多チャンネル表面筋電図法により明らかにした(Nishikawa Y et al., J Electromyogr Kinesiol, 2017, 125-131)。具体的にはパーキンソン病患者は健常高齢者と比較して持続的な筋収縮時の筋活動は一部の筋線維に限局していることが視覚的に確認でき、疾患特異的な筋活動の評価ツールとして多チャンネル表面筋電図法の有用性が示された。
しかし、これまで神経疾患の嚥下障害において電気生理学的検討が行われた研究はほとんどなく、今回『多チャンネル表面筋電図』を用いて検討することを着想した。
②目的
今回、パーキンソン病患者を対象に、『舌骨上筋群(頸部筋)』の『多チャンネル表面筋電図』を行うこととした。これは国内外で初めての試みであり、パーキンソン病の嚥下動態を新たな手法で電気生理学的に解明するのが目的、ねらいである。あわせて頸部電気刺激のリハビリ介入を8週間行い前後の比較をする。評価には、嚥下造影(時相解析含む)、1%クエン酸咳テスト、舌圧、カフピークフローの評価もあわせて実施し、既存の嚥下評価と対応させることでより詳細にパーキンソン病の嚥下動態を評価する。
助40-46
CEST-MRIと機械学習を組み込んだ定量的pHイメージング手法の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
Amide proton transfer(APT)イメージングを代表とするchemical exchange saturation transfer(CEST)イメージングは,核磁気共鳴画像(magnetic resonance image:MRI)診断装置を利用して,可動性タンパク・ペプチド内のアミド基やヒドロキシル基のプロトンが周囲のバルク水と水交換されているために,その濃度や交換速度に基づくコントラストを得ることが可能である.最初にCESTイメージングを用いたpHに起因すると提唱した手法(Zhou J, Nature Med. 2003)では,ラット脳の生体と剖検による過去の文献値から算出している.ヒトを対象にしたとき,また異なる組織を想定したときに,Zhouらの手法によって算出したpHは直接的に求めているとは言えない.また,MR spectroscopyにおいてもpHの測定は行われているが,多くの場合造影剤を投与する必要があり,その造影剤物質のキレートの影響を受けるので,生体の静的なpH変化を捉えることはできない.
②目的
本研究は,MRIを用いて,生体内組織のpHを定量的に可視化するために,内因性CESTイメージング手法と機械学習を組み込んだpHキャリブレーションの手法を開発する.単に信号を取得する従来手法とは異なり,物理的および科学的な数値を算出し,機械学習により精度を向上させることで,生体内組織のダイナミックな物性を評価することを目指す.
そのためには,次の(A)(B)(C)の項目に焦点を当て開発を行う.
(A)ファントム物質の安定性とpHダイナミックレンジの検討.
(B)CESTイメージングの撮像条件によるpHの変化.
(C)pHキャリブレーションと機械学習を適応したCESTイメージングの可視化プログラムの開発(pHイメージング).
助40-47
人工知能および距離センサーを用いた次世代手術トレーニングシステムの開発
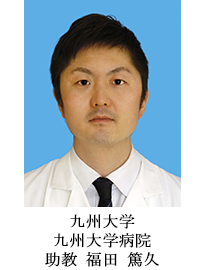 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
若手外科医にとって、内視鏡手術のトレーニングは重要課題である。我々のグループでは様々な疾患を模した疾患特異的手術シミュレータを開発し、三次元磁気式計測技術などを併用することで手術技術を客観的に評価可能なシステムを開発し報告してきた。更に、同モデルを用いた継続的手術トレーニングにおける学習効果を検証し成果を得た。しかしながら実臨床では「見て学ぶ」、「慣れて学ぶ」といった主観的かつ経験的指導が行われているのが現状である。
技術の担保は「医療安全」に関わり、「医療安全」は常に社会問題のトピックスとして注目され、内視鏡外科手術による医療事故が社会問題になっている現代において、安全な内視鏡外科医療を安定的に供給できる教育環境の構築が求められる。
②目的
本研究は我々が開発してきた技術定量評価システムを備えた内視鏡外科シミュレータを応用し、人工知能(AI: Artificial Intelligence)および距離センサを用いることで内視鏡手術下での縫合手技を定量化し、客観的なトレーニングシステムを構築するものである。安全な内視鏡手術を遂行する上で確実な鉗子操作および愛護的な組織の取り扱いが重要であり、次世代外科医教育システムを構築する上のメリットは大変大きい。本研究の実現によって、これまで行われてきた生体動物を犠牲とするトレーニングや臨床ベースのトレーニングに代わる新たな教育環境を実現することが目的である。
助40-48
タイピングスキルを支える手指運動制御則の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
タイピングは現代社会における重要な日常生活タスクであり,その作業効率によって生産性が左右される.速くて正確にタイピングを行うためにヒトがどのような運動制御則に基づいて指を動かしているかを明らかにすることは,安全で効率的なタイピングの学習に向けた運動学的根拠に基づくアプローチの確立に貢献し得る.
ヒトの運動制御の研究はこれまで,複数筋の協調構造を表す筋シナジー解析(Bernstein 1996)や単一筋内の運動単位の協調構造を分析し,動作の安定性を評価する手法(Madarshahian & Latash, 2022)をはじめ,収縮要素である筋の協調機能から運動の規則性が導かれてきた.しかし,関節の安定化や力伝達には靭帯や腱などの非収縮要素も寄与し,動作速度や正確さに影響する.これらは筋による制御コストを低減するが,非収縮要素の構造特性を包含した運動制御に迫る研究はこれまでない.
②目的
非収縮要素である靭帯や腱の構造特性を包含した運動の規則性を評価する指標を確立し,この指標に基づいてタッピングやタイピングの手指運動を評価する.これによって筋に焦点を当てた既存の制御則にはない新たな制御則を導き,手指運動スキルの習熟を加速させる基盤データとする.
助40-49
殺菌レーザーとバクテリオファージを融合した狙撃分子の創成
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のみならず、Clostridioides difficile 感染症(CDI)もその治療に苦戦している。CDI は、C. difficileが原因で引き起こされる難治性の下痢症・腸炎であり、死に至ることもある。CDI の治療には抗菌薬が用いられるが、抗菌薬では、C. difficileのみを特異的に死滅させることは困難であり、腸内の有益な微生物(細菌、真菌、ウイルスなど)までも死滅させる。最近、その微生物の消失により、様々な疾患(認知症、心筋梗塞、肝癌など)を引き起こすことが報告されている。従って、C. difficile を特異的に死滅させることが治療の“鍵”を握る。
②目的
申請者らは、 C. difficileのみ特異的に殺菌する手法を開発するために、バクテリオファージ(ファージ)に着目した。ファージは、自然環境などに生息しており、特定の細菌にのみ結合する。その特異性は、ファージ尾部が重要な役割を担っている。一方で、申請者らが着目した蛍光プローブIR700 は、近赤外光を殺菌レーザーに変換することで、様々な病原体(C. difficile、新型コロナウイルスなど)に強い殺菌活性を示す。申請者らは、これまでの研究成果(PNAS, 2012; Nat. Med., 2011; Nature, 2010; PNAS, 2005)により、これらを融合させた新しい“狙撃分子”を考案した。狙撃分子を用いることで、標的となる微生物のみを特異的に狙撃(スナイプ)することから、“スナイプ法”と名称する。本研究テーマでは、狙撃分子を利用し腸内微生物叢を乱さないスナイプ法を検証する。
助40-50
慢性疼痛患者に対するストレス評価方法の開発と生活習慣病のリスク判定への応用
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
慢性疼痛患者にとっての痛みは,存在そのものがストレスとなり不安などの心理的影響を受け,生活の質(quality of life; QOL)を低下させる.そしてこのようなストレス状態は,更なる痛みの悪化要因となりうると考えられている.臨床において「痛み」は,主観的な感覚であることから客観的な評価が難しく,慢性疼痛患者への治療効果の判定は主観的な患者の評価でなされているのが一般的である.近年,慢性疼痛の原因や客観的評価についての脳機能研究が多数報告されている.その中で,慢性疼痛の一つである腰痛の重要な因子として背外側前頭前野(dorsolateral prefrontal cortex; DLPFC)が関与しているという内容が注目されている.
②目的
本研究の目的は,痛みによるストレスを患者自身が計測・管理する評価システムを確立することである.そのためには,血圧測定と同様に,簡便かつ短時間で(安価に)測定可能であり,評価の妥当性が十分である必要がある.そこで,NIRS(Near-Infrared Spectroscopy)で計測したデータと,痛みの主観的な評価8種類の質問紙(厚生労働省慢性の痛み研究班参加31大学・医療機関共通)との関連性を調査することで,評価法の確立と妥当性の検討を実施する.
助40-51
皮膚表面形状の計測方式の差が手の動作認識の精度に及ぼす影響についての検証
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
生体信号に基づく手の動作認識は様々な分野における入力インタフェース(電動義手,外骨格ロボットアシスト,VR)に適用されている.表面筋電位は最も一般的に用いられる生体信号であり,随意的な筋肉の収縮を反映し,非侵襲なセンシングで人間の動作意図を取得できる. 前述の通り,表面筋電位は随意的な筋収縮に対応しているため,動作意図に機敏に反応できる高い応答性を有する.しかし,一定の入力を維持したい場合は筋肉の収縮を常に維持する必要があることに加え,人体の生理的な反応における微細な電気信号を皮膚表面で取得しているため,筋肉の疲労や汗などによって信号が変化してしまう.また,筋肉の収縮のみを反映しているため,日常生活中において重要な動作の一つである前腕の回内外で生じるような大きな骨の変位などの活動は取得できない.
これらの問題点を受け,表面筋電位以外の生体信号で人間の動作意図を取得すべく,動作によって生じる皮膚表面形状の変化を計測する手法が提案されている.皮膚表面形状は,力センサ,距離センサ,歪みセンサなど様々な計測方式で取得され動作認識に応用されており,表面筋電位と比較しても豊富な運動情報を含むことが先行研究より確認されている.この皮膚表面形状は皮膚の機械的な変形を計測しているため,筋肉の収縮に加え関節運動に伴う筋肉の変形,腱の伸長,骨の変位などの多くの体組織活動が含まれている.多くの先行研究において,皮膚表面形状は表面筋電位と比較され,動作認識の精度などをもって,それぞれの信号の特徴・得手不得手が議論されている.
しかし,皮膚表面形状の計測方式の違いによる認識精度の差について比較・議論されている論文は少ない.特定の計測方式内で,センサの数や計測部位を変化させ精度を比較する研究はあるものの,同一のセンサ数で同一の計測部位を対象とした異なる計測方式間の精度比較はなされていない.
②目的
本研究の目的は,皮膚表面形状の計測方式の差が手の動作認識の精度に与える影響を検証することである.様々な計測方式(力,距離,歪みセンサなど)で皮膚表面形状を取得し,動作認識の精度や特徴空間における動作ごとの分布を比較することにより,差の有無を検証する.前述の通り皮膚表面形状には多くの体組織活動が含まれるため,センサごとの特性の違いにより計測される皮膚表面形状に差異が生まれるのか,その特徴の差によって動作ごとの推定精度が変化するのかといった議論は,皮膚表面形状に含まれる体組織活動に対する理解を深める助けになると考えられる.
助40-52
寒冷誘発性血管収縮の新規メカニズム解明-塩素イオンチャネルTMEM16Aに着目して-
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
私たちが寒冷に曝されたときには皮膚血管収縮反応が生じ、この反応が不十分である場合には低体温症、過剰に生じる場合には冷え性やレイノー症候群と呼ばれる末梢の皮膚血管障害に陥るため、ヒトの皮膚血管収縮反応のメカニズムを解明することは健康な日々の生活には必要不可欠である。これまで、皮膚血管収縮には交感神経調節が強く関与していることが報告されてきたが (Stephens et al. 2004; Pérgola et al. 1993)、その他のメカニズムは明らかになっておらず、冷え性やレイノー症候群の発生メカニズムの解明には至っていない。そのため、申請者らは皮膚血管収縮に関する新規メカニズムの解明に取り組んできた (Arnold et al. 2020; Fujimoto et al. ARIHHP Forum 2022)。
近年、塩素イオンの透過やニューロンでのシグナル伝達など多数の生理機能に関わる塩素イオンチャネルTMEM16Aの構造解明が進み (Paulino et al. 2017)、さらに、血管収縮反応に関連している可能性がTMEM16A阻害剤や を用いた動物実験において報告されつつある (Cil et al. 2021; Leo et al. 2021)。しかしながら、ヒトの皮膚血管収縮に対する塩素イオンチャネルTMEM16Aの関連については検討されておらず、明らかでない。
②目的
本研究では、ヒト皮内マイクロダイアリシス法を用いて、塩素イオンチャネルTMEM16Aが寒冷暴露時に生じる皮膚血管収縮に及ぼす影響を明らかにし、ヒトの皮膚血管収縮に関する新規メカニズムの解明を目指す。
助40-53
緑内障治療に向けた微弱電流刺激による眼球の若返り
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
“緑内障”は中途失明原因第一位の疾患で、世界では1億人近くが罹患しているといわれ、予防や根治の方法が未だ見つかっていない。網膜神経節細胞からなる視神経が傷害され、加齢に伴い増加する。眼球内の圧力(眼圧)が緑内障の主な原因で、近年増加しているといわれる高眼圧を伴わない正常眼圧緑内障も原因が不明なことが多く減圧抑制が主な対処療法となる。進行が遅く自覚症状が少ないため、気づいた時には悪化している場合が多く、高齢化に伴い新たな予防方法や検査方法の開発および治療法の開発が重要な課題になっている。
眼圧も約24時間周期の概日リズムがあり、我々は交感神経と副腎皮質グルココルチコイド(GC)の時間情報により調節されていることを発見した(Ikegami et al., IOVS 2020; Ikegami and Masubuchi, Commun Biol 2022)。眼圧は毛様体からの眼房水の産生と線維柱帯からの排出のバランスで生み出されているが、加齢に伴いそれらの調節機能は低下し、眼圧が上昇しやすく、視神経も障害されやすくなる。緑内障は生活習慣や加齢と非常に密接に関係しており、夜型社会や高齢化に伴い今後増加すると考えられる。夜間シフトワーカーでは眼圧リズムが消失し、眼圧リズムの消失と視神経障害との関連性が近年報告された(Neroev et al., Int J Mol Sci 2021)。さらに、加齢とともに緑内障発症リスクは高まるが、加齢とともに眼圧概日リズムと内分泌リズムの脱同期といった概日リズム異常も報告されている(Mansouri et al., IOVS 2012)。これらから、我々は外的環境の調整で加齢に伴う眼圧リズムの乱れや視神経障害といった老化を抑制または若返り効果が期待できるのではないかと考えた。再生誘導や細胞活性化の外的刺激の一つに微弱電気刺激が知られているが、微弱電流刺激は筋再生を加速させたり、神経の軸索伸長を促したりする(Liu et al. Alzheimer's Research & Therapy 2020)ことが知られている。
②目的
しかし、微弱電流の検出により眼圧を測定するコンタクトレンズ(SEED社製など)はすでに開発されているが、微弱電流刺激により眼圧を制御したり、眼球リズムを整えたり、神経で構成されている網膜の視神経障害を抑制できるかは分かっていない。そこで本研究ではマウス眼球や網膜組織、初代培養細胞を用いて微弱電流刺激により眼房水産生排出部位の機能が亢進し、眼圧リズムの乱れが改善され網膜神経節細胞(視神経)の細胞死が抑制または若返るかを検証する。
助40-54
柔道の初心者における頭部外傷を予防する安全な大外刈りの構築
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
【柔道の頭部外傷】日本の中学校・高校の柔道の部活動において、1983~2011年に73名が頭部外傷で亡くなっており、大外刈りで投げられて死亡するケースが多いと指摘されている(内田、2013)。その後、全日本柔道連盟の安全対策によって、2012~2014年の死亡事故は0件となったが、2015~2020年に急性硬膜下血腫等が10件、脳震盪が11件報告されている。2021年には重篤な頭部外傷はなく、7件の脳震盪が報告されている(全日本柔道連盟、2022)。コロナウィルスによる活動自粛が影響しているために、重篤な頭部外傷が発生しなかったと推測される。一方、海外では、近年の頭部外傷の報告は皆無に近いが、今後の頭部外傷の発生が十分に考えられる。
【問題の所在】日本では、人やダミー人形を投げる実験において、大外刈りによる頭部外傷の危険性を検証した研究が非常に多く(Ishikawa et al, 2018,Koshida et al, 2017, 2019;Murayama et al, 2019, 2020)、海外でも同様の研究が行われている(Vacca et al,2020)。Hayashi et al(2019)やIshikawa et al(2020)は、外力が付与された際の反応が頭部外傷に影響を及ぼすことを示唆し、頭部外傷の発生要因の解明に取り組んでいる。研究全体として、どのような大外刈りの投げ方が頭部外傷の危険を高めるのか、どのような投げ方が安全であるかは解明されていない。そのため大外刈りを掛ける者が注意すべき具体的な安全対策が講じられていない。
②目的
【課題】以下の3つの課題を設定した。
(1)頭部外傷の危険が高まる大外刈りの投げ方を検証する。
(2)頭部外傷を防ぐ安全な大外刈りの投げ方を検証する。
(3)前述の2つの大外刈りの投げ方を比較し、頭部外傷を防ぐ安全な大外刈りの効果を実証する。
【ねらい】本研究の目的は、頭部外傷の危険が高まる大外刈りの投げ方を解明し、頭部外傷を防ぐ安全な大外刈りの投げ方を提言することである。
助40-55
腱の三次元培養技術と力学的収縮を組み合わせた抗運動器治療戦略
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高齢化を迎えている我が国では、加齢に伴う肥満・糖尿病などの「代謝疾患」だけでなく、筋萎縮症・骨粗鬆症などの「運動器疾患」への対策が健康寿命の延伸を図る上で喫緊の課題となっている。この対策として、「運動療法」が効果的であることは疑いようない事実である。その一方で、これらの取り組みは殆どが代謝疾患などの克服に向けた治療を目指しており、比較的強度の高い運動が求められている (Tsuchiya et al, Metabolism 2015)。このため、筋量や骨量の減少により運動器に悩みを抱える高齢女性などは、代謝疾患克服のための運動さえ実施困難な状況にあり、結局、効果の現れにくい低用量の運動を繰り返さざるを得ない現状にある。この現状を物語るように、様々な治療対策が講じられてきているものの、筋萎縮症・骨粗鬆症の罹患率はいずれも増加しており (平成 30 年国民健康・栄養調査)、決定的な解決には至っていない。
②目的
課題は、加齢性筋萎縮により効果の低い運動を繰り返さざる得ない高齢者、特に女性ホルモンが激減する高齢女性などが運動効果を得ることなく「運動不足-虚弱-QOL低下の悪循環」に陥ることにある。この背景には、既存の研究の多くが代謝疾患に対する効果を独立して検討している問題点が挙げられる。そこで申請者はこの悪循環を断ち切るべく、「腱」のもつ臓器間コミュニケーションを活かした治療戦略に着目した。国内外の研究機関では、幹細胞からの腱分化や組織再生に注力しており、腱の臓器連関能に繋がる研究データはみられない。本研究では上述の命題を解決すべく、閉経後に著しく萎縮する筋量や衰退する筋再生能を腱特異的な進展刺激により維持・改善することをねらいとする。
助40-56
光操作技術による適切な行動を生み出すtop-down入力の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
突然、部屋から焦げ臭さを感じた時には、とっさに火元や匂い源を確認する。しかし、家族の誰かが料理をしているような状況(文脈)であれば、同じ匂いを感じてもそのような行動はとらない。このような、文脈に基づき感覚入力を行動出力に正しく結びつけるための脳の神経回路の働きは、動物の生存においてきわめて重要である。しかし、末梢からの感覚情報が文脈に応じた意味を持つためには、高次領域からの情報と統合されなければならないが、どこでどのように情報統合が行われるのかはほとんど不明である。これまで感覚入力と高次領域からの入力の統合は、比較的高次の情報処理段階で行われると考えられてきた(Miller et al., 2005)。しかし、情報処理が高次な段階へ進めば進むほど、感覚情報の持つ意味が不明瞭となるという問題があった。
②目的
そこで申請者は、嗅覚系に注目することで、その問題を回避できると考えた。嗅覚は五感の中で唯一、感覚受容器からの入力が、視床を経由せずに、一次中枢の嗅球から二次中枢の嗅皮質へ最短でわずか2つの神経細胞を介するだけで到達するというシンプルな解剖学的構造をもつ。さらに、嗅皮質は、嗅球からの匂い入力を受けるだけでなく、適切な行動を取るために必要な文脈情報を担う高次領域からの入力を受けるventral tenia tecta(vTT)という亜領域が存在する。申請者は、これまでの研究でvTTの個々の神経細胞が、文脈に依存した様々な行動状態に対して応答することを明らかにした。さらにこれまでに、mPFCを中心とした回路で文脈情報が作られていることもわかっている(Hyman et al., 2012)。それらのことから、嗅球からの入力とmPFCからの入力の両方を受けるvTTは、感覚情報と文脈情報を統合する重要な場であることが容易に想像できる。そこで本研究は、文脈に応じて感覚情報を正しい行動に結びつける神経メカニズムを明らかにするために、末梢からの感覚情報と高次領域からの文脈情報がvTTで統合され、行動につながるための神経回路を解明することをめざす。
助40-57
加速器ホウ素中性子捕捉療法におけるデータ駆動型アプローチによる全身被曝線量の予測
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ホウ素中性子捕捉療法(Boron Neutron Capture Therapy: BNCT)は,原子炉等から照射される中性子と,中性子に増感効果のあるホウ素薬剤との反応を利用し,腫瘍細胞のみを選択的に破壊する治療法である.我が国では世界に先駆けてBNCTのプロジェクトが進行し,近年では原子炉に替わり病院に設置可能な加速器BNCTシステムが国内の病院に導入され,次世代放射線治療法として期待されている.申請者の所属機関では,産学共同で開発されたBNCT治療システムNeuCure®が設置されており,2020年6月に切除不能な局所進行および局所再発の頭頸部癌が保険診療となった.また,再発高悪性度髄膜腫に対するBNCTが第Ⅱ相臨床試験として実施されており,今後様々な臓器への適応拡大が期待される.
一方,加速器BNCTでは中性子のみならず,照射野内外からγ線が発生することが知られ,全被曝線量の多くを占める1.また,患者の全身状態や照射部位に応じて,患者設定体位が様々であるために,患者毎に全身被曝線量は異なると考えられる.そのため,BNCTを施行する全患者に対して,線量計を複数部位に貼り付けて治療中の被ばく線量をオフラインで測定している.しかし,その手技が煩雑かつ多大な時間を要するため,抜本的な改善策が求められている.
参考文献:1. T Tukamoto, et al., Appl Radiat Isot, 2011;69;1830-1833.
②目的
本研究の目的は,加速器BNCTにおける全身被曝に影響を与える因子を解明し,さらに患者個別の被曝線量予測モデルを構築することである.具体的には,データ駆動型アプローチの中核を成す機械学習アルゴリズムを活用して,BNCTに係るパラメータを入力因子とし,高精度に被曝線量を予測する.最終的には,患者個別に行っている被曝線量測定の省力化を目指し,更には本研究より得られる知見に基づき,被曝線量を低減するような治療計画の立案方法を確立する.
助40-58
末梢神経刺激が静的ストレッチングの柔軟性向上効果に与える影響とその神経機序
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ストレッチングは関節の可動域を広げ、柔軟性を向上させる。関節の柔軟性はスポーツ競技者の身体運動パフォーマンスの決定因子になることに加え、スポーツ傷害の発生リスクとも関連する。そのため、身体の各関節の柔軟性を向上させるストレッチングに関する知見は、子どもから高齢者まで人間の健康や身体機能を維持・向上させるために重要である。
最も代表的なストレッチング法は、静的ストレッチングである。静的ストレッチングは長座体前屈のように、関節可動域の限界まで筋を伸ばし、数十秒間その姿勢を維持する。これを繰り返し行うことで、関節可動域の拡大が期待できる。近年では、効果的に柔軟性を向上させるストレッチング法が提案されている。例えば、固有受容性神経筋促進法(PNFストレッチング)は、ストレッチングの対象となる骨格筋を意図的に収縮や弛緩させることで、可動域の限界近くまでのストレッチングを実現させる。申請者は、末梢神経刺激を用いてストレッチングの対象となる骨格筋を弛緩させてストレッチング効果を高める研究に取り組んだ。その結果、骨格筋を弛緩させる神経活動の増減に関係なく、末梢神経に電気刺激することによってストレッチング効果の改善が見られた。この研究結果から、『末梢神経刺激による感覚神経活動の増大が静的ストレッチング効果を促進させたのでは?』と考え、本研究計画の着想に至った。
②目的
本研究の目的は、末梢神経刺激で誘起した感覚神経活動がストレッチングの柔軟性向上効果に与える影響を明らかにすることである。ストレッチング効果を高める神経メカニズムを特定し、従来のストレッチング法を刷新することが本研究の最終目標である。
助40-59
変貌する日本の食文化-はじまりの米と魚の食文化から再考する-
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
海で囲まれた日本列島の食文化は、「米と魚」を基本としてきた。その食文化は、弥生時代に稲作農耕が導入され、縄文時代以来の魚食文化と融和したことで、日本独自の「米と魚食」の食文化が醸成され、和食へと昇華されていった。
しかし、近年、日本の「米と魚」の食文化は、衰退の一途を辿っている。昭和から平成にかけて生鮮魚介類購入量は約3割減少している一方で、国民の食に対する健康・安全志向は高まり、魚食への関心も非常に高い。そこには、経済性・簡便性を求めた肉食傾向の拡大と健康・安全性を求めた魚食への期待が認められるが、長引く不況により、肉に比べ高価格帯である魚への十分な回帰は無く、結果として魚食が減り、日本独自の魚食文化は衰退しつつある。同様に、米の消費量も主に欧米やアジアなど様々な食文化の普及により、減少の一途をたどる。その結果、日本の食文化が消えつつある状況にある。だが、米と魚は食糧安全保障の要でもあり、日本の風土に適した「米と魚」の食文化を守ることは、多様化する食習慣のなかで、守るべき大切な文化である。
②目的
そこで、本研究では現代日本に繋がる「米と魚」の食文化の開始期である弥生時代の魚食文化を解明することを目指す。そして、「米と魚」の食文化について、根源的な見直しを推し進め、次世代へと継承していくモデルを構築する。
助40-60
森林伐採と気候変動の飲み水のアクセスへの影響:高解像度衛星データとGPS付き人口健康調査による分析
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景および目的
国連によれば、2020年において、世界人口の26%が清潔な水にアクセスできていない(SDG 6)。この問題を考えるうえで、しばし議論されるのが森林伐採と安全な飲み水へのアクセスへの関係である。
興味深いことに、森林面積と安全な飲み水へのアクセスへの影響に関しては、これまで環境学や水文学の中では否定的な議論がなされてきた。例えば、Filoso S, Bezerra MO, Weiss KCB, Palmer MAらは、306の文献をサーベイし、森林面積の増加は、水源での水量を減少させると結論づけている。この直感に反する研究結果は、森林自体が水を消費しその水を空気中に排出するためと、先行研究において説明されている。
このような森林伐採と水へのアクセスに関する先行研究の定説に対して、申請者は、水源における水量の物理的増加は、消費可能な水の増加を意味しないと議論してきた。これまでの環境学および水文学での先行研究は、森林部分の面積と水源での水量の関係を物理的な側面から分析したものである。しかしながら、水源における物理的水量が増加したとしても、世帯の安全な水へのアクセスが増加するとは限らない。その増加が水質の減少によってもたらされているならば、消費者は安全な水にアクセスできない可能性がある。
以上のような理由から、準備研究として、申請者とその学生のMapulangaは家計に直接サーベイを行っている人口家計調査と高解像度衛星画像を使って、森林伐採と安全な飲み水へのアクセスへの関係を統計的に解析した。具体的にはアフリカで森林伐採が問題になっているマラウィに注目し、マラウィでの森林伐採が家計の安全な飲み水へのアクセスにどのような影響を与えるかを分析した。その結果、1%ポイントの森林面積の減少は、安全な水へのアクセスを1.3%ポイント減少させることを発見した。これは、当該国で過去20%ポイント森林面積が減少していることを考えると、安全な水へのアクセスが26%ポイント減少することを意味する。著者らのこの準備研究の結果は、Nature, Scienceに次いで世界的に最も権威が高いと言われている全米科学アカデミー紀要に出版されている(Mapulanga and Naito (2019))。
助40-61
感染症予防難易度の高い社会福祉施設における環境特徴量抽出と空気質管理方法に関する研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
これまで,我々の研究グループでは,COVID-19の感染拡大防止に関する東京都,京都府など自治体との連携により,飲食店・音楽会場・医療/介護施設向けの換気方法について調査,研究を行い,結果をプレプリント6本(現在,論文投稿中)で発表するとともに,一般の方々にも理解が容易な「実践!換気対策ガイドブック」にまとめて配布する活動をおこなってきた.それらの内容は,感染が沈静化しつつある現在(2022年5月),ポストコロナ社会の形成に貢献している.ところが,特殊な環境であるがゆえに,通常管理が難しい場所が置き去りになりつつある.
代表的なものの一つに保育施設がある.クラスター発生時には保護者も休業を強いられるなど社会的インパクトが大きい施設である一方で,乳幼児の安全確保のため部屋の構造が特殊である,近隣への配慮から窓開による換気が憚られる,食事や昼寝などマスクを外さざるを得ない場面が多いなど,感染症対策が難しい.
このように,社会的に重要な社会福祉施設ほど,感染対策が難しいにも関わらず予防策に関する議論,研究から取り残されている場所が多く,事業者のリソースを圧迫する社会課題となっている.
②目的
エアロゾル感染に関する対策が難しく,かつクラスター発生時の社会的インパクトが大きい社会福祉施設における感染症予防のための空気質管理方法を,実際にCOVID-19のクラスターが発生した現場におけるCO2センサーなどIoTデバイスを用いた環境分析とモニタリング,機械学習による特徴量抽出と感染症拡大リスクの定量化,発生状況に関する疫学的調査と因果推論を通じて明らかにし,管理すべき特性と管理手法について明らかにする.それらの結果を学術論文として公開するとともに,社会福祉施設向けのガイドブックに編集し,広く配布して啓蒙を図る.
助40-62
小中学生のハイリスクなネット利用行動に及ぼす規定因の研究:個人レベルと学校レベルの分析
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
今日、小中学生(以下、子ども)でもスマートフォンやタブレット、ゲーム機器などを用いてインターネット(以下、ネット)を利用し、ネット上のコミュニケーションに対するハードルが下がっている。見知らぬ相手とも簡単にSNS等でコミュニケーションをとり、その結果、犯罪被害(性被害、誘拐など)にあう事件も起きている。しかしこのような現象が議論の俎上には上がってはいるものの、ハイリスク行動をとる子どもを対象とした実証研究はほとんど行われていない。またネット依存についての研究は非常に多く行われているが、ネット上で見知らぬ人とコミュニケーションをとり、実際に会うといったハイリスク行動についての学術研究はほとんど行われていない。申請者は、これまでハイリスク行動をとる子どもの特徴を明らかにするための調査研究を行い、地域を問わず2%程度はネットで知り合った見知らぬ人と実際に会うという非常にリスクの高い行動の経験をもつ子どもがいること、それらの子どもたちは孤独感が強く居場所感が低いこと、まわりにサポートされている感覚が低いことを報告している(鈴木・中山, 2021, 2022予定)。
②目的
本研究では、申請者の先行研究をふまえて子どものネット上のハイリスク行動(以下、ハイリスク行動)を規定する要因について、子どもを取り巻く環境、とりわけ学校との関係に焦点づけて検討する。近年のGIGAスクール構想やコロナ禍の影響により、学校からタブレット端末が配布され、配布された端末を利用して、オンラインゲームやSNSを利用し、これがハイリスク行動につながっていると推察される。本研究では、子どもの個人特性に加えて、学校での情報教育やICT利用の方針を調査し、ハイリスク行動への影響を検証する。これをふまえて情報教育やICT利用のあり方についても考察し提言する。
助40-63
学校数学における生徒が確率的に推論する授業の理論的・実証的研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
確率的に推論することは,すべての市民が日常にある不確実性を考慮して意思決定を行うために,また,ビジネス,医療,政治,法律,心理学などの様々な専門的分野においてサンプリングや推測を行うために必要である。確率的推論とは,次の4つの段階で構成される推論である。
[1] 自然,技術,社会におけるランダムな事象を特定する。
[2] そのような事象の条件を分析し,適切なモデル化の仮定を導き出す。
[3] 確率的状況に対する数学的モデルを構築し,そのモデルから様々なシナリオや結果を探索する。
[4] 確率・統計の数学的手法と手続きを応用する。
日常的な例では,COVID-19の検査結果の解釈に確率的推論が利用されている。専門的な例では,インターネット検索システムであるGoogleのWWWページのランク付けに確率的推論が利用されている(本村, 2003)。このように私たちにとって確率的推論は身近で必要な推論であることから,学校数学(中学校・高等学校の数学)には,すべての生徒に対して確率的推論を身につけさせることが要請されている (Batanero et al., 2016)。
しかしながら,「学校で教わる確率というのは,…(略)…数学を展開する意味では重要だが,世の中での生活や仕事には,直接役に立つとは言えないものなのだ」(小島, 2013, pp.32–33) や,「確率は,学校で学ぶだけの無味乾燥な技術的なことがらでは決してない」(マンクテロウ, 2015, p.1) などのように,現在の国内外の学校数学における確率の授業は,学校卒業後の生活や仕事に役立っていないと批判されている。実際に,私たちは学校数学で確率を学習したにもかかわらず,社会に出てからは確率的に推論することが苦手であることが,認知心理学や行動経済学の研究によって明らかにされている。このような背景から,生徒が確率的推論を身につけることができる授業の在り方を明らかにすることは,学校数学の確率に関する研究において喫緊の課題である。
②目的
以上より本研究の目的は,次の3つである。
(1) 生徒が確率的に推論する授業をデザインする。
(2) デザインした授業を高等学校で実施していただき,その有効性を検証する。
(3) (2) の結果から,生徒が確率的に推論する授業が具備すべき条件を明らかにする。
助40-64
個別最適な学びと協働的な学びの一体化を目指したプログラミング教育における学習プロセス評価手法の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
令和の日本型学校教育(中央教育審議会,2021)では「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実が求められている.一方で小学校では,プログラミング教育が2020年に開始され,かつGIGAスクール構想(文部科学省2019)によって一人一台端末を活用した実践が進められている.両者を踏まえると,プログラミング教育における個別最適な学びと協働的な学びを一体的に引き起こすことで,学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した取り組みが求められているといえる.具体的には,児童生徒個人がプログラムを作成しつつ,他者との共有や対話の中でより良いプログラムを創造していくような過程が想定される.指導と評価の一体化の観点では,児童生徒の評定を付けるために行う「評価」とともに,教師が次の授業改善に活かすための,子供の学びのプロセスをとらえるような「評価」が求められているといえる.
プログラミング教育の領域では,正解の決まったプログラム(本研究ではこれを正解モデルと呼ぶ)を速く正確に記述できることだけでなく,自らゴールを設定しそのゴールへ自ら接近したり,ゴールをより高い目標へと設定し直したりする創造的な活動が注目されている(Resnick, 2017).正解モデルによる研究では,ある問題を与えた際に,その問題を解くために最適な手続きと比較することで,学習者の操作が速く正確だったかが評価されている(小林・太田・長谷川,2022).一方で,創造的なプログラミングでは,正解が学習者によって異なるため,各学習者のプログラミングについて共通する「不適切な手続き」の定義は困難である.また,不適切な手続きのデータが未蓄積のため,AI(教師あり学習)を用いて不適切な手続きを自動抽出することも不可能である.
②目的
本研究では,創造的なプログラミング実践場面における「不適切な手続き」に着目し,それを「バグ」と同定してアノテーションすることで,その学習プロセスにおける特徴を顕在化させる評価手法の開発を目指す.具体的には以下の2つの実践を実施する.一つは,小学生が一人でプログラミングを実施する場面を対象とし,バグがどのように起きているかのデータを収集する.もう一つは,小学生および大学生を対象として,一人でプログラミング課題を実施したのちに,ペアで話し合い活動を実施し,その後再び一人でプログラミング課題を実施する中でのバグのデータを収集する.これらのデータ分析を通じて,創造的なプログラミング活動遂行時に発生するバグの傾向や種類を同定し,教育方法の改善に活かすとともに評価手法について検討する.
助40-65
幼児期の「サウンド・エデュケーション」を支援するアプリケーションの開発と検証
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
カナダの作曲家マリー・シェーファー(1992)の著書『サウンド・エデュケーション』は、日本の音楽教育に「音を聴く」という行為の重要性を啓発し普及した(阪井2011)。幼児期の子どもを対象に『サウンド・エデュケーション』を実施した研究については、今川(2006)の実践研究や、吉永(2012)の音感受の研究等で知見が示されており、日本の幼稚園・保育園・認定こども園においても様々な「音を聴く」ことに関連した報告を確認することができる。他方、「音を聴く」こととも密接に関わる「音楽をつくる」活動については、幼児期の子どもを対象とした音楽づくりでは坪能ら(2005)による2004年から続く実践研究の蓄積や、「応答性」に着目した駒(2013)の研究が挙げられる一方、現時点で多くの研究が為されているとは言い難く、その研究の多くは小学生以上の子どもを対象としている。さらに、日本の小学生以上の年齢において対象となる教科「音楽」では、教科の目的を達成するためにコンピューターやタブレット等のICTの利点を活用した音楽づくり・創作の授業事例も見ることができる。音楽科においてICTを活用する教育的価値については、時得ら(2011)による、音や音楽が空間に響いた後に消えて無くなってしまう特性によって生じる子どもの「知覚」「感受」「価値判断」の3つの段階を支援するためにICTが有効であると示した研究や、サンプリング手法に焦点をあてた創作活動におけるアプリケーションの教育的意義を検討した木下ら(2018)の研究が挙げられる。こういったアプリケーション利活用の知見が幼児期の音楽表現に援用可能な一方、幼児の「音を聴く」「音をつくる」ことを目的にアプリケーションを活用した先行研究は、菅見の限りでは確認できない。
②目的
本研究では、ICTのもつ「音の記録」の機能に着目して次の2点の課題を達成することを目的とする。1つ目は、複数の幼児が協同的に身のまわりの音に耳をすましながら、音を記録・操作して音響作品をつくり、それを幼児自身が振り返り聴取するといった「サウンド・エデュケーション」を支援するアプリケーションを開発することである。そして2つ目はそのアプリケーションを搭載したタブレットを用いた音を聴く活動・音楽づくりを幼稚園で実践し、幼児の行動や音への興味関心等の分析を通じて、ICT活用によって幼児の協同的・能動的な音楽づくりに与える影響を実証し、保育の質の向上を音楽経験の視点から目指すことである。
助40-66
自閉スペクトラム症児を支援する大学生に対するヒデュン・カリキュラムの効果
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
将来,自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:以下,ASD)児を援助する職に就くことを志望する大学生は,学外のボランティアに積極的に参加する。学内の授業では身に付け難い実践的な知識やスキル修得のためである。しかし,学外のボランティアでASD児と関わる体験を得ることができても,関わりの困難さを解決するスーパービジョンが脆弱であり,大学生は悩みや困り感を抱え易い(土居,2012)。そこで,有為な人材育成には,ASD児と実際に関わる体験を得て,その場でフィードバックを受ける教育プログラムが必要になる。このような教育プログラムは,国家資格等を取得する特別なカリキュラムを除くと,大学での単位化にはいくつかのハードルがある。この点を解決するために,海外の医学教育システムでは,ヒデュン・カリキュラム(Hidden Curriculum)と呼ばれ,一定の歴史がある手法を用いている。それは,正課外で行われ,大学生の専門能力の開発に強力な影響を与える学習形態の一型をなしている(Neve & Collett, 2017)。以上をふまえ,本研究では対人援助職を志望する大学生への臨床発達心理領域のヒデュン・カリキュラムを開発する。
②目的
本研究では,将来ASD児への対人援助職を志望する大学生を対象として,臨床発達心理領域のヒデュン・カリキュラムを開発することをねらいとする。そのため,以下の2点を課題として解決する。
1.大学生がASD児の行動変容を引き起こす上で必要な専門能力(知識とスキル)を促進する教育プログラムを作成,効果検証を行う。
2.1.の教育プログラムで,大学生の専門能力を高める要因を同定する。
助40-67
障害者福祉拠点における利用/支援実態と拠点間連携の研究-共生型地域包括ケアシステムの構築を目指して-
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景(内外における該当分野の動向)
我が国では戦後の人口増加時代に高齢者福祉と障害者福祉の仕組みがつくられ,各分野に専門特化する形で支援やケア体制が構築された。2000年代には各分野で介護保険法/障害者自立支援法が施行され,措置から契約へとサービス体系が切り替わり,施設収容から住み慣れた地域での生活支援/ケアへと方針が転換された。現在,高齢者福祉では重度の要介護状態でも住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられる「地域包括ケアシステム」の構築が進められている。しかし人口減少で物的・人的資源が縮減するこれからの社会で地域密着型の支援/ケア体制を持続するには,両分野を広義の福祉として捉え直し,障害者福祉の施設や事業所等(以下,拠点)もまた地域資源として組み入れる「共生型地域包括ケアシステム」として再構築し,高齢/障碍/疾病等で何らかの支援やケアが必要な人たちを包摂する必要がある。
②目的
本研究では「共生型地域包括ケアシステム」構築に資する知見を得ることをねらいに,まずは幼児期〜高齢期にかけて多様な支援サービスが提供される障害者福祉の拠点での利用/支援実態と拠点間連携を明らかにすることを目的とする。地域での拠点間連携による障碍当事者への支援実態と,総合的な支援拠点となる施設での地域生活移行や地域生活支援の実態の解明を本研究課題に設定する。
助40-68
移民第二世代のオートエスノグラフィー
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
日本で移民が急増してから30年以上が経過し、日本育ちの移民二世が研究者になっている。しかし、日本では在日コリアンを除けば移民は研究の客体であり続けており、移民による移民研究の発信には至っていない。移民による研究の困難は、大きく2つの要因による。第1に、高階層出身者が支配的な研究者の世界で、ブルーカラー層出身が多い第二世代には、「民族」「階級」の不利がのしかかる。
第2に、不利を克服したとしても、主流パラダイムへの同化により自己疎外が生じてしまう。第二世代研究者は、既存のパラダイムを用いて論文を書くに際して、自らを含む移民集団を一人称ではなく、三人称で(=他者として)呼ぶこととなる。業績主義に適応することで、他者(主流のパラダイム)の枠組みでしか自己を語りえなくなるという意味で、オリエンタリズムと同型の問題が発生する。
これらは、第二世代研究者自身だけでなく、日本の移民研究全体にとっても大きな損失をもたらしてきた。マジョリティ視点を前提とした主流の研究は、移民を統合の客体とみなし、移民側の視点は軽視されている。
②目的
では、日本のニューカマー移民第二世代は、どうすれば当事者ならではの研究発信を行えるのか。そこで用いるのがオートエスノグラフィーという研究手法である。これは、自伝(autobiography)と民族誌(ethnography)を掛け合わせた造語で、著者自身の経験を記述し体系的に分析する手法を指す。代表者以外全員が日本で教育を受けた第二世代の研究者からなるチームにより、『移民第二世代のオートエスノグラフィー』という書籍を刊行し、当事者を担い手とする新たな研究潮流を作り出すことが、本研究の目的となる。
助40-69
デジタル時代におけるヒト固有なコミュニケーション方策の変化予測
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
三菱総合研究所が昨年出版した『スリーエックス 革新的なテクノロジーとコミュニティがもたらす未来』では、来るべき100億人・100歳時代の社会をより豊かに迎え、かつ、国連「持続可能な開発目標」で宣言された「だれ一人取り残さない」社会を実現するための方策として、「革新的な技術」と「新しい人のつながり」の確保が重要であるとの提言がなされている。DX化が叫ばれ高度に情報化・デジタル化されつつある昨今の潮流は経済的な豊かさを増強させるものではあるが、技術革新のみを押し出した「なりゆきの未来」では、本来アナログな生き物であるはずの人間の、人間らしさや人間性の喪失につながることが懸念され、心の豊かさの存在が脅かされている。コンピュータが登場する以前の世界では、人々はオンラインではなく実際に会って会話し、表情や声色といったアナログ情報をもとにした情緒的なコミュニケーションを介することでこれが緩衝材の役割を果たし、価値観の異なる他者や集団とも親和的に意見を調整し、互いに融和的な信頼関係を構築してきた。
しかしながらオンライン変革期である現代のコロナ禍事情や、より情報化が加速することが見込まれる未来の社会においては、人々はスマートフォンなどのデジタル媒体や購買情報などのデジタル記録によって極限まで個人化され、個人個人で多様ではあれど互いに交わることのない、他者不信と怒りに支配された社会が構築されつつある。事実、Twitterを始めとしたSNS上ではすでに利用者のクラスター化(自己が選好する意見にしか耳を傾けない)と異なるクラスターへの過剰な攻撃や誹謗中傷が繰り広げられており、他者や外集団への無関心や無理解という形で、デジタル化の弊害が表出し始めている。
したがって、「加速度的に進展する高度なデジタル社会やそれを後押しするデジタル技術」と、「心の豊かさが担保された中でのつながりの維持」の両立は喫緊の課題であり、特に後者に表される、“人間本来のコミュニケーション”の持続可能性向上を目指す新たなコミュニケーション様式の模索と、そのための社会基盤の整備が不可欠となる。
②目的
デジタル時代におけるコミュニケーション方策の変化予測と、アナログ時代に享受されていたメリットの持続的維持のため、本研究では以下の3つの目的を掲げる。
A:生物学的ヒトが元々どのようなコミュニケーションを形成しているのか、動物や機械の特徴と比較する比較認知科学的見地から、ヒト固有な行動特徴を明らかにする
B:上記ヒト固有な行動特徴が、デジタル社会の中ではどのように変容すると見込まれるのか、予測して未来の社会構造のあり方を描く
C:アナログからデジタルへの移行で削ぎ落される要素について、移行後も維持するための施策を提案する。
助40-70
熟練の情報科教師に見られる「翻案」の特徴の解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高等学校の必履修教科である共通教科情報(以下「情報科」と呼称)は、2022年度から初の必履修科目「情報Ⅰ」が設置され、統計学やプログラミングなど学習内容が高度化する。また2025年度から、大学入学共通テストに「情報」が加わる。このような状況の中、充実した授業展開に向けて、情報科教師の専門性の向上が期待されている。
一方、様々な学習内容の指導に「自信がない」や「あまり自信がない」と回答する情報科教師が一定数いること(文部科学省 2017)や、情報科の専任が不足していること(中山ほか 2017)などの課題がある。こうした先行研究は、情報科教師の専門性の向上を目的とした研修の充実を指摘することに帰結する。しかし、そもそも情報科教師の専門性とは何か、という具体性が検討されてこなかった。
②目的
教師は、教育的推論と行為の過程で学習する(Shulman 1987)。つまり、まず教科内容や教科書を「理解」し、生徒の特性を踏まえてそれらの内容を教材へと「翻案」する。そして、実際に授業で「指導」し、生徒を「評価」する。その後、これらの活動を「省察」し、「新しい理解」を得る。
教科ごとに学習内容が異なることを踏まえると、各教科の教師の専門性は、特にこの過程の「翻案」周辺から検討できると考えらえる。そこで本研究では、情報科教師の専門性の一側面として「翻案」の特徴を明らかにすることをねらいとする。また、このねらいの達成に向けて、以下の課題を設定する。
課題:熟練の情報科教師への学習指導案作成に関するインタビューと授業観察を通して、情報科の教科内容をもとに教材や指導案を作成する方法を、明らかにする。
