受領者紹介
特別テーマ
助38-01
無電極プラズマ推進機による革新的スペースデブリ除去技術の確立
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
宇宙事業の多様化・活性化が進む中、スペースデブリ(宇宙ゴミ)の問題が深刻化し、小型のものも含めると50万個以上あるとされている。地球規模の環境問題であるとの認識が国際的に認知され、デブリの除去技術の開発が喫緊の課題であるとされている。デブリを除去するためには、地球を周回するデブリを減速することで高度を下げ、大気圏突入による燃焼で処理する必要があるが、その明確な方式の開発には至っていない。デブリの減速を実現するためには、周回速度と逆向きの運動量(または力)をデブリへと外部から照射する必要がある。化学推進機または電気推進機により燃料を高速噴射しデブリの減速を図った際には、衛星には逆向きの推力が働き、デブリとの距離を一定に保つことが原理的に不可能である。したがってデブリと逆方向にも運動量を放出し、衛星に加わる推力および速度の制御を同時に実現する必要がある。欧州では、イオンエンジン2台を用いたデブリ除去法が提案され検討が進められている一方で、申請者らによって、数kW以上の大電力動作が可能である無電極プラズマ推進機を用いた、搭載推進システム1台でデブリ減速と衛星速度制御が可能な革新的方式が提案されてきた。
②目的
上記研究背景を踏まえて、本研究では申請者が世界をリードして開発を進めてきた磁気ノズルおよび高周波プラズマ生成法を活用した無電極プラズマ推進機を基盤技術とした、推進機1台でデブリの減速と自己推進機能を兼ね備えた双方向加速・制御型の革新的電気推進システムの高性能化と動作原理の理解を進め、大型デブリを除去可能な推進性能(推力約30-50mN、比推力2000秒、動作電力3-5kW)を室内実験で得ることを目的とする。
助38-02
マイクロ流体デバイスによる環境中マイクロ・ナノプラスチック検出技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
マイクロプラスチックは、海洋を始めとした環境中に存在するマイクロメートルサイズの微小なプラスチック粒子であり、それ自体の蓄積はもちろんのこと、PCBなどの有害物質を吸着する性質を有することから、環境及び生体への潜在的影響の検証が喫緊の課題となっている。しかしながら、現状では300µmの目合いの網で回収後、手作業により取り出してFT-IRと色素染色による光学顕微鏡観察を行って同定していることから、300µm以下のマイクロ・ナノプラスチックの存在量が過小評価されており、分析手法の効率化と標準化も求められている。
②目的
本研究では、特に300µm以下のマイクロ・ナノプラスチックを簡便・迅速かつ正確に定性的・定量的に解析できる分析手法を確立し、マイクロ・ナノプラスチック分析手法の効率化と標準化を達成することを目的とする。将来的には、オンサイトで計測可能なデバイスを構築し、地球環境が抱えるマイクロプラスチック問題解決に向けた計測デバイスの開発を目標とする。
基本テーマ2
助38-03
テーラーメイド修飾酵素によるマイクロプラスチック分解技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
地球の美しい海洋環境を保全するには、深刻さを増すマイクロプラスチック問題を解決する技術が必要である。機能性と利便性の高い高分子材料から構成されるプラスチックは、2017年に世界で4億トンが生産されており、廃棄ごみや洗濯排水による拡散によって海洋汚染の原因になっている。この問題解決に向けて、生物の力を利用したマイクロプラスチックの分解技術は、環境保護や省エネルギーの観点からも特に期待されている。ポリエステルの分解菌をはじめ、生物が持つ分解酵素を活用したプラスチック分解技術は、いずれも有望であるが、以前、分解速度は十分でなく、分解酵素の能力を最大限向上するための技術が求められている。
②目的
マイクロプラスチックを効率的に酵素分解するためには、酵素がプラスチックの疎水性表面に円滑に吸着する必要がある。本提案では、親水性の高い分解酵素に、疎水性のマイクロプラスチックの表面に吸着する能力を付与するために、精密かつ簡便に疎水性分子を化学修飾したテーラーメイド酵素を作製し、酵素応用によるマイクロプラスチック分解技術を開拓する。本提案者が独自に開発した、選択性が高く、世界で最も簡便なタンパク質N末端技術を活用して、ターゲットとした酵素に対して、部位特異的に合成分子や脂質などの天然の疎水性分子を連結した分解酵素クチナーゼを作製し、プラスチックであるポリエチレンテレフタラート(PET)への吸着能力と分解能力の向上に取り組む。
助38-04
ワイル半金属ヘテロ界面における非従来型磁気メモリ効果の実証
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:革新的スピントロニクス材料としてのワイル半金属への期待
固体の性質がバンド構造のトポロジーによって特徴づけられるトポロジカル物質群は、トポロジカル絶縁体の発見以降、理論予測に先導される形で、様々な新物質・機能を生み出してきた。特に、ワイル半金属は、固体全体がスピン分裂した線形分散バンドを有することが理論提案されている。これは、(実在しないが)二次元層状物質グラフェンが三次元化かつハーフメタル化した異常物質に相当する。さらに、線形分散バンドが交差するワイル点は、波数空間で仮想磁気モノポールとして振る舞い、巨大異常ホール効果などの素子機能を創発することから、物性分野でなくスピントロニクス分野からも注目を集めている。ワイル半金属であることの証明は難しく、提案物質の多くは「候補」止まりであるが、ごく最近、シャンダイト型化合物Co3Sn2S2(キュリー温度175K以下で強磁性)のバルク単結晶において、ワイル電子状態が実験的に裏付けられた[D. F. Liu et al., Science 365, 1282 (2019)]。ほぼ同時期に、申請者らが、共スパッタ法による同物質の薄膜化に世界で初めて成功したことで、ワイル半金属薄膜・界面を用いた研究への期待が高まっている。
②目的:ワイル半金属ヘテロ界面におけるスピンヘリシティ磁気抵抗効果の実証
本研究では、理論予測されているスピンヘリシティ磁気抵抗効果[K. Kobayashi et al., JPSJ 87, 073707 (2018)]に着目し、その舞台となるワイル半金属ヘテロ界面の実現に挑む。ワイル点は、磁場の湧き出し(+)・吸い込み(-)に対応するペアを単位に現れ、各ワイル点の周辺ではスピン自由度と波数が結合している(スピンヘリシティ)。+/-は、系のマクロな磁化反転によってスイッチ可能であり、波数空間での+/-配置が異なる(同じ)物質を接続した場合、スピンヘリシティの不一致(一致)により電気抵抗が増加する(減少する)。この効果は、巨大磁気抵抗比に加え、不純物などの乱れに対して堅牢であることが予測されているが、その検証には、未だ報告の無い「垂直磁化系ワイル半金属薄膜の界面」を必要とする。申請者のCo3Sn2S2薄膜がこの条件に最も近いことを活かし(垂直磁化を確認済)、「界面」の創製により当該効果を世界に先駆けて実証することを目指す。
助38-05
ひまわり超高層寒冷化モニタリング実現に向けた地上レーザセンシング用狭帯域フィルタの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
地球温暖化は現代社会が抱える環境課題であり、その進行度を監視する有効な手段の確立が求められている。地球温暖化の進行に伴い、地表付近・下層大気は温暖化し、その影響で超高層領域は寒冷化する。超高層寒冷化によって夏期極域の高度80km付近に出現する夜光雲(氷粒子の雲)の発生頻度増大や発生領域拡大が指摘されており、夜光雲の観測情報を用いて、超高層領域の寒冷化、即ち地球温暖化のモニタリングが可能であると考えられている。近年、米国の低軌道衛星Aeronomy of Ice in the Mesosphere(AIM)[Russell et al., JASTP, 2009]によって夜光雲モニタリングは大きく前進した。しかし、極軌道をとる為に広域モニタリングが不連続などの課題がある。加えて、夜光雲情報から背景の大気温度情報を抽出する手法が十分に確立されていない為、寒冷化の度合いを定量的に把握できていない。
②目的
本研究では、静止軌道衛星ひまわりの全球画像データを活用した夜光雲モニタリングに地上レーザセンシングによる背景温度の計測を組合せることで夜光雲の発光波長特性から背景温度情報を抽出する手法を構築し、その手法をひまわりデータに適用することで地球規模の温暖化に伴う超高層領域の大気温度、即ち超高層寒冷化の全球変動をリアルタイムで連続的に捉える環境モニタリングシステムの実現を目指す。本目的達成には、夏期極域(日照時)に発生する夜光雲と同時期に地上レーザセンシングを行う必要があり、日照時の背景光ノイズを抑制する為の狭帯域フィルタの開発、及びレーザセンシングシステムへの実装も重要な目標である。
助38-06
物質表面の局所構造を高空間分解能で計測可能にする新規和周波発生分光法の創出
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
触媒や電極などの表面化学反応の分子メカニズムを理解するには、物質表面に吸着した分子の局所構造を、直接観測できることが理想的である。和周波発生(SFG)分光法は、表面・界面の情報を選択的に検出できる測定法のため、これまで吸着分子の観測に有用性を発揮してきた。しかし、従来の遠視野(far-field)による測定では、空間分解能は光の波長程度に制限され(回折限界)、得られる信号は多数の分子(~106個)の情報を平均化したものであった。
②目的
本研究の目的は、表面選択的な振動分光法であるSFG分光と、金属針の先端に生じる増強近接場(near-field)効果を組み合わせた増強近接場SFG分光法を開発することである。これによって、従来の分光測定の回折限界を打ち破り、物質表面の吸着分子の信号を1分子レベルで検出可能にする。さらに、表面化学反応の活性や選択性に影響を与える吸着分子の局所構造を、ナノメートル以下の空間分解能で観測できるようにする。
助38-07
触力覚的介入がFoP発生に及ぼす影響
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
誰もいない空間で「存在の感覚(FoP:feeling of a presence)」を覚えることは、一般的には気のせいあるいは超常現象の類として扱われるが、一部の脳機能障害患者(Brugger et al. 1996; Arzy et al. 2006)や精神・神経疾患患者(Fénelon et al. 2011)では無視できない数の報告例がある。また健常者でも、雪山登山中などに極限・瀕死の状態に直面すると、複数人でFoPを明確に体験することがある(Geiger 2009)。FoPを報告する患者では自己認識や運動・自己位置に関わる脳部位(島皮質など)で皮質障害が見られることが明らかにされており、また視覚と聴覚を遮断してロボティクス技術によりこれらの感覚運動の混乱を疑似的に引き起すことで、FoPを健常者に実験的に体験させることにも成功している(Blanke et al. 2014)。このように、FoPはヒトの認知・脳機能に深く関わるものとして、認知神経科学分野などでは近年その主要因や発生機序の科学的解明が試みられている。
②目的:課題設定とねらい
前述の雪山登山の例では、吹雪などで視覚・聴覚情報が上手く利用できない状況で良くFoPが報告されていることから、ロープで繋がった登山家達(ザイルシャフト)の触力覚的なコミュニケーション(自由に動けたり、互いに引っ張られたり、など)がFoP発生に大きく寄与しているものと考えられる。そこで本研究課題では、このザイルシャフトの状況を一般化して実現するために、ハプティクス技術を用いてFoP実験中に触力覚フィードバックを様々に操作できる実験システムを新たに開発し、触力覚的介入がFoP発生に及ぼす影響について明らかにすることに挑戦する。本研究課題により、FoPなどのヒトの身体認知研究に対して新たな可能性と議論の場を提供するとともに、究極的にはその成果を基盤として私たちのQOL(生活の質)を向上させる新しい感性認知支援システムの創出にまで繋げることを目指す。
基本テーマ1
助38-08
リアルタイム計測歪モデリングで実現する衛星航空機の大変形制御
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高精度通信観測の需要増に伴い、大気圏内を年単位で飛行し続ける衛星航空機の実用化が期待されている。衛星航空機の超細長翼は従来航空機にありえない大変形が発生する。2003年にNASAの試験衛星航空機が墜落して以来、数値モデルを用いた大変形解析の研究が活発化してきた。しかし、無人の衛星航空機が飛行し続けるには、設計段階の解析だけでなく、実運用中にリアルタイム計測される変形量と数値モデルを用いた大変形制御が必要となる。
②目的
大変形時でもリアルタイム計測できる変数で記述されたモデリング法を構築し、大変形制御を風洞実験で実証することが目的である。申請者含め、従来は大変形解析のみを目的としたベクトルモデルが開発されてきた。
一方で、制御用モデルはリアルタイム計測可能な変数で記述される必要がある。本研究では無線・光ファイバ歪センサの発達によって、大変形時も計測が容易になってきている歪に着目した過去にない新たなモデリング法を構築する。
助38-09
シリコンフォトニクス技術を用いて、世界初となるチップスケールの光パルス位相測定器の実現を目指す
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における該当分野の動向
近年、レーザー加工や光周波数コム、分光分析など、光短パルスの応用は産業、学術問わず広がりつつある。そして、短パルス光源の開発、校正には短パルス測定器が必要不可欠である。短パルスの波形測定に用いられる光相関計は一般に自由光学系から成り、大型、精密なアライメントが必要、機械的に脆弱、さらに高価である。こういった難点を克服するデバイスとして、過去に申請者はシリコン(Si)導波路上に二光子吸収フォトダイオード(PD)をアレイ化した構造のオンチップ光相関計を実証した。しかし、パルス光源の開発においては、パルス包絡線だけを測定する光相関計よりも、位相まで測定できる周波数分解光ゲーティング(FROG)装置などの方が需要が大きい。位相を再生するには相関波形と波長の強度分布(スペクトログラム)を取得する必要があるが、パルスのスペクトル測定に必要な分光器は集積が困難であるため、チップサイズのパルス位相再生器は報告例がない。
②目的:課題設定とねらい
本研究では世界初となるチップサイズのパルス位相再生器の実証を目指す。相関波形の取得には過去に実証済みのオンチップ光相関計を用い、さらに、これの片経路に波長フィルタを置き、そのフィルタリング波長をスキャンすることで波長情報を抽出してスペクトログラムを測定する。この方法で得られるスペクトログラムはソノグラムと呼ばれ、これによる位相再生はファイバ光学系で実証されている[K. Tairaら、IEEE Photon. Technol. Lett.(2001)]。分光器と違い波長フィルタは集積可能なので、チップ上に完全集積可能なパルス位相再生器を実現できる。
助38-10
安定・安価な高効率有機EL発光素子の開発-Cu(I)錯体の励起状態解析を基にして
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
有機electro luminescence(EL)素子は陰極および陽極から注入された電子と正孔が輸送されて発光性分子内で再結合し、発光する原理を用いたデバイス素子であり、次世代ディスプレイ、次世代照明用の光源として、大いに期待されている。また種々のフレキシブルな基板への展開も可能なことからウェアラブルデバイスな素子としての利用も期待されている。有機EL素子として当初、一重項から発光するけい光性物質が用いられていたが、電子と正孔からできる励起状態は励起一重項が25%、励起三重項が75%になるため、より高効率な素子として三重項から常温で発光するリン光性物質にその主流が移っていった。すなわち、白金(Pt)やイリジウム(Ir)などの第二、第三遷移金属錯体のりん光である。しかし、これらの性能は優れているものの、高価で希少金属材料を用いなければならないため、第3世代として、電荷移動励起状態をもつ有機化合物の熱活性化遅延蛍光(TADF)を利用した素子が開発され、大きなブレークスルーとなった。しかし、有機化合物の励起三重項は基本的に基底状態との遷移が禁制であり、寿命が長いため、耐久性の点から改良が望まれ、蛍光性物質へのエネルギー移動と組み合わせた素子など、さらなる開発が勢力的に進められている。
②目的
本研究では、安価で豊富で入手しやすい金属イオンであるCu(I)を用いた錯体に着目し、より安定・安価で高効率な発光素子をその励起電子構造の物理化学的、分子論的解明に基づいて開発することを目的とする。特に、Cu(I)錯体では、りん光と遅延けい光が両方とも発光する点がこれまでの発光素子とは異なっており、高効率素子の開発が期待される。
助38-11
金属材料におけるLPSO構造/ミルフィーユ構造による『革新的材料物性増強理論』の高分子材への適用
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
今世紀に入り、機械工学/金属材料の分野において、従来の常識を打ち破る革新的な学説が生まれた。LPSO構造(Long Period Stacking Ordered structure; 長周期積層構造)と名づけられたその構造体の力学物性は、柔らかい軽量金属と認識されていたMg合金従来の降伏強度を遥かに凌駕するものであり、この合金の適用範囲を大幅に拡大する新素材となった。この研究は、文科省の科研費補助金・特定領域研究「高性能マグネシウムの新展開」として1999年から4年間のプロジェクトが組まれ、近年では同科研費事業の新学術領域研究「シンクロ型LPSO構造の材料科学―次世代軽量化構造材料への新展開―」が2011年から、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の「航空機実装化を目指した超急冷マグネシウム合金の製造基盤技術開発」プロジェクトが2014年から、そして科研費事業の新学術領域「ミルフィーユ構造の材料科学-新強化原理に基づく次世代構造材料の創製-」が2018年から開始され、正に我が国の英知を結集したオールジャパン体制での開発研究が進行している。
②目的
近年、LPSO構造/ミルフィーユ構造の学理・学説が確立に至り、社会実装が達成されようとする中、金属・セラミックス・高分子の三大材料全てで、この構造/機能相関性の適応が検証されている。既にMg合金以外の金属材料系ではその実例が見出されようとしており、他の材料系においてもこの理論の適用と、新素材創出の機運が高まっている。しかしながら特に繊維・プラスチックを始めとする有機高分子材料系は、その構造単位が金属のように原子レベルで議論可能ではなく、分子/分子鎖の配列が階層的に複雑に絡み合った組織構造体であるが故、この立証に一定の困難さが付き纏う。本研究の目的は、結晶性高分子/無機フィラーナノ複合材料の延伸配向構造体を活用して、スケールの大きなミルフィーユ構造を創出し、新規高強度材料の創製(モノ)とLPSO構造理論の実証(コト)に資するアプローチを行うことである。
助38-12
超高密度2次元鉄ナノ磁石ハニカム規則配列作製による超省エネ電界書き込み制御型・磁気記憶素子の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
スマホ等でやりとりされる全ての情報は、クラウドコンピュータ内の磁石NS極向きで「1」「0」信号として保存される。信号制御にはコイルに電流を流し発生する磁界を使うため発熱する。5G社会の発展に伴い、世界の情報量は星の数ほどの1021個まで増大し、桁違いの電力消費が予想される。しかし、もし、電界で磁気情報を制御できる物質があれば発熱は生じない。
我々は2010-2012年に2原子層厚さ(0.4nm)のFeナノ磁石であれば、電界による磁気制御が可能なことを発見した[Nat. Nanotechnol. 5 (2010)792]。しかし、当時のFeナノ磁石の大きさは20nm程度と大きく、規則配列化も不可能であった。その後、我々は有機分子研究の中で、真空表面合成法を使うと2次元分子ハニカム(蜂の巣)格子が作製できる事が分かった。その格子の穴の大きさは1nmであったことから本研究を立案した。
②目的
電界応答する超極薄(厚さ0.4nm)・大きさ1nmの鉄ナノ磁石規則配列を実現する。本実験は全て、超高真空走査トンネル顕微鏡(STM)装置も用いて実施する。Cu(111)表面上に前駆体分子を1分子層分蒸着する。基板加熱し合成反応を起こす。前駆体分子同士が結合し、炭素原子の結合からなる2次元ハニカム格子が表面全体に作製される。ハニカム炭素格子には1nmの大きさの穴が開いている。この表面にFeを原子2層分蒸着する。Feがハニカム格子構造をフォローして配列すれば、超高密度1nmサイズの規則配列鉄ナノ磁石パターンが実現する。STM探針による電界印加実験を行う。
助38-13
多彩な伝導様式を示すグラフェンモアレ超格子の作製と量子閉じ込めによる新機能の発現
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
グラフェンは炭素のみで構成されたハニカム構造を有する単原子層物質であり、それらが積層した2層グラフェン(BLG)では整合性を持つAB積層構造が安定構造となり、いずれも価電子帯と伝導帯が一点で接合したゼロバンドギャップ半導体である。しかし近年、原子層1枚1枚をファンデルワールス力で持ち上げて積層する「ファンデルワールスヘテロ構造形成技術」が発展し、従来のMBE法などとは異なり、格子整合に捕らわれない非平衡な人工ヘテロ接合が形成できるようになってきた。ファンデルワールスヘテロ構造の特徴は、積層構造を詳細に制御でき、通常の2次元物質をも凌駕する特性をひきだせることが最大の利点といえる。その最たる例が、2枚のグラフェンシートがある角度をもって積層された2層グラフェン(TWBLG)である。小さなツイスト角度に依存して、2次元層同士の格子の角度のずれによるモアレ構造のパターンが形成され、従来の整合的積層とは異なる長距離変調によりバンド構造が一変する。さらに、マジックアングル(MA)と言われるツイスト角度約1.1°で積層されたMA-TWBLGでは、電荷中性点付近にフラットバンドが形成され、その上下に超格子ギャップが開くことになる。それに伴い、フラットバンド内ではMott絶縁体化や、その近傍での超伝導状態の発現といった現象が観測されており、もはや「グラフェンだからバンドギャップがない、超伝導にはならない」といった従来の常識が成り立たない系でありながら、グラフェン特有なバレーの自由度は維持されるという特異な系となっている。本研究では、このような人工的に作製された2次元物質を微細加工によって1次元的に閉じ込めることに注目した。
②目的:課題設定とねらい
本研究では、このような長周期構造形成による新しいグラフェン系での特徴的なバンド構造を利用し、「スプリットゲート構造による量子閉じ込め効果」を付加することで、その中における特異なキャリアの振る舞いを明らかにすることを目的とする。スプリットゲートとバックゲートの電圧をコントロールすることで、スプリットゲートの直下を絶縁化し、その間(量子細線領域)とスプリットゲートの外側(2次元電子領域)の電場を別々に設定することで、バリスティック伝導チャネルで期待される伝導度の量子化のみならず、超伝導電流、強磁性電流およびバレー流といった多彩な伝導チャネルの形成による新たな量子伝導現象の発現と観測をねらう。
助38-14
ばね形状の3次元流路を用いた伸縮デバイスの開発
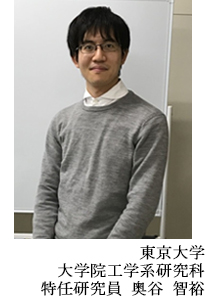 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、ヒトの身体やロボットの関節といった伸びる部位にも追従できる、伸縮電子デバイス(伸長率>100%)が注目を浴びている。このような伸縮デバイスを実現するには、ゴムのような伸長する材料が必ずしも必要ではなく、デバイス構造を工夫することでも実現可能である(C. Wang, et al., Adv. Mater. 30, 1801368 (2018).)。例えば、切り紙のようにフィルムに切り込みをいれたフィルムデバイスや、波状構造やばね構造を有するデバイスは、伸長に対し構造的に変形することで、デバイス素子自体に応力がかかるのを防ぎ、結果として伸縮性を持たせることが可能である。特にばね構造は、ばね幅に対しばねの全長が非常に大きく設計することが可能であるため、500%以上の伸長が容易に実現でき、さらにばね独自の復元力を利用することで繰り返し伸縮特性も付与可能であり、伸縮デバイスとして優れた構造であるといえる。(Y. Won, et al., NPG Asia Mater. 6, e132(2014)., J. Woo, et al., Adv. Funct. Mater., 1910026(2020).)。しかし、3次元のばね構造のデバイスを2次元から組み立てて作製するには複数の工程が必要で、また使用できる材料が限られており、応用性に乏しかった。
②目的
そこで本研究では、3次元のばね構造を有する伸縮電子デバイスのシンプルな開発方法を提案する。着目したのは、3Dプリンタと流路である。3Dプリンタは指定した箇所に材料を配置していく組み立て方式の手法のため、自由に3次元構造を作ることが可能である。そのため中空構造を有する3次元ばね構造を作製することも可能であると考えられ、この中空を流路として活用し、液体金属を封じ込めることで導電ネットワークを形成させ、伸縮デバイスを実現する。
助38-15
くさび型SPRセンサとDNAによるVOCの吸着メカニズムの解明と超高感度検出
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
「嗅覚」は人間の五感の中で最も数値化しにくい感覚である。「匂い」は多くの揮発性有機化合物(VOC)の集合であり、その検出技術は食品品質管理、医療・医薬品、安全検査等多方面へ応用でき、社会への影響は大きく、センサ市場の中でも今後特に発展が期待されている。食品の品質検査では、酢酸エチル等のVOCの分析が食品の鮮度の定量化に有効である。医療分野では、がん細胞が発する匂いの検出により進行レベル特定が期待されている。
しかるに現状では、目視による検査や破壊検査が行われており、時間を要し、不確実性が残る。気体分子の濃度は主としてガスクロマトグラフィー装置によって分析されるが、測定時間、手間、装置の大きさ、費用の点から現場へ導入されていない。これまで表面プラズモン共鳴(Surface Plasmon Resonance; SPR)センサや半導体式ガスセンサが開発されており、ppm~ppbの感度が報告されている。しかしながら、現状では1ppbを超える高い感度を持ち、匂いをかぎ分ける約1000種類の受容体をもつ犬の嗅覚が頼りとされており、同等以上のセンサの開発が必須である。
②目的:課題設定とねらい
ガスセンサの開発において、ガス成分の選択性と検出感度、スループットはトレードオフの関係にあり、全てを満足する技術は確立されていない。SPRセンサは金属表面の近接場光によって屈折率変化の検知により物質の濃度を測定する光センサである。標識が不要で、高スループットを可能にするSPRセンサは、感度を現状(1ppm)の1000倍にし、ガス選択性を付加することで、トレードオフの関係を打破する匂いセンサとなり得る。感度向上には、微小なガス濃度の変化に対して大きな信号変化を示すセンサハードウェアの性能向上が必要である。同時に雰囲気中の様々なガスの中から測定したいガス、匂いに関わる信号変化を選択的に検出することも重要である。本研究では「くさび型SPRセンサとDNAによるVOCの吸着メカニズムの解明と超高感度検出」を題目とし、センサの高感度化、DNAによるVOCの吸着メカニズムの解明と選択的高感度検出(1ppb超)を実現する。
助38-16
固体量子コンピュータモデルSi:Pの実演に向けた31P核のスピンダイナミクス解明
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
近年、固体量子コンピュータ(QC)に関する研究が世界的に盛んに行われている。数あるQCモデルの中で、Kaneにより提唱されたモデル(Si:P)は、量子ビットの長いコヒーレンス時間と量子ビット数の拡張性を共に備えている点において量子演算の優位性が高いことから注目を集めている。(B. E. Kane, Nature 133, 393(1998))。Si:Pは希薄にドープした31P原子の核スピン(I=1/2)を量子ビットとし、31P核スピンとその周囲の電子の相互作用により量子的な制御が可能となる。Si:Pは電子スピン共鳴(ESR)及び核磁気共鳴(NMR)手法を用いて量子計算を行う磁気共鳴型QCである。しかし、Si:P中の31P核は希薄であるためにスピンダイナミクスを支配する物理の解明は不十分で未だQC実現には至っていない。本研究はQC実現に向けた基礎研究として、31P核スピンのNMR信号を動的核偏極(DNP)により相対的に増幅させることにより、31P核のスピンダイナミクスを世界に先駆けて明らかにする。
②目的:課題設定とねらい
本研究の目的は、Si:PモデルのQC実現に向け量子ビットとなる31P核のスピンダイナミクスを世界に先駆けて解明することである。Si:Pでは核スピンが希薄な上に超低温では縦緩和時間T1Nが非常に長く核磁化が小さい。そのため、31P核のNMR信号の高感度な検出が課題となる。DNPにより31P核スピンを100%完全偏極させることで、熱平行状態に比べ相対的にNMR信号を増幅させ、課題を克服する。NMR感度に重きを置いたESR/NMR二重磁気共鳴用共振器を開発することにより微弱な31P核のNMR信号の高感度測定を実現する。QCにおいて量子計算を行う演算時間は31P核スピンの横緩和時間T2Nに依存することから、T2NのDNP-NMRによる直接観測が最大の課題である。QC実演に向けてT2Nのスピンダイナミクスを解明し、初期化及び演算のためのパラメータ探索をねらいとする。
助38-17
走査型プローブ顕微鏡によるMEMSの機械電気特性評価
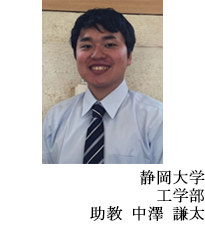 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
将来の社会の姿であるSociety 5.0では温度や速度などの物理情報をモノに伝えるインターフェイスとして、物理センサが非常に重要となる。物理センサにはMEMS技術が適用されることが多く、Society 5.0におけるキー技術のひとつである。MEMSセンサでは機械的挙動をもとに物理変数を計測する。例えば圧力センサでは、薄い円板の表面と裏面に発生した差圧を円板の変形として検出する。そのため可動構造の機械的挙動を検出する手法はMEMSの性能に直接的に影響する。機械的挙動の検出には、静電容量型、圧電型、ひずみゲージ型などがある。ひずみゲージ型にはピエゾ抵抗効果がしばしば用いられる。製作されたMEMSセンサの評価方法は確立されていないものが未だ多く残されている。しかし、近年において評価方法の研究の進展は大きくない。その要因として、技術的には測定試料(MEMSセンサ)が微小で機械的に運動すること、MEMS分野的には計測手法よりも新しいデバイス開発に重きが置かれていることが考えられる。評価方法の中でも特に、運転中にMEMSセンサの機械電気特性を高分解能で隅々まで評価することのできる計測方法の確立が望まれている。
②目的
そこで申請者は走査型プローブ顕微鏡(SPM)を用いてMEMSセンサを、運転中に高分解能に機械電気特性を評価する手法を提案する。計測対象として、MEMSの重要な機械運動検出機構のピエゾ抵抗型ひずみセンサを用いる。運転中、すなわち、ひずみ印加によって生じるピエゾ抵抗型センサの電気的挙動の変化をミクロに計測する。さらに、それらミクロ計測を基にした最適設計指針の創成を行うことを目的とする。
助38-18
硫黄の脱離を分子設計の鍵とするn型有機半導体の可溶性前駆体の開発と有機薄膜太陽電池への応用
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
有機半導体は有機薄膜太陽電池をはじめとする次世代電子デバイスの要である。有機半導体を溶液プロセスにより成膜できれば、デバイスの低価格化と大面積化に繋がる。しかし、一般に優れた半導体特性を示す有機分子は溶解性が低く、溶液プロセスには不向きである。そのため可溶性前駆体の利用に注目が寄せられている。可溶性前駆体とは、有機溶媒に対して優れた溶解性を示しつつ、光や熱といった外部刺激により有機半導体分子へと変換できる化合物を指す(U. H. F. Bunz, et al., Chem. Rev. 2018, 118, 5598.))。これらを活用すれば有機半導体を溶液プロセスにより成膜することが可能となる。加えて、可溶性前駆体を巧みに扱えば、従来の真空蒸着では不可能なナノレベルでの分子配列制御を達成することもできる。これまでに、p型有機半導体に関しては対応する可溶性前駆体が開発されてきた。一方、n型有機半導体の可溶性前駆体には限りがあり、特に代表的なn型有機半導体であるペリレンビスイミド(PBI)については報告がない。有機薄膜太陽電池といった光電変換素子においてはp型半導体とn型半導体の双方の開発が不可欠であることを考慮すると、新規なn型有機半導体の可溶性前駆体の創出が求められる。
②目的
申請者は最近、独自に開発した「硫黄挿入型ペリレンビスイミド」に光や熱を加えると、硫黄が脱離し、n型有機半導体分子であるPBIへと変化することを明らかにした。本研究ではこの化合物を可溶性前駆体として活用する手法を確立する。最終的には、この前駆体を駆使して、高い光電変換効率を示す有機薄膜太陽電池の開発を目指す。
助38-19
シリコン技術を基盤とした高感度短波赤外光センサの研究開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
コロナ禍で生活が一変した。従来と違った生活様式はポストコロナ禍時代でも継続となる可能性が高い。申請者は光通信デバイスの研究を行ってきた。「(1)コミュニケーションインフラである光通信技術の一層の大容量化」と「(2)通信以外の分野、特に医療・創薬分野への光デバイス技術の応用」で今後の社会へ貢献しようと考えている。テレワークや遠隔授業などでもインターネットが必須となった一方、必要となる大容量通信が完全に行き渡ったとは言いがたい。申請者はシリコンフォトニクス技術に約20年前の黎明期から取り組んできた。生産性よく低電力の光通信デバイスを作製できる利点があり、世界的に研究が進められた結果、データセンタでの利用を中心に1000億円市場に成長した。上記(1)へ貢献すべく、大容量化(波長分割多重やコヒーレント通信)の技術開発をこれまで同様に進めている。一方、光通信で利用される波長1.55ミクロンのSWIR光は人間の眼に損傷を与えにくいアイセーフの特長があり、自動運転や監視用のレーザーレーダーに向けた研究(主に光源側)が活発化した。生体をはじめとする物体・物質への侵入長が大きい特長を利用し、上記(2)のように医療や創薬における非破壊・非接触の内部観察技術として応用を拡げることにも大きな意義がある。今後研究が活発化するものと考えられる。
②目的
申請者が推進してきた光通信用Si上Ge受光デバイス技術を基盤として、SWIRの広い領域で高感度動作するSi系光センサを開発し、レーザーレーダーや医療・創薬分野へ応用することを目的とする。SWIR光は、生体応用の観点からはNIR-I(0.8-1.0µm)、II(1.0-1.4micro;m)、III(1.5-1.7µm)に分類できる。Si光センサはNIR-Iで動作するが、IIおよびIIIでは光吸収がなく動作しない。InGaAs光センサはNIR-IIおよびIIIで動作するが、Iでは感度が低下する傾向があり、価格・生産性にも劣る。Ge光センサはNIR-I、IIおよびIIIの全ての領域で動作する。Siプロセスを利用できるため生産性がよく、イメージング用のアレイデバイスへも展開しやすい。ボトルネックは、自由空間光に対して「薄膜」Ge光センサの受光効率がNIR-IIIで十分でない点がある。まずこの課題解決に挑戦する。
助38-20
人工分子の軌道を利用した桁違いに速い単一電子スピン量子操作の実証とその物理の研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:集積化が望める量子計算ハードウェアにおける単一電子スピン操作
単一電子スピンは、量子力学的な二準位系を構成し、情報の担体(量子ビット)として量子情報への応用や基礎物性に向けた研究が盛んである。特に半導体上に作成される人工原子構造(量子ドット)に閉じ込めることで、量子計算や、量子シミュレーションの研究開発が加速している。現在は、量子位相の保持時間(コヒーレンス時間)が長い半導体として珪素を材料とした開発が集中しており、また、電子スピン一つに付き量子ドットを一つ割り当てる小規模のデバイス開発が進められている。
半導体デバイスは微細加工技術によって量子ビットの調整に使う金属電極をナノスケールに集積化できる利点を持っているため、極低温でも比較的簡便な電気的な動作が見込まれている。一方で、量子ビットを十分な速度で動作させるためには、現状ではデバイスに磁性材料を載せながら大きな高周波電圧を印加する必要がある。そのため、多数の演算を連続して行う際には固定した条件での安定した動作が難しく、種々のフィードバック機構も研究されている。もう一方で、珪素という材料系の制約から、光学特性としては量子通信には不向きで、長距離通信を用いる量子暗号システムとの関りが薄いままである。
②目的:複数ドットを使った単一スピン回転操作の実証
半導体中の単一電子スピンを用いた量子情報操作を今後さらに発展させるためには、電気操作の利得が大きくかつ汎用性の高いスピン操作の仕組みが必要だと考え、多重量子ドット中でのスピンシャトルを利用したスピン操作法を実証し、より確度の高いスピン操作を得るための物理的な研究を提案する。
トンネル効果を介して複数の量子ドットが結合した人工分子様の多重ドットを用意し、その分子的な軌道中をスピンが移動することによって、半導体に存在するスピン軌道相互作用を介して、既存のスピン操作を凌駕するスピン回転操作の速度を実現する。
助38-21
ZnSe系有機-無機ハイブリッド型紫外集積APDの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、医療、科学計測、天文計測、次世代光ディスク用、火炎センサー用などの紫外線光検出器に注目が集まっている。現在の医療用PETに必要な微弱放射線の検出には、シンチレータを介して変換された可視光を光電子増倍管で検出する方式が用いられる。そのため、応答速度が遅くかつ装置が大型で壊れやすく高価になるという問題点がある。一方、紫外線変換型の高速シンチレータ(LuAG:Prなど:応答速度20ns)を用いることで、高速PETシステムが実現可能になると期待されている。そこで、光電子増倍管を全固体素子である紫外線光波帯アバランシェ・フォトダイオード(APD)に置き換えることができれば、上記問題が解決されるだけでなく集積化も可能となる。しかしながら、紫外線領域では各材料の吸収損失が大きいため、紫外線波長域専用の集積型APDは実用化されていない。紫外線光波帯の高感度集積型APDが実用化されれば、医療分野のみならず、天文分野、科学計測分野、次世代光ディスクなど多分野にわたり貢献できるものと期待されている。
②目的
本研究では、ZnSe系有機-無機ハイブリッド型アバランシェ・フォトダイオード(APD)により紫外線APDのもつ感度および暗電流などの課題を打破して、紫外線光波帯で初めて実用的な集積型APDを実現することを目的とする。光検出器の性能で最も重要なものは、高い感度および低い暗電流であり、この両立により高い光検出能D*が実現される。本研究は、無機層としてZnSSeを、有機層としてPEDOT:PSSを用いたZnSe系有機-無機ハイブリッド型APDにおいて、低暗電流化・安定動作化、および集積化を目指し、実用に供しうる紫外線領域の全固体高感度集積型光検出器を実現しようとするものである。
助38-22
ナノスケール電気摂動効果を用いた新奇ナノ分光法の開拓
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
2000年代中頃から、貴金属ナノ構造近傍に誘起された局所光増強場(局在表面プラズモン)を利用した表面・界面物性の高感度分光分析が国内外で精力的に行われている。このナノ分析法は、生体分子等のバイオ材料[Xiao, Anal. Chem. 2016他多数]・量子構造等の半導体材料[Liao, Nano Lett. 2016, Park, Nano Lett. 2016他多数]・触媒等のグリーン材料[Hartman, J. Phys. Chem. Lett. 2016他多数]といった最先端材料のナノ分析に応用されている。申請者はこの研究分野において高空間分解能でナノ分光センシング・イメージングを行う研究開発を先進してきた[申請者筆頭, Nature Commun. 2013; Nature Photonics 2009; Nano Lett. 2006;他多数]。しかしながら、従来のナノ分光計測法は全て物質固有の構造および物性を受動計測することにとどまっているのが現状である。
②目的:課題設定とねらい
本研究の目的は、単一分子レベルの空間分解能と分子機能制御能力を兼備する革新的ナノ分光計測手法を開発することである。本研究の独創的な点は、分子スケールの電気的摂動効果をプローブとした全く新しい原理に基づくナノ分光計測法を開発することにある。従来のナノ分光計測法は試料物質のあるがままの姿(光物性)を観察(測定)することに特化した“パッシブ(受動的)”な光計測に基づくものであったが、本手法は電気的摂動効果による分子機能制御という“アクティブ(能動的)”なナノ光計測技術を提供できる。この実現によって、任意の場所とタイミングで分子機能を局所的に誘発・制御することも可能となり、機能性ナノ材料開発・分子パターニング技術への応用が実現される。
助38-23
テラヘルツコムを用いたテラヘルツ単一素子イメージング
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
テラヘルツ波(THz波)は波長30um~3mm程度の電磁波であり、電波と光の中間に位置する。電波のような透過性と光のような画像取得能力という利点を持つ。このため非破壊検査への応用が期待されている。具体的には空港におけるセキュリティチェックや考古学における絵画の検査などに用いられている。THz波はX線に比べてフォトンエネルギーが6桁近く小さいため、測定対象に対する侵襲性が小さい。このため、ボディスキャナーにおける人体への安全性にも着目されている。
テラヘルツ非破壊検査におけるイメージング技術は、カメラに代表されるアレイ検出器を使ったイメージングと、単一検出器を用いて光源、サンプルを走査する(ラスタースキャン)手法に大別される。アレイ検出器の利点は測定時間が極めて短いことであるが、テラヘルツ帯の検出器でアレイ素子を構築するには高い技術が必要である。現在実現しているテラヘルツ帯のアレイ検出器は熱型検出器によるものがほとんどで、面照射に対する検出感度が十分でない。一方ラスタースキャンは、走査のために測定時間を要するが、光源の照射強度を最大限利用できる事や、単純な点型素子を利用できる事が利点である。このため、可視領域に比べてデバイスが未熟なTHz帯イメージングにおいてはラスタースキャンが主流である。単一素子も用いて、スキャンを行わない(スキャンレス)二次元イメージングの試みも報告されているが、液晶素子などの補助的な二次元素子やその切り替えが必要となる。しかし、THz領域では適当な液晶素子が乏しいため、測定系の構築が難しい。これまでの単一検出素子を用いた二次元イメージング手法にはスキャニングに対応した操作が必要となり実験を複雑にしている。
そこで、本研究では、THz帯多次元空間分散素子(Virtually imaged phased array: VIPA)を開発し、周波数空間変換を用いた二次元THzイメージングを提案する。これによって、単一検出素子によるテラヘルツ帯スキャンレス二次元イメージングが実現する。
助38-24
ベイズ推定に基づく適応的グループテストのアルゴリズム開発:検体検査の効率化と誤り訂正
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
血液学的検査や遺伝子検査などの検体検査は、多くの医療機関において日常的に行われている。通常時は、患者数に対して十分な医療資源が用意されているが、一方で感染症の爆発的流行が起きた場合、膨大な患者集団を相手に、同じ検査を何度も行う必要性が生じる。検査を速やかに行い、患者に適切な処置を施すことが必要であるが、大きな時間的・資源的コストを伴う検体検査は、医療のボトルネックとなりうる。
医学的検査が標準化した近代では、検査の効率化は常に議論されてきた。そのような中、1943年に経済学者のRobert Dorfmanはグループテストと呼ばれる検査法を提案した。グループテストとは、患者から採取した検体を混ぜ、混ぜ合わせた検体に対して検査を行う方法である。混ぜ合わせた検体数を患者数より少なくすることで、検査回数を減らすことができる。ただし、検査の結果から患者の状態(感染している・していない)を推定する数学的プロセスが必要となる。
Dorfmanの提案の一方で、戦後にはグループテストが必要となるような感染症の蔓延は見られなかった。その間、グループテストは情報通信における符号やセンシングの数学的理論と大きく関係することから、情報科学の問題としての研究が行われてきた。しかし、この度のCOVID-19の流行は、グループテストが実用化されるべき技術であることを示している。
②目的
実際の検体検査にはある確率でエラーが起こる。このエラーは検査の検出限界や、検体採取の失敗などに起因する。上記の符号理論とグループテストの関係性を鑑みると、グループテストは検査数削減だけでなく、検査エラーの訂正にも貢献できると考えられる。そこで本研究では、グループテストにおける「混ぜ合わせた検体に対する検査結果から患者個人の状態を推定する」というプロセスについてのアルゴリズムを開発し、検査数の削減とエラーの訂正を数学的に行うことで、検体検査の効率化を実現することを目標とする。
助38-25
表現力豊かな音声の声質を決める声門流波形と声道伝達関数特徴の解析
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
音声に関するマン・マシン・インターフェイスの長年の研究の結果、音声認識技術や音声合成技術がスマートフォン、スマートスピーカ、家電製品、ロボット、自動車などに組み込まれて利用されている。しかし、多様な感情や表現力を伴う人間の音声の認識と合成はまだ不完全であり、音声インターフェース技術を幅広い人間の表現力に対処できるように改善することが望まれている。広く使用されている感情モデルには、「覚醒度」(活性から非活性までの軸)と「感情価」(喜びから不快までの軸)の2つの直交する次元を含む。その観点において、感情認識と表現音声の合成は、覚醒度の次元ではそれなりの性能を発揮するが、感情価の次元では、依然として性能が劣っている。
この点、ディープニューラルネットワークやエンドツーエンド処理に基づく最新技術の進歩には目覚ましいものがある。しかし、それらの研究で用いらる方法には、大量のトレーニングデータが必要であると同時に、トレーニング対象である特定のタスクの枠を越えた操作に対応する柔軟性はない。さらに、表現力のある発話に関わる音響的と生理的要因の関係については未だに理解されていないため、表現力のある声質は自由にコントロールできていないのが現状である。
特に表現の豊かさには2つの生理学的要因が重要な役割を果たしていると考えられている。それは、声の音響的な源であり、感情状態によって大きく変調される声門流と、主に発声された音素に依存するが、表現状態によっても影響を受ける声道の形状である。これら2つの要因を多様な感情や表現力を伴う人間の音声波形から確実に推定できれば、音声中の感情変動の生理学的統計モデルの構築につながる可能性がある。これにより、表現関連モデルに基づいてこれらの要因を独立して操作することが可能となり、元の発話を修正したり、聞き手側で送信・再生する前に表現力を高めたりすることができるようになる。このような技術が開発されることで、現在、そして将来的には、これほどまでに普及しているオンラインコミュニケーションツールの楽しさや効果を高めることが期待されている。
助38-26
繊維人工筋で駆動される手指用装着型アシスト装置の試作と制御
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
装着型アシスト装置は、ロボット技術により装着者の動きに応じてアクチュエータの力が制御され、装着者の動作を支援する装置であり、運動弱者の自立支援や労働者の負担軽減のための一手段として期待されている。この種の装置には、対人安全性を備えたソフトアクチュエータが適しており、本研究では最近発明された繊維人工筋に着目する。繊維人工筋は、高分子繊維が加熱により収縮する性質を利用した熱駆動ソフトアクチュエータである。ナイロン糸等をコイル状に加工することにより作製でき、例えば人工筋に巻き付けたニクロム線に通電した際のジュール熱で駆動できる。これは、柔軟、超軽量、出力/重量比が高い、安価、静音といった装着型の装置に適した利点を備える。繊維人工筋は、比較的新しいアクチュエータであるため、製品化には至っておらず、各研究者が試行錯誤的に試作している段階であるが、見方を変えれば、アクチュエータとして更なる発展の可能性を大いに秘めている。
②目的
従来のナイロン製繊維人工筋をアクチュエータとして用いる場合、100℃以上に加熱して駆動されるのが一般的だが、装着型の装置へ応用するには、人体に対する安全対策が必須で高いコストがかかる。しかも、一般に動作速度が遅く、人間の動きに追従することが難しい。加えて、入力電圧―収縮量の関係に大きなヒステリシスを有し、かつヒステリシスは動作速度や負荷に依存して不確定に歪むため正確な制御が難しいという課題もある。そこで、本研究では、従来よりも低温駆動時の動作速度を改善したハイブリッド型の新しい繊維人工筋をアクチュエータとして用いた、手指用装着型アシスト装置を試作するとともに、繊維人工筋の非線形ヒステリシス特性に対処するため、機械学習に基づくモデリング・制御手法を用いて制御システムを構築し、被験者による検証実験を行うことを目的とする。
助38-27
リポソームとナノフォトニック共振器のインタフェース
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
Liposomes are biological nano-particles made from lipid bilayers. Liposomes have the same structure as cells, but they do not have a cell nucleus. For this reason, liposomes make an excellent test platform to develop manipulation techniques for living cells, and other bio-particles such as exosomes. Use of nanowaveguides to trap nanoparticles will allow the development of integrated optical circuits for trapping, transport and analysis of nanoparticles. This method could allow new miniaturized technology for analysis of bio-nanoparticles. However, for bio-nanoparticles such as liposomes, two large problems exist: i) particles adhere to the nanowaveguide surface and ii) particles are very difficult to trap because of very low refractive index.
②目的
In the proposed research project, the applicant will create a nanophotonic platform to i) Transport and trap liposomes on a nanowaveguide (optical nanofiber) and ii) couple the liposomes to a nanowaveguide cavity.
助38-28
高齢心不全患者における深層学習を応用したフレイル自動評価法の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高齢化社会の進行に伴い、心不全罹患症例は増加の一途をたどり、厚生労働省の試算では2055年までにわが国の人口は約3割減少する一方、75歳以上の高齢者の割合は約3割に増加し、心不全患者は約120万人に達すると推測されている。高齢心不全患者の強力な予後規定因子のうち、近年「フレイル(虚弱度)」が注目されており、その評価法に関する報告が相次いでいる。しかしながら、いずれも評価者毎に判断される主観的指標(例:頑強で活動的、動作緩慢等)によるものにとどまっている。したがって、フレイルは強力な予後規定因子とされながらも、主観的指標のみでは高齢者心不全患者のリスク層別に応用することが困難であることから、客観的評価法の開発が喫緊の課題とされている。
②目的
我々は最近、人工知能による深層学習を応用した萌芽的研究として、北海道大学工学研究院、北海道大学医学研究院画像診断学教室、東京に本社を置くIT企業と共同で、OpenPose®(米国カーネギーメロン大学が公開している深層学習を用いて人物のポーズを可視化する手法)を用いた歩行動画アプリケーションの開発に成功した。本アプリを用いて撮影された歩行動画を人工知能解析(深層学習)することにより、高齢者心不全患者におけるフレイル自動検出、予後層別を行うことが本研究の目的である。
共同研究施設(全国15病院)より75歳以上の高齢者心不全症例を登録し、本歩行動画アプリを搭載したiPod®により、統一条件下で歩行動画を撮影し、動画データを変換用コンピュータ(Jetson Nano®)でエクセルデータ化(座標情報として保存)する。その後、予後と関連する歩行パターンについて人工知能深層学習により層別解析を行う。
助38-29
磁場中多角度光散乱計測システムの開発と痛風診断装置への確立
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
現在、痛風関節炎の診断において、原因物質である尿酸ナトリウム(MSU)結晶の存在を非侵襲的に確認する方法が求められている。既存の装置を用いて結晶の存在を確認することも報告されているが、それぞれに問題点があり確立された方法はない。我々はこの尿酸ナトリウム結晶が、永久磁石程度の静磁場下で「磁場配向」することを明らかにし、結晶の懸濁液に光を透過すると、磁場のON-OFFで光強度が変化することを報告した。この現象を利用し、生体透過性の高い近赤外光を体外から照射し磁場で疾患が疑われる部分の光強度を変化させ、体内の結晶の有無を評価することを目指している。
②目的
診断の際、近赤外光を対象の関節に照射するが、測定領域が厚いと検出された光は透過できないため散乱光を考慮する必要がある。MSU結晶のサイズはマイクロオーダーであり、入射光の波長と比較して大きい粒子のため、前強い散乱を起こすミー散乱によって説明される。この場合前方、側方、後方の散乱光強度が均一にはならない。さらに、それがMSUなどの大きな異方性結晶である場合、「磁場配向」による散乱への影響は未知である。実際に装置に応用するにあたっては、疾患部分に対してどのように磁場を印加し、どのように光励起および検出を行うのが適切か、結晶の散乱特性を踏まえて検討する必要がある。そこで、本研究は以下の2つを目的とする。
・磁場中での多角度光散乱計測システムの開発
・最適な光学システムの配置の確立
助38-30
骨組織の材料物性に及ぼす骨髄機能の解明と、骨粗鬆症の治療に向けた応用
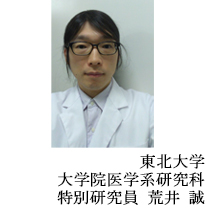 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
骨粗鬆症とは、骨の脆弱性が増し、骨折の危険性が増大する疾患である。近年、その有病率は高齢化の進行とともに増加の一途をたどっており、わが国における骨粗鬆症患者数は約1,300万人と推定されている。骨粗鬆症で最も問題となるのは骨折である。その代表である大腿骨近位部骨折のわが国における年間発生数は約18万件であり、その数は年々増加している。さらに、骨折は移動を含めた生活全般の機能を低下させるだけでなく、生命予後にも悪影響を及ぼすことが明らかになっている。こうした社会的要請に応えるべく骨粗鬆症治療薬が開発されているが、それでもなお、高齢化の進行とともに増加する骨粗鬆症患者数や骨折発生数を抑えているとは言い難いのが現状である。
医工連携と言われて久しいが、その当初から骨組織は物性物理学的な考察になじみやすいことから工学的な解析対象とされてきた。一方、医学的にも、従来は重力に抗するだけの支持的な組織としてしか捉えられていなかった骨組織が、絶えずリモデリングを続け、他臓器との相互作用も有する臓器であると認識されるようになった。医工連携に関しても、材料物性に基づいて骨組織を補強するマテリアルの開発などが進められている。しかし、そうした「骨を外から強くする」研究は工学側から進められている一方で、「骨を中から強くする」研究に関してはまだ不十分と言わざるを得ない。
②目的:課題設定とねらい
本研究では、超高齢化社会を迎え今もなお増え続けている骨粗鬆症や骨折を抑え、健康寿命を延伸することを長期的な方向性として見据えている。そしてそのために、骨組織を医学・工学の両面から捉え、新規の骨粗鬆症の治療薬・予防法開発の基盤を創出することを目的としている。その際に、骨組織の内部に存在する骨髄の機能に着目し、それが骨組織の材料物性に及ぼす影響を解明することで、「骨を中から強くする」ことを志向する。
助38-31
健康環境ミエル化のための室内バイオエアロゾル連続センシング技術の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
アレルゲンやウイルスなどの生物由来の微小粒子であるバイオエアロゾルは、密閉空間となる屋内環境中において長時間浮遊し続けるにも関わらず、知覚することができないために暴露を防ぐことが難しい。さらに屋外とは異なり、マスクなどを装着せずに無防備な状態で過ごす屋内では、無意識のうちにバイオエアロゾルに接触・吸引することで体内に取り込まれ、アレルギー疾患やウイルス感染症に罹患するリスクが高まる。したがって屋内において「見えない」バイオエアロゾルを「ミエル化」することで、ヒトにバイオエアロゾルの存在を認識させ、掃除や換気、消毒などの暴露回避を促すことがバイオエアロゾルを原因とした疾患予防に重要である。しかしながら、センサの感度や選択性、繰り返し使用に課題があり現在までにそのようなモニタリングシステムは実現していない。
②目的:課題設定とねらい
埃やPM2.5などのエアロゾルを検出する装置は既に開発・製品化されているが、これらはレーザー光の散乱光強度から微小浮遊粒子を検出するため、成分を識別することはできない。そこで本研究は、密閉空間となる室内のバイオエアロゾル濃度を成分ごとに連続的に計測し、環境状態変化をミエル化することで意識的な暴露回避を促し、健康的な屋内環境を築くバイオセンサ技術の開発を目的とする。
助38-32
磁化細胞単一操作機構を具備したマイクロ引張デバイスによる細胞-細胞間接着強度の測定
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
体内の細胞は、その大部分が基材に接着または、細胞同士で接着して存在している。このような細胞において、接着は細胞特性を決定する重要な要因となる。がん細胞が、転移細胞かどうかを細胞-基材間の接着強度から見分けられる可能性を報告されている(Fuhrmann et al., Biophys. J., 2001.)。また、細胞同士の接着が細胞死や増殖に関わるという報告(Jaiswal et al., Oncogene, 2002.、Byrne et al., Mathl. Comput. Modelling, 1996.)があり、これらの文献は、2020年現在に至るまで多数引用されている。このように、細胞転移や細胞死などの細胞学的知見において接着性の評価は極めて重要である。
しかし、細胞-基材間の接着強度は計測手法が報告されている一方で、細胞-細胞間の接着強度を効果的に測定する手法は存在しない。このため、細胞-細胞間の接着が細胞特性において重要であると従来から知られているが、強度による定量的な議論がなされていないという現状である。
②目的
従来では達成されていない「細胞特性の細胞-細胞間接着力への依存性」の追求を課題とし、細胞-細胞間接着強度の計測システム開発を目的とする。がん細胞や幹細胞など、様々な細胞の接着強度の汎用的な定量評価実現がねらいである。
助38-33
健康寿命延伸に向けた体内時計機能の若返り
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
現代の60歳以上のおよそ3割に何らかの睡眠障害がみられると言われている。年齢と共に睡眠は質・量ともに変化を示し、健康な人であっても睡眠が浅くなり、中途覚醒や早期覚醒がみられる。また、血圧、体温、血中のホルモン分泌も変化し、老化とともに生体リズムが徐々に破綻していく。さらに、退職や隣人との死別、メリハリのない生活による精神的、身体的なストレスが睡眠障害を招く事や、認知症と睡眠障害が併発する事実などから、適切な睡眠をとる事が健康寿命を延長する一つの方法であり、現代の超高齢化社会において、老化に伴う睡眠障害の治療は喫緊の課題と言える。しかし、高齢者にとって適切な睡眠をとる事は実際困難であり、何らかの介入が必要と考えられるが、その効果的な方法が未だ存在しない。本研究では、老化に伴う睡眠障害やそれに伴う様々な生理機能の低下を回復可能な方法の開発を行い、現代の高齢者の生活の質の向上を可能とする臨床応用に向けた技術基盤の構築を目的とする。
睡眠・覚醒など、ほぼすべての生理機能には24時間を1サイクルとする“概日リズム”が存在し、“概日時計”がその時間的調節を担う。我々の身体を構成するすべての細胞に、概日時計は備わり、時計遺伝子の転写・翻訳を介したフィードバックループがその中心的役割を示す。概日時計の中でも、中枢時計である「視交叉上核」がペースメーカーとして機能し、睡眠・覚醒のリズムを調節する。この視交叉上核では、数千にも及ぶ神経細胞が密集し、その一つ一つが24時間のリズムを刻むと同時に、細胞間ネットワークにより同期する事で安定した24時間のリズムを刻む。また、網膜から入ってきた環境の明暗情報は視交叉上核に入力し、視交叉上核の24時間のリズムは、環境の明暗サイクルに同調する。しかし、老化とともに、①視交叉上核の細胞間脳同期が低下する事、②明暗環境への同調に破綻が生じる事、により適切な時間に適切な質の睡眠がとれなくなり、睡眠障害が生じてしまう。したがって、老化に伴うこの二つの機能破綻を何らかの形で回復する事ができれば、老化に伴う睡眠障害が改善され、生活の質の向上や健康寿命の延伸が期待できる。本研究では、老化に伴う視交叉上核の同期を回復する事(Synchronization)、さらに視交叉上核の概日リズムを24時間の明暗環境に適切に同調する事(Entrainment)を達成する為、実験動物であるマウスを用い、老化に伴う概日時計機能の破綻を、“光”を用いて回復する事を目指す。
助38-34
転移性脳腫瘍定位放射線照射における実測線量不確かさを考慮した品質管理手法の確立
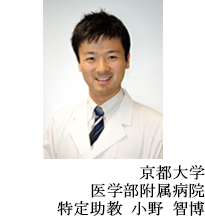 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ここ数年、転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療に大きな変化が生じている。日本放射線腫瘍学会の2016年ガイドラインにおいて、放射線治療は4個以下の病巣を対象としていたが、本邦で実施された多施設共同前向き観察試験の結果、患者の全生存期間は、転移性個数2-4個群と5-10個群との間で有意な差異が認められなかった(Yamamoto et al Lancet Oncol. 2014)。これを受け現在では患者の長期予後と有害事象の軽減の観点から10個以下の病巣への定位放射線治療による加療が推奨されてきている。一方、転移性脳腫瘍への定位放射線治療は腫瘍径3cm未満を対象とするため、X線を出力する照射野の大きさが小さくなる。しかしこの小照射野におけるX線の挙動は通常サイズの照射野に比べ複雑となり、投与される線量が不確かであることが現状だ。これにより小照射野測定における過剰過少照射の医療事故を誘発していた。これを受けIAEAは、照射野サイズ5cm2以下に対する小照射野測定の不確かさを軽減する補正方法に関する勧告を発出した(IAEA TRS-483 2017)。本勧告により照射野サイズ毎に出力補正係数(以下:TRS483出力補正係数)が与えられ、定型小照射野に対する検出器応答の不確かさの軽減が可能となった。しかし、TRS483出力補正係数は、実患者における照射野の連続的な変形に対し適用できない問題があり、実臨床上抜本的な解決策が強く求められている。
②目的
本研究の目的は、小照射野における過剰過少照射の問題を解決し患者の長期予後に貢献する安全で確かな治療を患者に提供することである。具体的には、脳定位放射線治療における患者投与線量の不確かさが存在する現状の課題解決を目指し、患者毎に異なる複雑な照射プランにTRS483出力補正係数を適用する手法を創出し、多種類の検出器を用いたより確かな実投与線量の評価を実施する。
助38-35
副作用セルフマネジメントによる効率的かつ安全な化学療法のためのシステム開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
2017年人口動態統計および全国がん登録によると、がんで死亡した人は373,334人で、がんは全死亡原因の27.9%を占めている。2016年に新たに診断されたがんは995,131例であり、1985年以降は癌の罹患率は現在も増加傾向にある。集学的治療の進歩に伴い、化学療法により生存期間が延長することが証明されてきている。そのため、多くのがん患者が化学療法を受ける状況になっており、癌治療の中で化学療法の重要性はますます高まってきている。このような背景のなか、長期入院の必要性がなく入院費などの負担軽減や、日常生活を継続できるなどのメリットがあることから、近年は外来にて化学療法を行う機会が増加している。しかしながら、化学療法を行うと、副作用はほぼ必発であり、1.6%~11.1%で致死的な状態に陥ることが報告されている。重症化の予防や早期治療介入のためには、副作用の状態を把握し、適切なタイミングでの医療介入が必要である。しかしながら、重症化率はそれほど高くはないため、医療者が全患者の状態を毎日外来診察や電話問診等でモニターすることや、全例入院にて治療するのは非効率的かつ非現実的である。
②目的
そこで、患者自身で全身状態を把握してもらうことを促し(Patient Engagement)、かつ必要に応じ医療機関とつながるためのシステムを構築することで、効率的で安全な外来化学療法のシステムを構築することを目的とする。医療資源としての可能性を秘めた患者参画による医療の効率化と、治療の安全性を両立することがねらいである。また、患者自身の医療への参画により、自己決定感が向上し、治療における満足度が高まることも期待される。
助38-36
生体の電気素子「イオンチャネル」の電圧感知機構
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
脳や心臓の活動に代表されるように、細胞膜を介した電気的シグナリングは我々の生命活動にとって重要な役割を果たしている。その電気活動を発生させ制御する中心的な役割を担う分子が電位依存性チャネルである。しかしながら、電位依存性チャネルが膜電位を感受できる分子機構の詳細、特に分子構造の変化は未だに明らかになっていない。
②目的
本研究は、電気生理学的手法、光学的観測手法を用いて、電位センサーの動きをダイナミックに解析し、電位依存性チャネルが膜電位を感じとるメカニズムを分子構造のレベルから明らかにすることを目的に行う。最小単位の電位依存性チャネルとして機能する、電位センサードメインのみからなる電位依存性H+チャネル(Hv チャネル)を用いて研究を進め、全ての電位依存性チャネル共通に成り立つ原理を理解を目指す。
助38-37
車いす介助初心者のスキル向上のための車いす介助訓練システムの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
近年の超高齢化に伴い、高齢者の介助は我々の生活の身近にあり、その負担低減が強く望まれている。介助の中でも、移動介助は生活に密接に関わるものであり、特に介助者が車いすを押す介助動作では、熟練者と初心者においてその疲労などの身体負担が大きく異なり、初心者における負担軽減は急務である。
②目的:課題設定とねらい
車いす介助者の身体負担に関する研究は様々実施されながらも、熟練者と初心者間における車いす介助動作の力学特性の違いについては十分に議論されていないため、熟練者がもつ負担低減に効果的な因子が明らかにされておらず、初心者に教示すべき、負担低減に効果的な車いすの介助動作はいまだ確立されていない。本研究の目的は、車いす介助における熟練者の車いす操作の工学的解明とその操作を規範とした介助力学モデルの構築、それに基づいた車いす介助訓練システムの開発である。
助38-38
顔見知り看護師の存在による短時間の手術室看護システムの構築-生体的指標を用いて
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
手術を受ける患者は、手術をめぐる不安、既往歴や手術歴からくる不安、術中死への不安など、様々な不安を強く感じている状態にある。術前の強い不安は術後回復に影響を及ぼし、過度の不安は麻酔導入に悪影響を与えて患者の合併症によっては予後にも影響するため、手術を受ける患者への心理的援助は重要である。多くの医療施設において、手術室看護師は術前訪問を実施して術前から手術を受ける患者への心理的援助を行っている。日本手術医学会は手術を担当する看護師による術前訪問を推奨し「術前訪問により術前に患者と顔見知りになり、手術中のコミュニケーションを円滑に図ることができたなら、患者は大いに安心感を持って手術に臨むことができる」として、術前訪問の実施、顔見知り看護師の存在、円滑なコミュニケーションの重要性を提唱している。これは、同一看護師による術前から手術当日の患者の受入れまでの一貫した患者への関わりが、手術を受ける患者への安心感の増大につながることを示唆している。
手術当日に患者が手術室に入室してから麻酔導入されるまでの時間は非常に短い。手術室看護師は患者の安全・安楽を保証することを目標とし、非常に限られた時間の中で患者への生体モニターの装着、点滴介助といった手術前準備や麻酔介助と並行して患者の心理的援助を行う必要がある。時として手術室看護師は患者への心理的援助が不十分であると感じつつ麻酔導入に至る場合があり、患者への心理的援助の重要性を感じながらも援助の在り方にジレンマを抱えている実情がある。
手術室での患者との短時間の関わりの中で、患者の心理状態を主観的に評価することは困難である。そのため、客観的指標となる生理機能を観察することで、心理的援助による患者の心理状態の変化を評価することを着想した。なぜなら人間の生理機能は情動と密接な関係にある自律神経に支配・制御されており、精神的な興奮や不安によって変動する心拍数や呼吸数の値は患者の心理状態を反映するため、生理機能の値が客観的指標になると考えたからである。
②目的
本研究の目的は、患者の心理状態の客観的指標としてウェアラブルデバイスを用いて、顔見知り看護師による心理的援助の効果を可視化し、短時間の手術室看護システム構築の基盤的データを得ることである。
助38-39
3次元Foot Scannerによる子どもの足部の発達評価システムの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
小学生の外反母趾や踵の外反などの足部変形が急増している。一方で、中高年の変形性膝関節症は、2570万人に発生しており、要介護、転倒骨折、高齢者医療費の高騰、日常生活機能の低下の点で社会問題となっている。この要因の1つが足部の発達にあると考えられる。発達の観点から、子どもの足部は軟骨で構成されており、適切な刺激により骨形成と神経・筋の発達が促される。合わせて、歩行に寄与する足爪が正常に育成されるが、末節骨への荷重不足や不適切なケアで爪(巻き爪等)や指先が変形する例もある。
先行研究では、子どもの足部の研究のキーワードとして、「扁平足」、「肥満」が挙げられ、扁平足の指標として舟状骨という中足部を手作業で計測したものが多いが、十分な知見が得られているとは言えない状況である。[Mickle K, et al: The feet of overweight and obese young children, Obesity, 2006, Pfeiffer M, et al: Prevalence of flat foot in preschool-aged children, Pediatrics, 2006]
②目的
子どもの外反母趾などの変形の増加の原因は、A. 遺伝的影響と発達の状況、B. 歩行や運動の影響、C. 靴などの外力、D. 怪我や病気が挙げられる。外反母趾や回内足などの足部の変形のリスク評価には、その発生メカニズムからA、Bについてバイオメカニクスの観点から 動的(荷重・非荷重位)、静的(静止)に解析しなければならないと考える。
これらを踏まえ本研究では、足部の骨格評価の新しい計測手法を提案し、学校健診などで利用できるヘルスエンジニアリングに寄与するスマートデバイスを用いた足部3次元Foot Scannerを開発することを目的とする。
助38-40
ポータブル眼科医療機器を利用した遠隔画像診断支援システムの構築
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
世界の失明原因の35%は白内障、21%は屈折異常(角膜混濁など)と、原因の半分以上が適切な診断・治療により回復が可能な疾患である (Lancet Glob Health 2017)。特に発展途上国では、白内障による社会的・経済的損失の割合が非常に高い。ではなぜ、発展途上国では十分な眼科医療が行き届かないのか。「金銭的に貧しく医療を受けられない」「現地における医療従事者の不足」「高齢化」以外にも理由があるに違いないと思った申請者は、2017年にNPO法人ファイトフォービジョンに入会し、実際にベトナムの医療過疎地域に出向、無償白内障手術ボランティアに参加することで明らかにしようとした(2018年、2019年も同様に活動した)。そこで判明したことは、「そもそも眼科医療機器が不足している」、ということであった。次に、眼科医療機器不足の原因は何か、という疑問が生じた。既成の眼科医療機器(細隙灯顕微鏡:主に前眼部を診察する機器、眼底鏡:主に眼底を診察する機器)には問題点が多く、その問題点とは①機器が極めて高価、②固定式あるいは記録が不可能、③1台で全ての診察が完結しない (細隙灯顕微鏡と眼底鏡が独立した機器として両方診察に必要)、といった事柄に代表される。これらの問題の解決策として申請者グループは、“Smart Eye Camera眼診療機器 (SEC)”という、スマートホンアタッチメント型の眼科診察機器を開発した。
SECを使用すると、非眼科医でも眼科診療を行うことができる様になり、スマートホンを介した眼科遠隔診療が可能となる。例えば、今年話題となっているCOVID-19の影響のように、医療機関を気軽に受診できないような環境が今後も懸念される場合非常に有用であると考える。しかし得られた画像の診断は非眼科医では困難である。そこで本研究では、①SEC含むポータブル眼科医療機器の有用性を証明すること、②撮影された画像データから眼科画像診断プログラムを作成し、眼科疾患の早期発見に繋がるシステムを作成すること、の2つを目的とする。
助38-41
新世代汗中乳酸計測ウェアラブルデバイスを用いた筋疲労の定量化研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
生物において、エネルギー代謝経路は酸素を使うTCAサイクル(いわゆる有酸素運動)と、酸素を使用しない解糖系(いわゆる無酸素運動)に分けられることは生化学研究における基本として広く知られている。臨床医学においても米国心臓病学会「心血管疾患リスク低減のための生活習慣マネジメントのガイドライン」にて、脳心血管疾患の強いリスク因子である血清コレステロールおよび血圧を低下させるために、有酸素運動を40分間、週3-4回実施することが推奨されている通り、有酸素運動の重要性が取り上げられている。
臨床において運動負荷を上昇させることで運動代謝が有酸素から無酸素代謝に切り替わる事がよく知られており、このタイミングは無酸素代謝により血中乳酸が発生する事もしくは呼気ガス中CO2が上昇する事で測定されている。前者を乳酸性閾値(Lactic Acid Threshhold: LTポイント)、後者を嫌気性代謝閾値(Anaerobic Threshhold: ATポイント)と呼称される。臨床で使用される‘有酸素運動’とは同ポイント付近での運動強度を意味し、医療においては血液乳酸での測定が侵襲的かつ運動中の頻回の採血を要し困難であることから、呼気ガス分析装置を用いたATポイント測定が行われ運動処方として患者に指導されている。一方同装置は巨大かつ煩雑、高コストであることから普及には至っていない(心臓リハビリテーションにおいては専門施設のうち17%の普及率である)。我々はこれまで汗中乳酸を連続的に測定することが可能なウェアラブルデバイスの開発を進めており、簡便かつ低コストな同装置で汗LTポイントの計測に既に成功している。現在医療機器としての開発を進めているが、同デバイスは代謝の変化のみならず、疲労物質としての側面を持つ乳酸を運動中簡便に測定できることから疲労研究分野でも高いポテンシャルを持つ。
②目的
汗中乳酸ウェアラブルデバイスを用い今まで不可能であった運動疲労のみえる化および定量化を可能にする。
助38-42
骨格筋リボソーム量の減少に着目した模擬無重力に伴う筋萎縮の機序解明と電気刺激による予防効果の検討
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
2020年商業宇宙旅行がスタートするなど、我々が宇宙空間で生活する未来も遠くない。しかし、長期間の宇宙滞在はヒト生体に様々な影響を与える。特に、無重力により誘発される骨格筋萎縮は重大な問題であり、骨格筋量・機能の低下は肥満や糖尿病といった代謝疾患、アルツハイマー病、がんなどの疾患の病因となることが疫学ならびに実験生物学により明らかとされている(Hood et al., 2019)。したがって、ヒトが宇宙空間で生活するには無重力により誘発される筋萎縮のメカニズム解明および予防法の確立が必要不可欠である。
地球上における無重力の影響の検討には、模擬無重力モデルである、尾部懸垂マウスが広く用いられている。尾部懸垂は宇宙環境と同様の筋萎縮を誘発するが、その要因の1つに筋量を正に制御する筋タンパク質合成の低下が挙げられる。この原因究明に関する先行研究は、尾部懸垂によるmTORシグナル経路(タンパク質翻訳開始制御因子)の減弱や酸化ストレスの蓄積など、リボソームにおけるタンパク質合成速度に影響する因子に焦点を当ててきた。しかし、これらの因子に対するアプローチにより部分的には筋萎縮を抑制できるものの、その程度は十分ではない。一方で近年、骨格筋のリボソーム量が筋タンパク質合成を正に制御することが新たに明らかとなってきた(Stec et al., 2016; Kotani et al., 投稿中)。尾部懸垂によりリボソームの量が減少することは既に報告されていることから(Mirzoev et al., 2016)、尾部懸垂による筋タンパク質合成低下の根本的な原因は、タンパク質合成の場であるリボソームの量の減少にあるのではないかと申請者は考えた。また、申請者は骨格筋への電気刺激(EMS: Electrical Muscle Stimulation)は、骨格筋のリボソーム合成を活性化し、リボソーム量を増加させることを明らかにしている(Kotani et al., 2019)。この知見より、無重力環境でも実現可能なEMSがリボソーム量の減少予防に効果的である可能性が高いと考えられる。
②目的
本研究では、無重力環境により誘発される筋萎縮のメカニズム解明および効果的な予防法の確立を目指して、以下の項目を検証する。
1.尾部懸垂によるリボソーム量の減少は筋萎縮の要因か否かを明らかにする。
2.尾部懸垂中のEMSは、リボソーム量の減少を予防できるか否かを明らかにする。
助38-43
大学生のインターンシップは就職後にも効果があるのか-就職・採用におけるマッチング機能の有効性の検証-
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
本研究は、大学生のインターンシップ(以下「IS」という)の就職に係る効果が就職後も有効であるのかを定量的に分析し、ISの就職・採用に係るマッチング機能の有効性を検証するものである。若年者の就職・雇用問題は多くの国の政策的課題となっているが、学生の志向が大企業に集中し、企業も学生の能力を十分に把握できないなど双方の情報不足・ミスマッチが存在している。これらを軽減する一方法としてISが考えられるが、日本では数日という世界的にみて特異な短期ISが一般化している。また、ISを就職・採用に関連付けることは政府の方針等もあり、一種のタブーが存在している。しかし、欧米や中国などでは在学中にインターンシップを行い、双方の情報不足を補うことにより就職・採用につなげていくことは一般的であり、マッチング機能の一つとして機能している。日本の現行の就職・採用システムでは、就活日程の早期化、大学教育の形骸化、インターンシップの短期化などの歪みが生じており、こうした労力を双方が過大に負担しながらも決して満足する結果が得られておらず、新たなマッチング機能の構築が急務であるといえる。
②目的:課題設定とねらい
申請者はこれまでの研究において就職・採用時に着目してきたが、本研究では、就職後数年後(5年程度を想定)に着目してその有効性を定量的に検証することを目的とする。具体的には、入社後のISの有効性の指標を企業の実情把握、同一企業勤務、仕事の満足度などとし、これらの有効性をより高める要因なども明らかにする。具体的なリサーチクエッションは以下のとおりである。
(a):【企業側の視点】採用方法の相違(ISの活用やその具体的内容)により入社時と入社後の能力把握の確度にギャップはあるか、従業員の定着はどうか。また、欧米の場合は欠員補充が一般的であり、新卒一括採用中心の日本にも当てはまるか。
(b):【学生・従業員側の視点】就職方法の相違(ISの活用やその具体的内容)により入社時と入社後の社風等の実情把握の確度のギャップ、現在の仕事の満足度、離職率などに相違はあるか。
(c):(a)及び(b)よりISのマッチング機能の有効性を高める要因は何か。ISの内容(期間など)や企業特性、学生・従業員の特性による違いはあるのか。
助38-44
製造業従業員の働きがいと労働生産性の向上を両立させる新たな指標の開発およびその実証研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
日本の労働生産性の低さが指摘されて久しい。OECDデータに基づく2018年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たりの付加価値額)は、46.8ドル(購買力平価(PPP)換算)で、米国の74.7ドルのおよそ6割強しかない。これはOECD加盟36カ国中21位であり、主要先進7カ国でみると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いている。業種で見ると、製造業はサービス業に比べ高い水準を保っているものの、総出荷額約300兆円、総従業員数約750万人の巨大産業において労働生産性を高めるインパクトは大きい。特に化学工業や石油製品など、一部の資本集約的な産業は比較的高い水準を維持している一方、食料品や生産用機械器具など、作業の主要箇所に人手を要する労働集約的産業では労働生産性が上がらず、またこれらの多くは地方に立地していることから、当該地域の経済成長を阻む要因となっている。そのことが結果的に地域の労働力確保の足かせとなり、昨今の人材不足に拍車をかけている。つまり、これら多くの地方製造業の現場では、労働生産性の相対的な低下と人材不足の二重苦のスパイラルに陥っている。他方、働きがいに関する指標においても、日本は諸外国に比べ低い水準にある。『ベター・ライフ・インデックス』(OECD)、『世界のエンゲージメントと職場環境実態』(Steelcase社)、『従業員エンゲージメント・サーベイ』(Gallup社)など、世界各国で比較可能ないずれの調査においても日本は世界最低水準にある。例えばSteelcase社の報告では、職場環境満足度において日本は世界20カ国のうち最低で、他のどの国よりも職場への不満が強く、また職場環境に対する愛着も低い。
②目的
上記の問題意識を受け、本研究は主に地方における労働集約的性質の強い製造業に従事する従業員を対象に、彼らの働きがいと労働生産性の向上を両立させる仕組みを開発し、社会実装することを目的とする。これはSDGsのゴール8『働きがいも経済成長も』の実現に直結する。大学において働きがいと生産性を両立させる新たな指標を開発するとともに、協力企業においてその成果の実証試験を繰り返し、将来的に新製品や新サービスに実装することで広く社会に普及させていくことを目指す。
助38-45
ポストGIGAスクールを支える、ICTを用いた学習者中心の教育方法の開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
ICTを活用した教育が世界標準となり(OECD, 2019)、プログラミング教育が各国の学習指導要領に取り込まれている(European Schoolnet, 2016; Jitsuzumi et al., 2019)。日本でも文部科学省から、児童生徒へ1人1台のPC端末を配布し、学校のインターネット接続環境を増強する「GIGAスクール構想」が発表された(文部科学省, 2019)。しかし、ICTという道具のインパクトに隠れて議論が遅れているのが、ICTを活用した効果的な教育方法の整備である。この教育方法として産業界は「AIドリル」の開発を進めているが(経済産業省, 2019)、AIドリルは1990年代に姿を見なくなったCAI(Computer-Assisted Instruction)と同様ではないかと指摘する声もある(安西, 2020)。AIドリルとは一般的に、正解が明確に定まる算数や国語などの問題を予め用意して1問ずつ子どもへ出題し、その子どもの回答の正誤を児童判別して子どもの苦手分野を推測し、その苦手分野の中から次の問題を選択して出題するシステムである。これは一定の知識を蓄積するために有効である一方、学習者が自分なりに学んだ知識を組み合わせて問題を解く能力の育成が困難であることが指摘されており、AIドリルにも同様の限界が想定され得る(白水, 2020)。2020年度からの新学習指導要領では、解き方やゴールが明確でない問題に対して、必要に応じて仲間と協働しながら、自分たちが知っていることを組み合わせて対応方法を考案できる主体的な学習者の育成が目指されている中で、正解が一意に定まる整理された問題が自動的に与えられるAIドリルの効果は未知数である。
②目的
そこで本研究では、GIGAスクール構想による児童生徒の1人1台端末配布後の日本において、主体的・対話的で深い学びを実現するためにICTを活用する教育方法を、学校現場の教師とともに整備することを目的とする。このために、ICTを活用した教育をすでに展開している地域の先導的な小学校教師らと大学の間の既存の連携関係を活かして実践研究を推進する。
助38-46
ストーリー中心型教育におけるチャットボットの活用が学習意欲に与える影響に関する開発研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
高等教育機関においては、専門知識を獲得させる方法として基礎からの積み上げ式によるカリキュラムが編成されることが多い。これは専門知識の着実な獲得が期待できる一方で、学ぶべき基礎的内容が増えている現在では、得られた専門知識を応用する場面が不足しがちになり、ひいては「何のために学ぶのか」を見失う学習者も少なくない。
学習内容を実社会・実生活に結び付けながら専門知識を学ぶアプローチの一つとして、教授設計学(Instructional Design)の領域では、ストーリー中心型カリキュラム(Story-centered Curriculum;SCC)が提案されている。SCCはGBS(Goal Based Scenario)理論に基づいている。GBSは現実的な文脈の中で「失敗することにより学ぶ」経験を疑似的に与えるための学習環境として物語(ストーリー)を構築する理論である(根本ほか 2014)。SCCを使ったカリキュラムの代表例である熊本大学大学院教授システム学専攻では、学習者は中途社員という役割が与えられ、業務に取り組むというストーリーの中で専門知識を獲得していくことが確認された(根本ほか 2011)。一方で、熊本大学での実践における課題の一つに学習者の没入感がある。没入感向上のためには、もちろんストーリーそのものの改善も考えられるが、本研究ではストーリーを展開するプラットフォームに着目した。近年のスマートフォンの普及に伴い、学習者が身近に利用しているコミュニケーションツール(LINE等のテキストチャット)を用いることで、学習者はストーリーをより親密に感じるようになり、没入感の向上が期待できるのではないかと考えた。
②目的
「SCCにおいてより没入感を高め、学習意欲を維持するためのオンライン学習環境とは何か」という問いを立て、本研究では「シナリオ操作にテキストチャットを用いることの効果」を探る将来の実証実験に向けて、テキストチャットツールの開発と改善点の明確化を目的とする。
助38-47
伝統産業の持続的創造性を支える場所ベースのリーダーシップ:石川県と香川県の漆芸プロジェクトを中心に
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
少子高齢化と人口減少が進行し、各地域は地域の個性を活かした地域活性化が求められているが、各地の多くの伝統産業は市場の成熟、嗜好性やライフスタイルの変化に適応できず衰退傾向にあり打開策を模索している。停滞状況を脱するには、従来の伝統を活かしつつ、製造業の他業種、ファッション、農業、飲食業、旅行業、出版など多様な産業との協働によって新たな商品開発を行い、潜在的市場を開拓して高級消費財を製造する方向性が考えられるが(柴田,2015)、Piore&Sabel(1984)が定式化した同一産業集積内での柔軟な専門化による需要変化対応を超える創造的協働が求められる。創造産業は大都市における多様な産業の厚い集積を空間的基盤にプロジェクト毎に必要なプレーヤーが離合集散するプロジェクトエコロジーをダイナミズムの源泉とするが(Grabher,2002; Scott,2008;原,2013)、地方においては単一産業集積としての地場産業は各地にあるものの、創造的プロジェクトに必要とされる多様な産業の厚みに欠ける。佐々木(1997) が論じる創造都市論で金沢市はそのモデルとされるが、創造都市論が表面的全体論と部分的分析であり、創造性のメカニズムが欠けていると批判されるのは(渡部,2012)、相対的に集積の厚みに欠ける地方で継続的にプロジェクトを実施するため大都市とは異なるプロジェクトエコロジーをどのように成り立たせているのかを解明できていないからと考えられる。近年、場所ベースのリーダーシップ(place-based leadership)が注目されているが(Hambleton, Sotarauta,2016;Beer et al.,2019;Vallance et al.,2019)、日本における検討はほとんど行われていない。こうした学術的な意味でも、先述した地方創生という実践的な意味においても、日本の特性を踏まえた場所ベースのリーダーシップ研究が望まれる状況となっている。
②目的
こうした問題意識の下、日本的な特徴を有し場所ベースのリーダーシップが期待される代表的な対象として地方における伝統産業に注目する。本研究は、場所ベースのリーダーシップとして、地方の伝統産業において多様な協働によりクリエイティブプロジェクトを持続的に行っているプロジェクトリーダーに焦点をあてて分析を行い、集積の厚みに欠ける地方において持続的なクリエイティブプロジェクトを成り立たせている地方版プロジェクトエコロジーのダイナミズムにおける場所ベースのリーダーシップの役割を解明することを目的とする。創造都市の取組みで有名な金沢市のある石川県と国際芸術祭で有名な香川県を二大産地とする漆器産業と、そのクリエイティブプロジェクトを研究対象とする。
助38-48
APD(聴覚情報処理障害)に対する教育支援法の実証的臨床研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
近年、新たな聴覚障害として、聴覚情報処理障害、APD(Auditory Processing Disorder)の存在が指摘されている。欧米圏では既に障害として広く認知されており、ICD-11(国際疾病分類第11版)に登録されるに至っている。しかし、我が国においては、日本語ベースの聴覚情報処理障害の診断・評価・教育的支援法に関する研究者は極めて少数であり、立ち遅れた現状にある。
そもそも、聴覚情報処理障害(APD)は、「聴力閾値の悪化はないものの、騒音下において言語理解が難しい、環境音と言語音の識別が難しいなど、語認識に特異的に困難が生じる障害」と定義されている。APD児は、聴力閾値には問題がみられないため、聞こえにくいという形で気付かれることがなく、教室での聞こえにくさの結果による学習の遅れや困難によって気付かれている。そして、その学習面での困難さに対して、LD児(学習障害児)として対応されており、適切な教育的支援が行われていない。
②目的
立入は2020年3月迄の期間、八田が研究代表者である科研(基盤C:18K02768)の共同研究者として、iPad上で動作する評価ツール・教育支援のアプリ開発を行った。すでに同科研費研究において、大学生を対象にした成人標準値を求め、さらにAPD疑い児2児に対して適用を行い、APDの評価が可能であることを明らかにした。そこで、作成ししたアプリをさらに多くのAPD児に実施し、APDの評価に使用できることを実証したい。本アプリはAPD評価だけではなく、APDの教育支援法として、DIID※法による、弱い音圧の語やノイズ下での聞こえを向上させるアプローチも実施できるように設計されている。本研究により、本アプリの有効性の検証と、DIIDによるAPDに対する対原因療法の実証を行うことで、APDに対する教育支援アプローチを対処療法から、対原因療法に転換するこに目的がある。
※DIID=Dichotic Intensity Increase Difference:アメリカ・EU圏で広く用いられているAPDハビリテーション法の一つ
助38-49
批判的思考力の育成と評価を志向した中等数学教材の開発とその実証的研究
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
人口減少、少子高齢化、エネルギー・環境制約問題など、我が国の様々な社会的課題に対し、その解決が求められる未来の子ども達が身に付けるべき資質・能力とは何か。本研究では、新学習指導要領においても教科等を越えた全ての学習の基盤として、その育成が期待されている批判的思考力に焦点を充て、この能力の涵養を新たな未来社会の実現の鍵の一つとして、子ども達に求めてみたい。汎用的能力である「批判的思考力」に関する研究は、教育学や心理学、哲学などの分野では古くから盛んに研究が進められているものの(例えば、Ennis,1987; Paul,1995)、数学教育という教科教育学的な実践研究は国際的にも国内的にも未だ端緒に就いたばかりである(例えば、Fonseca & Arezes, 2017;久保,2016;島田,2016)。そして、その研究内容は、どのような教材で如何にして生徒の批判的思考力を育むのかといった教材開発、指導法研究が中心で(久保ら、2019;服部・福田、2019など)、生徒の発揮した批判的思考力を適切に特定し、どのように評価をするのかといった新たな課題が現在顕在化しているところである。「生徒の発揮した批判的思考力を如何に評価するのか?」このリサーチクエスチョンは我が国の教科教育分野のみならず、国際的にも未解明で急務の課題として指摘できる。
②目的:課題設定とねらい
本研究では、中学校高校数学教育に焦点をあて、批判的思考力の育成を目指す教材の開発に加え、実践を通して生徒の発揮した批判的思考を適切に評価するプログラムの開発を行うことを研究の目的とする。より具体的には、「Ⅰ.中学校・高等学校数学授業における批判的思考力を育成する教材を開発し、実践に向けた教授・学習方法を構築すること」、「Ⅱ.Ⅰの授業実践を通して、生徒が発揮した批判的思考力の特質を解明するため、批判的思考を定量的に評価する手法の開発を行うこと」、「Ⅲ.生徒の発揮した批判的思考を分析的に捉えることのできるルーブリックの開発」の3点を本研究の課題設定とねらいとする。
助38-50
「掛かりつけ農家」をハブとする社会的ネットワークの経済的合理性と頑健性の検証
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
日本の土地利用型農業は大規模化による生産性の向上を第一義として、基盤整備等の土地改良事業や特定の企業的農業者への日本集中を進めてきた。そして、一般市場におけるブランド化や輸出などの販路拡大が推奨され、多くの日本の集落農業が変質してきた。他方で、中核農家の高齢化や米価下落により、規模の経済性による農的産業強化には依然として課題が残っていた。他方で、以前から大規模経営のオルタナティブとして存在してきた比較的小規模経営農家で、特定の顧客と強固なブランド力を築き、密なコミュニティを構築してきた農家が、新型コロナ状況下で頑健性を発揮し、著しい損害を出さずに経営を継続してきたという事例は、国内各研究機関が行った調査の速報に共通して見られている結果である。そのような固有の生産者・消費者関係は、地域医療に準えて「掛かりつけ農家」と呼ばれることがあり、今般の新型コロナのように今後も起こりうる不確実状況下での地域農業のあり方として期待できるものと考える。
②目的
生産効率を高めることは経営における競争優位の定説であるにも関わらず、なぜ新型コロナ環境下で大規模農家が大きな損失を生み、掛かりつけ農家として機能する小規模農家が頑健であったのか、その実態解明は学術的に高い関心対象である。そこで、規模拡大による企業的経営の脆弱性が曝露する地域農業の現局面を踏まえて、そのオルタナティブとして、生産や経営理念に共感した密な繋がりを基軸に、外部の競争環境とは異なるソーシャル・マーケティング手法(別称:共感マーケティング)による経営展開を実践する中小規模農家(掛かりつけ農家)の経済的合理性と頑健性を例証することを目的とする。事例とするのは、本研究が想定する「掛かりつけ農家」のモデルとして的確な県内の経営体とし、当該農家をハブとして繋がる消費者コミュニティのネットワークを解析対象とする。
研究方法として、ハブとなる農家にはWebインタビュー(新型コロナによる行動制限が解消されれば対面)による情報収集を行う。実験区となる消費者コミュニティに対してはWebアンケート及びWebインタビューを実施し、対照区となる一般消費者に対してはWebアンケートによって情報収集を行う。そして、強みの源泉となる、定常時と否定常時の生産・販売行動と消費行動の特殊性を明らかにする。
助38-51
先進医療における日本人のための意思決定支援ツールの開発
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
元来、医師が「能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとる」ことが医療倫理であった(ヒポクラテス, B.C.5)。近年、医療の専門化・複雑化と人権の尊重から、十分な情報提供と同意(インフォームド・コンセント)という新しい医療倫理が生まれた(ジュネーブ宣言, 1948)。しかし、現代医学の発展に伴って、進行臓器不全患者は、心身の過酷な状況下にありながら臓器移植を含む、複数の治療に関する多量な情報に暴露され、短期間で治療選択を迫られている。現在、臓器移植術前に精神科医や心理士による心理社会的評価が行われている。しかしながら、個人の治療選択行動に影響を与える生物学的・心理学的・社会的要因についてのエビデンスは未だ乏しく、標準化された意思決定支援が無く、かつ実施自体が現場に任されていることが、進行臓器不全医療における大きな倫理的課題である。近年、西欧特に米国において、臓器移植候補者に対して精神科医・心理士によるコンサルテーションが行われるようになった。移植前の心理社会的および行動的側面をスクリーニングするための評価尺度が開発され始めたが、国際的にも評価の内容と方法の標準化が進んでいない。スタンフォード大学臓器移植前心理社会的評価尺度(SIPAT)は、2012年に米国で開発された。PACTに比して予後予測率が高く、包括的な評価尺度である(Maldonado, 2015)。現在、日本語以外の複数の言語で翻訳が行われており、今後、国際的な評価尺度となることが期待されている。しかしながら、これらの尺度の目的は、移植を行わない患者を選別することであり、患者の支援という発想ではなかった(Denhaerynkck et al, 2005)。
②目的
本研究は、先進医療における日本人患者の治療選択のための意思決定支援ツールを開発することが目的である。そのために、臓器移植候補となる進行臓器不全を有する患者を対象として、SIPATによる評価、さらに年齢、認知機能、心理状態、文化・宗教・家族背景などの背景因子が、意思決定の安定度と移植後の生命予後にどのように影響するかを検証する。これより、心身の状態から患者の文化的背景まで幅広く包括する日本人のための予測妥当性の高い心理社会的評価尺度による意思決定支援ツールを開発する。
助38-52
父母の睡眠覚醒パターンから探る妊娠中および産後の家庭支援
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景:内外における当該分野の動向
子育て支援は、少子高齢化が進む日本社会の持続に直結する喫緊の課題である。少子化は経済成長が著しいアジアでも急速に進んでおり、シンガポール、香港、台湾、韓国は、日本の合計特殊出生率1.43を下回る(1)。一方、環境を整えて、子育てと就労の両立を支援しているフランスやスウェーデンでは少子化に歯止めがかかっており、その対策の有効性が伺える。核家族化が進み、共働き家庭が増えている日本でも就労と子育ての両立支援を求める動向にある。両立支援の第一歩は父母の相互理解を深めることである。妊娠・出産を通して徐々に母親になる実感が高まる女性と、子の誕生とともに突然父親になる男性とでは、子育てスタート時の当事者意識に乖離が生じがちである。ライフスタイルが多様化する今、父母それぞれの生活パターンや心理ストレスの特徴を捉え、実験的裏付けのある具体的な母親向けおよび父親向けサポート法を構築する必要がある。そこで本研究では、父母の睡眠覚醒リズムや生理・心理変化を記録し、これからの子育て支援に寄与する日常生活データを取得する。
参考(1)内閣府 令和元年版少子化社会対策白書
②目的:課題設定とねらい
心身の健康には良質な睡眠が重要である。睡眠不足は、認知機能の低下、不安や気分障害を引き起こす(Palmer & Alfano, Sleep Med Rev, 2017)。特に産後の母親は慢性的な睡眠不足に陥るが、母親の睡眠は、乳児の睡眠時間の長さより、家庭環境の秩序レベルに大きく影響を受ける(Thomas et al, MCN Am J Matern Child Nurs, 2016)。核家族での子育てには父母の協調が必須だが、相互理解の出発点となる父母の日常的な生活パターンや心理変化に関する縦断的な比較検討はなく、実践的な支援構築に至っていない。そこで本研究は、父母の睡眠覚醒リズム、呼吸・心拍、心理ストレスに関する基礎データ収集を行い、「自身のストレスレベルが高まる」あるいは「自分の子や伴侶を含め対人上の衝突が起こる」前の予兆因子を見つけることを課題に設定した。中長期の研究目的は、得られた基礎データを基に各親に合ったストレスコーピングのフィードバックシステムを開発し、子育て支援に貢献することである。睡眠および生理計測は、ウエアラブルデバイスを使って連続取得する。睡眠と精神状態の両方について専門知識が必要となるので、睡眠研究に造詣の深い精神科医の船戸弘正氏と共同研究を行う。
助38-53
衰退都市のコンバージョン——都市縮小時代における都市再開発政策の日米比較
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①目的と問い
「都市が衰退しはじめた時、一体、どのようにして都市を再活性化させるのか」「変化をいかにコントロールするのか」———本研究はこうした一連の問いに答えるための日米比較研究であり、都市縮小時代の都市政策を考えるための、基礎的な歴史社会学的研究である。転換期にある日本の都市問題・都市政策をアメリカと比較し、より深い理解を得ることが目指される。
②背景
持続可能な形で都市を再開発していくことは、焦眉の課題である。建築・都市計画学では、近年、こうした課題を「コンバージョン」をキーワードに研究してきている。その多くは、衰退した団地などを、いかに更新し、新たな用途に対応させるように転換(コンバージョン)させていくかが議論されている。しかし、地域のコミュニティは形態的変化によって大きく影響されてしまう。「地域社会住民にとって望ましいコンバージョンはいかにして可能か」という、社会的位相を踏まえた議論こそが求められている。本研究はまさにこの点に照準を合わせている。
助38-54
自然体験活動における学校教員の危機管理能力向上を目指した視線特徴分析:初心者と経験者の着眼点比較
 【本研究の背景と目的】
【本研究の背景と目的】
①背景
現在、日本の小学校における宿泊を伴う自然体験活動(自然の中で自然を活用して行われる活動)の実施率は、およそ90%となっており、多くの学校で実施がなされている。近年、自然体験活動は、子どもに道徳観・正義感をもたらすなどの効果が各種調査等から明らかになりつつあり、文部科学省(2008)は、自然の中での集団宿泊活動を重点的に推進すべきことと言及している。学校教育の中で、自然体験活動の重要性がこれまで以上に高まっている。
自然体験活動は、通常の学校生活よりも事故が発生しやすいことから、引率する教員の危機管理能力が重要となる。しかし、小中学生や10代・20代の若者が、学校外で自然体験活動(キャンプ含む)を行う機会は減少していることが報告され、教員を目指す大学生が、十分な自然体験活動の経験をしてきているとはいえない(内閣府 2013)。また、教員養成を行う大学においても、その位置づけの難しさから、自然体験活動に関する十分な学習や引率研修を行っているとはいえない状況にある。有する経験も知識も不十分であることを前提にした、危機管理能力育成のための教員養成支援が求められている。
②目的
教員の危機管理能力育成のための効果的な支援を考えるにあたっては、自然体験活動場面で初心者が見落としがちな点や、初心者特有の視線行動を明確化したデータが有用な資料の1つになると考えられる。
そこで、本研究では、自然体験活動経験が少なく、引率経験のない「初心者」と、自然体験活動経験・引率経験ともに豊富な「経験者」に対して、自然体験活動場面での危険予測時の視線移動を計測し、その特徴を明らかにすることを目的とする。具体的には、危険要因が含まれた自然体験活動場面のイラスト(危険予知トレーニングシート)を用いて、その中の危険を見つける過程における視線移動を計測し、初心者と経験者の特徴の違いを比較する。
